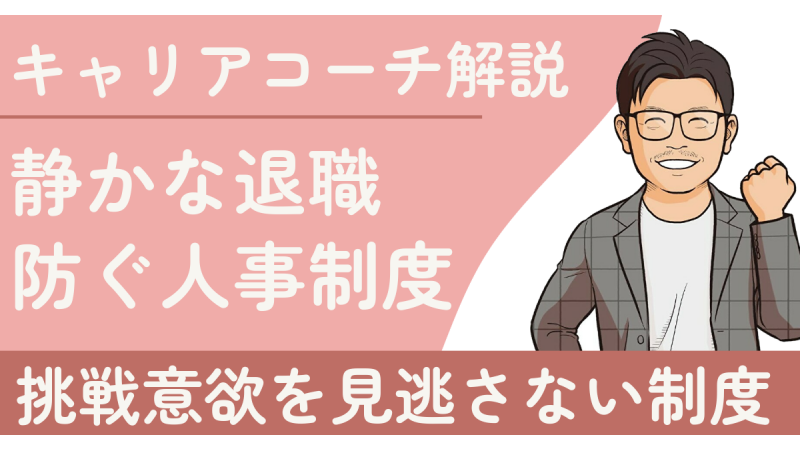
静かな退職を防ぐには?挑戦意欲を見逃さない人事制度のつくり方
静かな退職(Quiet Quitting)を防ぐには?
挑戦意欲を見逃さない人事制度や面談の仕組み、企業事例まで詳しく解説。離職率ではなく『意欲指数』を高める新しい組織づくりのヒントが見つかります。
すべらない転職が紹介するサービスの一部には広告を含んでおり、当サイトを経由してサービスへの申込みがあった場合には、各企業から支払いを受け取ることがあります。ただし、ユーザーの利益を第一に考え客観的な視点でサービスを評価しており、当サイト内のランキングや商品の評価に関して影響を及ぼすことはございません。
静かな退職とは?
静かな退職(Quiet Quitting)とは、従業員が表立って辞めるわけではなく、業務に対する熱意や主体性を失い、与えられた最低限の業務だけをこなす状態を指します。
外からは目立たず、業務時間は守っていても、内心ではキャリアや成長に対する意欲を失っている状態が『見えない退職』です。
この現象はZ世代(20代)だけでなく、30〜40代の中堅社員にも広がりを見せており、企業のエンゲージメント低下や突然の退職リスクにもつながります。
特に近年、キャリアの多様性や働き方の選択肢が増えるなかで「挑戦したい」「成長したい」という想いが受け止められない職場環境が、静かな退職を引き起こす要因となっています。
離職の意思を明確に伝えないまま、徐々に関心を失っていくこの現象は、人事制度やマネジメントのあり方に根本的な見直しを迫るサインでもあるのです。

静かな退職が起きる本当の原因とは?
静かな退職の根本的な原因は、挑戦意欲や成長欲求が無視される組織文化と制度設計にあります。
多くの企業は、福利厚生の充実や給与制度の見直しで離職防止を図ろうとします。しかし、静かな退職の根本的な原因は、そこにはありません。
実際には、次のような深層的な要因が静かな退職を招いています。これらの原因を理解せずに制度だけを整えても、社員の内なるモチベーションは回復せず、エンゲージメントの向上にはつながりません。
評価されない挑戦意欲や自己成長欲求
やる気を持って新しいことに挑戦しようとする社員がいても、その意欲を受け止める場がなければ、やがて諦めへと変わってしまいます。
「どうせ評価されない」「やっても報われない」と感じた瞬間、社員の心は離れていきます。特に若手や中堅社員は、自身の努力や挑戦が会社にどう評価されるかを常に意識しています。
フィードバックが希薄な環境では、彼らは積極的な行動を控えるようになり、結果的に静かな退職へとつながってしまいます。
キャリアパスが見えない組織構造
「この会社にいたら、自分はどんな未来を描けるのか?」が不透明な組織では、社員は目の前の仕事を『こなすだけ』になりがちです。
特に30代以降の社員は、長期的なキャリア形成を見据えた動機付けがなければ、静かに離れていく傾向があります。
評価基準や昇進の基準が不透明で、特定の部署に長く留まらざるを得ない仕組みがある場合、自らの未来に対して希望が持てなくなり、やりがいの喪失に直結します。
上司との対話不足と1on1の形骸化
本来、1on1ミーティングはキャリア相談や本音を引き出す場であるべきですが、実際には業務報告の場に留まっているケースが少なくありません。
上司との関係が希薄なままでは、内に秘めた不満や悩みを打ち明けることは難しくなります。信頼関係が構築されていない場合、部下は「どうせ言っても無駄」と感じ、次第に会社との距離を置くようになります。
このような状況が積み重なることで、社員の意欲は次第に減退し、静かな退職が進行してしまいます。
表面的な福利厚生だけでは離職防止にならない
リモートワークの導入や副業OKなど、制度面では充実している企業でも、内発的動機(挑戦・学び・貢献)が満たされなければ、真の意味でのエンゲージメントは高まりません。
社員が求めているのは、働きやすさだけではなく「成長できる環境」や「自分の意見が尊重される文化」です。
制度だけを整えても、それが活用されなければ意味を持たず、むしろ「うちには制度はあるのに、使える雰囲気がない」という逆効果にもなりかねません。
挑戦意欲を見逃さないための人事制度とは?
静かな退職を防ぐには、制度面で「挑戦したい」という気持ちをきちんと拾い上げ、組織とつなげる仕組みが必要です。
特に、社員のキャリア自律を支援しながらも、企業の方向性とリンクさせる制度設計が求められます。ここでは、挑戦意欲を見逃さず、前向きな行動につなげるための制度設計の考え方と実践例を紹介します。
キャリア自律支援と企業目標の接続
「個人のキャリア」と「会社の目標」が分断されていると、社員は『歯車』として働いている感覚に陥ります。
逆に、社員の挑戦や成長が会社の成果につながる設計ができれば、意欲的な社員は自ら動き始めます。
たとえば、中長期的なキャリアプランを上司と共有し、その中で会社の事業戦略と接続する場を設けることで、社員は自らの存在意義を見出しやすくなります。
このような取り組みは、上司と部下の信頼関係構築にも大きく貢献します。
抜擢人事・社内公募・FA制度の導入
挑戦したい社員に対して、社内でチャンスを与える制度として有効なのが、抜擢制度や社内公募制度です。
たとえば「今の部署で結果を出せば、次のステージに挑戦できる」といった明確なルートがあることで、社員のモチベーションは維持されます。
定期的な公募を行うことで、社員が「自分もチャンスを掴める」と感じられる環境が醸成され、結果的に離職防止にもつながります。
また、抜擢された社員が新たな部門で活躍する様子は、周囲への好影響をもたらし、挑戦の連鎖を生み出します。
OKRやMBOと連動した目標管理制度
評価制度と連動させることで「挑戦すること」自体が正当に評価される環境が整います。
たとえばOKR(目標達成を目的としたフレームワーク)を導入し、社員の挑戦を可視化・共有することで、組織全体に前向きな空気が生まれます。
MBO(目標による管理)を活用する場合も、結果だけでなくプロセスや挑戦自体を評価対象とする仕組みを取り入れることで、失敗を恐れず挑戦できる文化が根付きます。
こうした評価制度の透明性と公平性は、社員の安心感と納得感を高める要素にもなります。

挑戦を歓迎するカルチャーの制度化
「失敗を咎めない」「挑戦者を称賛する」文化が浸透しているかどうかは、制度として可視化することが重要です。
例えば、チャレンジ賞や表彰制度、社内での挑戦事例の共有会などは、制度と文化を接続する有効な手段です。
定期的に成功・失敗にかかわらず挑戦した社員を取り上げることで、組織全体に「挑戦していい」という心理的安全性が生まれます。
こうした文化の醸成は一朝一夕では難しいものの、制度の裏付けがあれば定着しやすくなります。

当社でもこうしたテーマに特化したマネジメント研修サービスを展開していますので、ご関心のある方はぜひお問い合わせページからご相談ください。
社員の『本音』を拾うための仕組みと実践例
制度をつくるだけでは不十分です。社員一人ひとりの内面に目を向け、その『兆し』を早期にキャッチする仕組みが不可欠です。
形式的な制度だけでは見えにくい「感情」や「価値観」の変化を捉えるには、多角的なアプローチと継続的な取り組みが求められます。
定量だけに頼らないサーベイ活用法
定期的なエンゲージメントサーベイを実施している企業は多いものの、スコアだけで判断するのは危険です。
コメント欄に寄せられる『声』にこそ、静かな退職の兆しが現れます。読み解きと対話のセット運用が鍵です。
サーベイの設問設計そのものも重要です。「仕事にやりがいを感じていますか?」「キャリアの未来が見えていますか?」といった主観的な設問を入れることで、数値に表れない違和感を可視化できます。
結果は部署ごと・年代ごとに傾向分析し、適切なアクションにつなげましょう。
キャリア面談やキャリアコーチングの定期導入
「あなたはこの会社で、どんな挑戦をしていきたいですか?」という問いを投げかける場を、意図的に設ける必要があります。
社外コーチの導入など、心理的安全性を確保する手法も有効です。キャリア面談の頻度は年1回では足りません。
目安として半年に一度は、キャリアビジョンや価値観の棚卸しができるようにし、1on1ミーティングとは異なる『キャリア対話』の機会を持ちましょう。
特に20代後半〜30代の社員にとっては、自身のキャリア像と会社の支援方針が一致しているかどうかが、エンゲージメントを左右する重要な指標です。

当社が提供する外部キャリアコーチ派遣サービスを活用すれば、社員が本音を話しやすい環境を整え、個々のキャリアビジョンを言語化するサポートが可能です。
ロールモデル可視化と社内メディアの活用
「挑戦してキャリアを切り開いた社員」の存在を、社内報や公式ブログで可視化することは大きな効果を持ちます。
自分と近しい立場の社員の成功体験は、次の挑戦者を生み出すトリガーになります。
「異動によってキャリアチェンジを実現した社員の事例」や「社内公募制度を利用してステップアップした社員のインタビュー記事」を発信することで、挑戦の道筋をリアルに感じてもらえるようになります。
リアリティのある成功体験の共有は「自分もやってみよう」と思わせるための強力なインセンティブとなります。
静かな退職を防いだ企業事例
ここでは、実際に挑戦意欲を制度的に支援することで、静かな退職を防いだ企業の取り組みを紹介します。
形式だけで終わらせず、実際に成果につながった事例は、他の企業にとっても導入のヒントとなるはずです。
事例1:社内FA制度で挑戦意欲を組織内で循環させたA社
A社では、年2回の社内FA制度を導入。
異動希望を公募で受け付け、選考制で配属を決定する仕組みを整えたことで、社員のキャリアへの納得感が大幅に向上。導入後3年で、30代社員の離職率が前年比20%減となりました。
さらに同社では、FA異動後の「成長レポート」を本人が執筆し、イントラ上で公開する取り組みも実施。これが社内に「挑戦の見える化」をもたらし、他部門の社員の意欲にも火をつけています。
FA制度は単なる異動ツールではなく、「社内に複数のキャリアパスがある」というメッセージとして機能しているのです。
事例2:キャリアコーチング導入で1on1の質が劇的に変化したB社
B社では、外部キャリアコーチとの面談を年1回実施。これにより社員自身のキャリア意識が高まり、上司との1on1も具体的で前向きな内容へと進化しました。
従業員満足度サーベイでは「キャリアへの相談機会」の項目で、前年より15ポイント上昇という結果に。さらに同社では、キャリア面談の内容を(本人同意のもと)上司にも共有する体制を整備。
上司が部下の志向を理解したうえで業務やプロジェクトをアサインできるようになり、結果として個々のモチベーション維持に寄与しています。
コーチングは単なる外部委託ではなく、社内の対話力向上にも直結する好循環を生んでいます。
成功体験談:挑戦を支援されたCさんのケース
IT企業C社に勤めるCさん(32歳)は、もともと営業部門でプレイヤーとして実績を上げていましたが、企画職への挑戦を希望していました。
上司との1on1で思い切ってその想いを伝えたところ、社内公募制度の案内を受け、企画部門の選考にチャレンジ。無事異動が決まり、現在は新規事業開発チームで活躍しています。
Cさん曰く「前職では『やりたい』と口にすること自体がタブーだった。でも、今の会社は『挑戦を歓迎する文化』がある。もし公募制度がなかったら、私は辞めていたかもしれません。」
さらに、異動後には社内で『キャリア体験共有会』に登壇し、自身の体験を他の社員にも発信。「あの話を聞いて自分も公募に応募した」といった反応が続き、社内で新たな挑戦者を生むきっかけとなっています。
このように、個々の意欲を制度で受け止め、さらにそれを文化に転化できるかどうかが、静かな退職を防ぐ大きな分岐点となるのです。

当社では、静かな退職の予防を目的としたキャリア支援型人材開発プログラムやエンゲージメント強化研修を提供しており、初めて制度を導入する企業様にもご活用いただいています。
まとめ:静かな退職を防ぐには制度と対話の両輪が鍵
静かな退職は、突然の退職よりも発見が難しく、組織にじわじわとダメージを与える厄介な課題です。
しかし、挑戦意欲を制度として拾い上げ、日々の対話でそれを支援する仕組みがあれば、確実に防ぐことは可能です。
いきなり大きな制度改革は難しくても、まずは「挑戦したい気持ちを聞く」「異動希望を受け付ける」「キャリア面談を始める」など、小さな一歩からでも変化は始まります。
組織における『挑戦の見える化』が広がれば、次第に社員同士の刺激や学び合いも活性化し、組織全体の風通しもよくなっていきます。
また、『離職率』だけに目を向けるのではなく、『意欲指数』や『挑戦率』といった新たなKPIを設けることも有効です。
社員がどれだけチャレンジしているか、成長に向けてアクションを起こしているかといった視点を可視化することで、組織の活性度や将来性がより明確になります。
これからの人事には「制度」と「対話」という両輪をもって社員と伴走し、キャリア自律を支援しながらも企業価値の向上に結びつける視点が不可欠です。
静かな退職を防ぐことは、人材流出を防ぐだけでなく、挑戦が連鎖する前向きな組織づくりの第一歩でもあるのです。
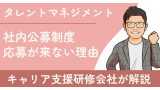
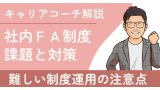
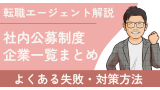
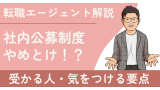
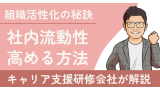
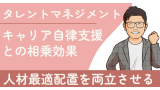
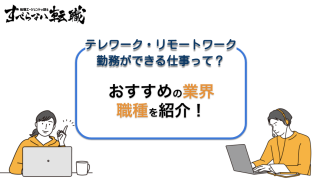
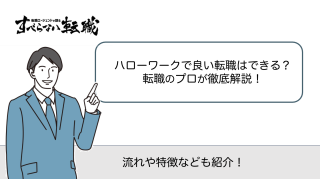
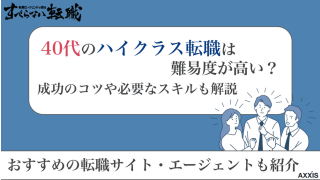
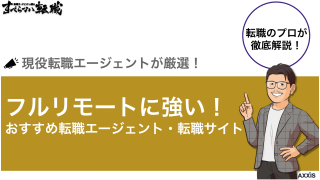
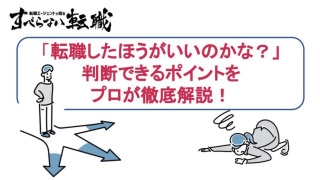
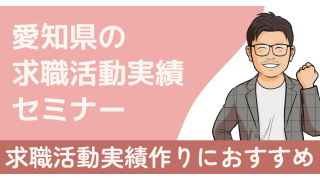
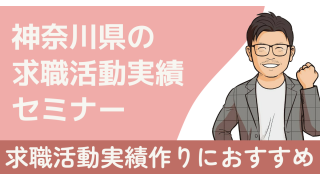
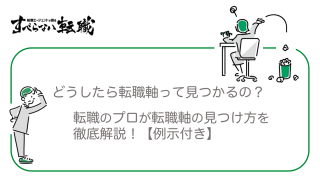
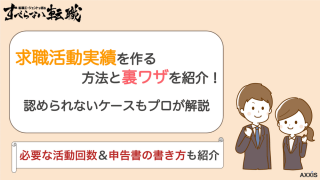
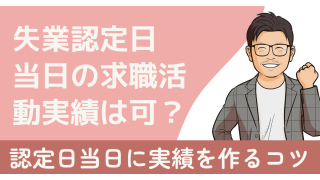







静かな退職を防ぐには、社員の挑戦意欲をすくい上げる仕組みと対話の場が必要です。なぜなら社員は「辞めたい」とは言わずとも、心のなかで職場との距離を取り始めるからです。