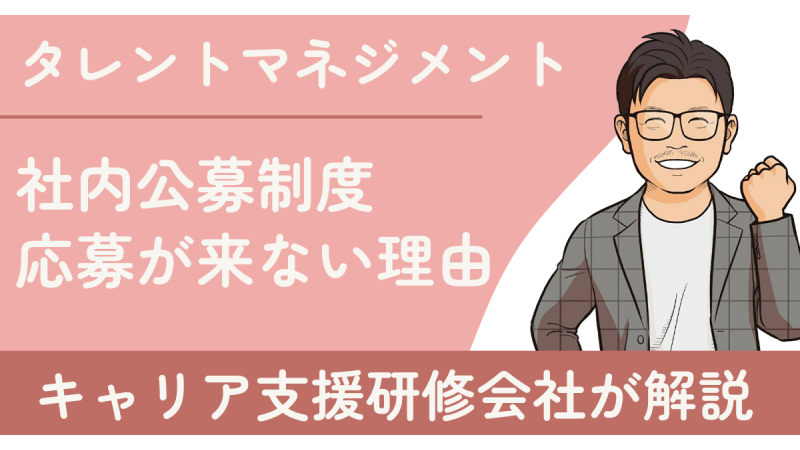
社内公募制度に応募がこない理由とは?よくある失敗と効果を高める改善策
「社内公募制度(社内FA制度)を導入したのに、誰も応募してこない…」そんな悩みを抱えていませんか?
社員のキャリア自律や社内の人材流動を促すはずの制度が、形骸化している企業は少なくありません。応募が集まらない背景には、制度の周知不足、募集内容の不明瞭さ、そして“見えない心理的な壁”が存在します。
本記事では、社内公募制度が機能しない理由と失敗事例、社員が自ら応募したくなる仕組みへと見直すための具体的な改善策を、キャリア研修支援サービス会社の専門家の視点で詳しく解説します。
すべらない転職が紹介するサービスの一部には広告を含んでおり、当サイトを経由してサービスへの申込みがあった場合には、各企業から支払いを受け取ることがあります。ただし、ユーザーの利益を第一に考え客観的な視点でサービスを評価しており、当サイト内のランキングや商品の評価に関して影響を及ぼすことはございません。
社内公募制度を整えても、社員は動かない?
社員の主体性を引き出し、適材適所の配置や組織の活性化を促す「社内公募制度」を取り入れている企業は多いです。
多くの上場企業が導入を進めていますが、実際に社内転職制度(ジョブチャレンジ制度)を運用してみると「応募がこない」「制度が形骸化している」といった悩みを抱える人事担当者は少なくありません。
制度としては魅力的なはずなのに、なぜ社員は応募しないのか。制度を導入しただけで満足していませんか?
本記事では、社内公募制度がうまく機能しない背景を深掘りし、応募が集まる制度に変えるための具体的な改善策をお届けします。社員が『本気で応募したくなる』制度設計のヒントを、ぜひ参考にしてください。
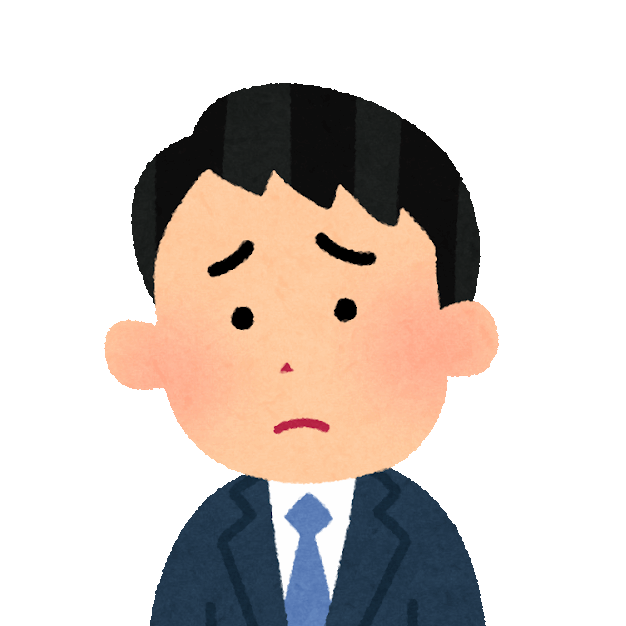

当社宛にこのような相談をいただくケースが増えています。数千人規模の会社でも一人で運用している会社がありますが、一人ではまず適切な運用は無理だと言えます。

当社は社員の適性やキャリア軸に沿った社内異動の最適化支援サービスを提供しています。社内異動制度(社内公募制度)の運用上の問題点はケースバイケースですが、大手企業が陥っている問題点をまとめました。
社内公募制度で応募がこない主な理由
社内公募制度の意図や目的が伝わっていない
社員が社内公募制度の意味や目的を理解していなければ、そもそも応募には繋がりません。
「応募したら裏切者扱いされて今の上司に嫌な顔をされるのでは?」「仮に落ちたら評価に影響が出るのでは?」といった心理的な不安を抱える社員は多くいます。
特に年功序列や終身雇用文化が根強く残る伝統的な日本企業では「異動=裏切り」といった空気があることも。それでは、制度が形だけになってしまうのも無理はありません。
制度を整えるだけでなく「やめとけ」「気まずい」と思われないようにし、「社員が安心して活用できる」環境づくりが求められます。
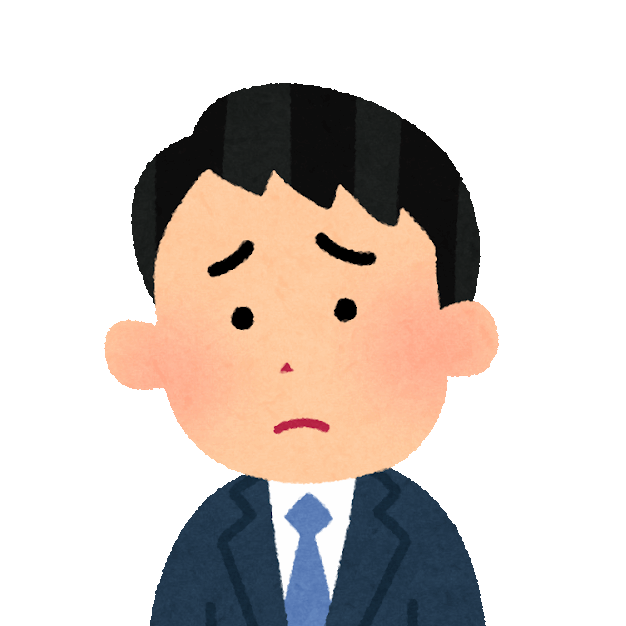
社内ポータルで公募情報を出しただけで終わってしまい、周知もフォローも不十分でした。仕組みはあっても使われなければ失敗です。
募集内容が曖昧で、魅力を感じにくい
仕事の面白さが伝わらなければ誰も応募はしません。
募集内容に明確な業務範囲や期待成果、キャリアに与える影響が書かれていないと、社員は「ただの雑用係が欲しいだけ」「リスクが高くメリットが無い」と感じてしまいます。
さらに「なぜそのポジションで社内公募を行っているのか」が説明されていないと、応募者は将来のビジョンを描けません。
社員が自分のスキルや志向に合うチャンスだと判断できるよう、魅力的な情報設計が求められます。

募集要項に必須スキル経験を書きすぎていませんか?失敗事例として、実際には5つのうち1つだけ満たしていればいいのに、全て満たさないといけないような求人票を書いていた企業がいます。
自分は受からないと決めつけている
「応募してもどうせ受かるはずがない」「結局、直属の上司の意見次第で決まるのでは?」といった不信感も、応募を妨げる大きな要因です。
特に過去に『出来レース』のような事例があると、社員の信頼は簡単には戻りません。例えば能力やスキルでは上回って人間が落ち、未熟だが上司に好かれている人間が採用されると不信感が一気に広がります。
応募から選考、配属までの流れが不透明だと、どれだけ制度を整備しても、実際の運用に疑念が生まれてしまいます。公正さと透明性が制度の信頼を支える土台となります。
社内公募制度の対象者が限定的すぎる
ごく限られた対象者のみの公募では、社員とマッチする確率が低下します。
キャリアを考えるきっかけは人それぞれ。異動意欲が高まっても、応募のタイミングが合わなければスルーされてしまう可能性があります。
定期的かつ継続的に制度を運用し、「常にチャンスがある」と思ってもらえるような仕組みにすることが大切です。

告知からエントリー時間が短くありませんか?社内転職は大きな決断です。一定の考える期間は必要です。
自分の軸が明確でない
大手企業の場合、そもそも自分の軸が明確でない人が多いです。
これはジョブ型採用をしていないデメリットで、会社都合での配属や異動に慣れすぎると自分の軸が曖昧になる傾向にあります。
これまで個人の意思を尊重せず、会社都合で配属部署を決めていたため「自分が本当にやりたいことは何だろうか?」と考える機会を奪っていたため、いざ面接になっても、受かる志望動機になっていません。

一度も転職を経験していない社員の場合、自分のキャリアプランを考える(表現する)機会が少ないです。そのためジョブポスティング制度を導入しても、社内異動(社内転職)で合格するために必要な志望内容やアピール能力が上手ではありません。
大手企業に見られる配属の課題と社内転職制度への影響
大手企業では、新卒一括採用やジョブローテーションといった慣習が根強く残っており、配属や異動における「個人の希望が通りにくい」という構造的な課題を抱えています。
例えば、「入社時の希望とは異なる部署に配属され、そのまま数年が経過」「希望異動を出しても通らない」「異動が突然でキャリアの見通しが立てづらい」といった声は、大企業の社員から頻繁に聞かれるものです。
こうした状況は、社員に“キャリアを自分で選べない”という無力感を与え、仕事へのエンゲージメント低下を招きます。さらに、キャリア観を重視する若手世代からは不信感が募り、離職意向にもつながることがあります。
このような背景において、社内公募制度や社内転職制度は、社員のキャリア自律を促す打ち手として大きな期待が寄せられています。しかし、制度自体が「人事側の調整用ツール」にとどまり、社員の声を汲み取るために機能していないケースも多く見られます。

大手企業が真に人材の流動性とキャリア支援を両立させるためには、従来の人事慣行そのものを問い直し、社員の納得感を伴う制度設計と運用を行う必要があります。
社員の適性やキャリア軸に沿った社内異動の最適化支援サービスへのお問い合わせはこちら
社内公募制度を機能させるための改善策
改善策1:制度の目的・意図をわかりやすく周知する
まずは、社内公募制度の背景と目的を全社に明確に伝えることが重要です。
なぜこの制度を始めたのか、どんな課題を解決したいのか、どのようなキャリア支援につながるのか。こうした情報を、社内報や全体会議、説明動画などを活用して丁寧に発信しましょう。
さらに「応募しても評価に影響しない」「上司の了承なしにエントリーできる」といった心理的安全性も、繰り返し伝える必要があります。社員が制度を信頼できる環境をつくることが、応募促進の第一歩です。

募集部署によるキャリア座談会(ワークショップ)の実施をおすすめしています。その際に各部署の責任者がバラバラの説明をするのではなく、ある程度の「話す内容」は決めてもらうことで、参加者が具体的に働くイメージをもってもらいやすくします。
改善策2:魅力ある募集要項を設計する
社員が「これなら挑戦してみたい」と思えるような募集要項の作成が必要不可欠です。
具体的には、次のような情報を丁寧に記載しましょう。
- 仕事内容の具体例
- 配属後に期待される成果
- スキルアップやキャリアへの影響
- どんな人物像が求められているか
- 募集部署の雰囲気やカルチャー
単に「人手が足りないから」ではなく、「あなたの経験がこのポジションでこう活きる」と伝えることが、応募の動機づけになります。

たとえば「海外出張あり」としか書くのではなく、どこの国なのか、年何回なのか、何日間の滞在なのか等をしっかり書かなくてはいけません。マイナス要素もしっかり書くことで、ミスマッチやモチベーション低下を減らせます。
改善策3:選考プロセスを明文化・可視化する
選考から配属までのフローを社内ポータルやFAQとして公開し、誰もが確認できるようにしましょう。応募から面談、合否連絡、異動決定までの流れを明文化することで、制度の公正性を示すことができます。
また、選考に関わる人事担当者や面談官には、公平性を保つためのトレーニングも必要です。過去の選考結果やフィードバック内容を一部社内で共有することで、「ちゃんと運用されている」信頼感も生まれます。

たとえば「海外出張あり」としか書くのではなく、どこの国なのか、年何回なのか、何日間の滞在なのか等をしっかり書かなくてはいけません。マイナス要素もしっかり書くことで、ミスマッチや異動後のモチベーション低下を減らせます。
改善策4:キャリア講座・面接対策を実施する
社員が社内公募に対して消極的になる背景には「どのようにアピールすれば良いかわからない」「経歴に自信がない」といったスキル面や意識面での不安が存在します。こうした不安を払拭するには、キャリア講座や面接対策の場を設けることが効果的です。
例えば、自己分析や強みの棚卸し、志望動機の伝え方などをレクチャーするキャリア講座を実施することで、社員は自分の経験や志向を見つめ直し、前向きに公募へ挑戦する土台が整います。
また、模擬面接やロールプレイを通じて、自信を持って自身を表現する練習の機会を提供すれば、選考過程での不安も軽減されます。単なる制度の提供だけでなく、応募までの“あと一歩”を支援する取り組みこそが、公募制度の活性化に直結します。

当社は社内異動制度の応募予定者に対してキャリアコーチを派遣し、1on1トレーニングを実施しています。応募理由の言語化や自己アピール作成のサポートをおこなっています。興味がある企業様はお問い合わせページからご連絡ください。
社内公募制度は適切な運用が命
社内公募制度は、社員のキャリア形成を支援し、企業全体の活性化にもつながる強力なツールです。ですが、形だけの制度では意味がありません。
応募がこない背景には、社員側の不安や不信感、情報不足といった“見えない壁”が存在しています。
制度を成功させるカギは、社員の信頼を獲得すること。そのためには、制度の趣旨を丁寧に伝え、応募者の不安を払拭し、選考の透明性を保ち続ける必要があります。
社内公募制度の再設計は、長期的には自律的なキャリア形成を促す企業文化の醸成につながります。今回の失敗事例や気をつけることを意識して、社員の声に耳を傾けながら、応募したくなる制度へと育てていきましょう。
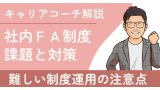
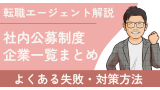
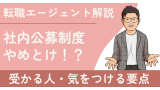
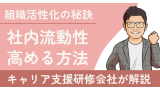
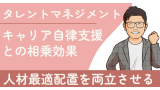
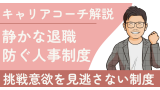
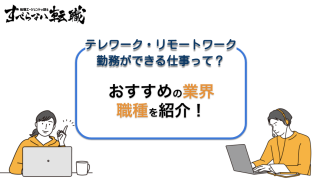
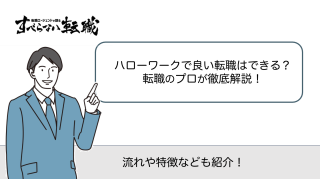
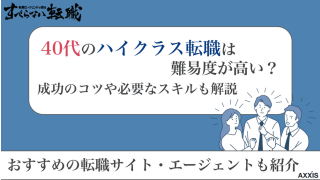
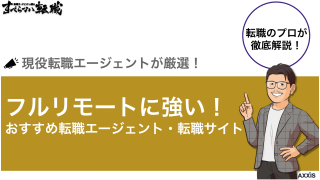
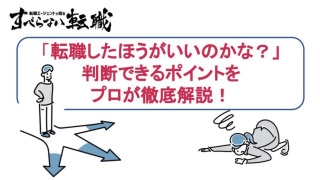
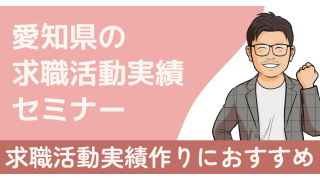
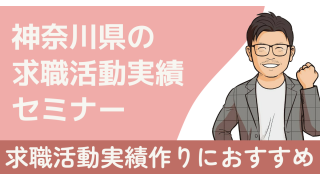
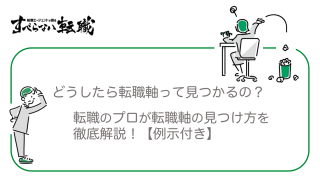
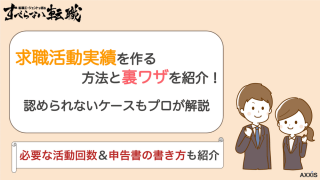
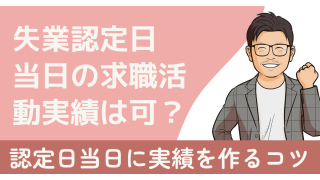







社内FA制度(フリーエージェント制度)を導入していますが、若手や中堅社員が応募してくれず「やりたいことができない」として退職が止まりません。気をつけることってありますか?