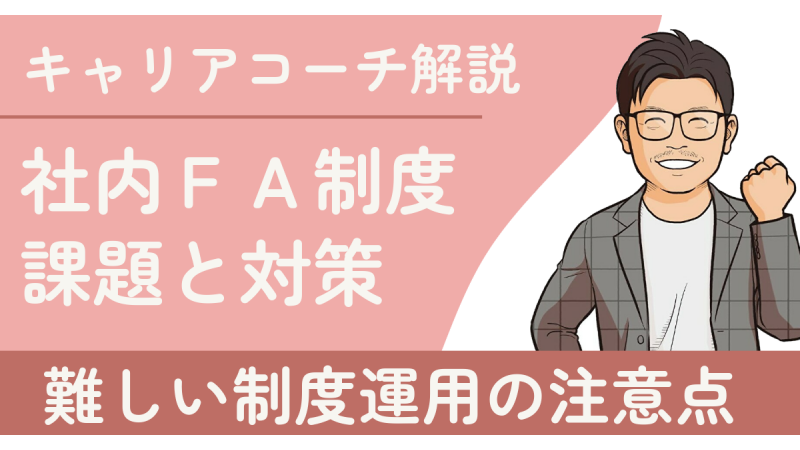
【社内FA制度】人事制度運用よくある課題と対策方法
「社内FA制度を導入したものの、思ったほど活用されていない」「制度はあるのに、手が挙がらない」そんな課題を感じていませんか?
社内FA制度(フリーエージェント制度)は、本来、社員の自発的なキャリア形成と社内の人材流動性を高める有効な仕組みです。しかし、制度設計や運用に課題があると、形骸化し、逆にモチベーション低下を招いてしまうことも。
本記事では、社内FA制度でよくある課題とその具体的な対策方法を人事視点で詳しく解説します。制度を「機能する制度」へと改善したいとお考えの人事・経営企画担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
すべらない転職が紹介するサービスの一部には広告を含んでおり、当サイトを経由してサービスへの申込みがあった場合には、各企業から支払いを受け取ることがあります。ただし、ユーザーの利益を第一に考え客観的な視点でサービスを評価しており、当サイト内のランキングや商品の評価に関して影響を及ぼすことはございません。
社内FA制度とは?基本の仕組みと目的
社内FA制度とは、企業内において社員が自ら希望する部署や職種への異動を申し出ることができる制度のことです。
「フリーエージェント制度」とも呼ばれ、社員が自身のキャリアビジョンに沿って自発的に異動先を選ぶことができる点が特徴です。
もともとはプロ野球の「FA(フリーエージェント)」制度に着想を得ており、組織に縛られるのではなく、個人が自分の意志で所属先を選ぶという考え方が背景にあります。
企業にとっては人材の最適配置と社員のエンゲージメント向上を図る手段として、また社員にとっては「やりたいことに挑戦できる」「転職しなくてもキャリアチェンジできる」といったメリットがある制度として、近年導入企業が増えてきています。
特に人的資本経営が注目される中で、キャリアの自律性を重視する企業文化を醸成する手段としても期待が高まっています。
ジョブポスティング制度との違い
社内FA制度とよく比較される制度に「ジョブポスティング制度」があります。
こちらは、部署側が人材募集を社内に公開し、それを見た社員が応募するという、いわば「部署発信型」の仕組みです。
一方で社内FA制度は、社員側が異動を希望する先を主体的に選ぶ「社員発信型」の制度である点が大きく異なります。
たとえばジョブポスティング制度では「この部署でこの業務が必要なので人を募集します」という明確なポジション情報がありますが、社内FA制度では「私はこの部署でこんなことに挑戦したい」という、社員のキャリア志向が出発点になります。
そのため、制度の運用にあたっては人事部門と異動先部門の柔軟な連携が求められ、社員の潜在的な能力や将来性を評価する力も重要になります。
社員の適性やキャリア軸に沿った社内異動の最適化支援サービスへのお問い合わせはこちら
制度導入の目的
社内FA制度の導入には、大きく3つの目的があります。
一つは社員のキャリア自律を促進することです。
企業内でのキャリア形成を会社主導ではなく、社員自身が選択できるようにすることで、モチベーションの向上や離職防止につながります。
二つ目は組織としての人材最適配置を実現することです。
特定の部署に人材が偏っていたり、成長意欲が高い人材が現業に留まっていたりする状態を解消することで、全社的な生産性向上を図ることができます。
三つ目は「人材を育てる組織」から「人材が育つ組織」への転換です。
社員が自らキャリアを切り拓き、挑戦できる環境を提供することは、結果として企業のイノベーション推進や組織文化の変革にもつながります。
社内FA制度は単なる人事施策の一つではなく、企業のあり方を変える可能性を持つ制度です。
社内FA制度よくある課題1:制度が形骸化している
社内FA制度は、導入した当初こそ注目されますが、運用が形だけに終わってしまうと、次第に社員の関心も薄れていきます。
「社内FA制度はあるけれど誰も使っていない」「実際に活用している人を見たことがない」そんな声が社内に広がると、制度は存在しているだけのものとなり、本来の意義が失われてしまいます。
特に多いのが「社内FA制度はあるものの、実際には年に数件程度の応募にとどまっている」「活用しているのは特定の部署や一部の社員に限られる」といったパターンです。
人事側は「自由に応募できる仕組みを整えた」と考えがちですが、社員にとっては「制度が機能していない」「誰も活用していないから使いにくい」と感じられ、利用がますます遠のいてしまいます。
活用されない背景
社内FA制度が形骸化する背景には、いくつかの共通した原因があります。
1つは、社員側の心理的ハードルです。
「制度を使うことが評価に響くのではないか」「上司にどう思われるか不安」「移った先でうまくやっていけるか分からない」といった不安要素が制度活用を妨げています。
制度そのものの設計よりも、社員が安心して使えるという文化づくりがなされていないことが大きな問題です。
また、部署間の人材獲得バランスの問題もあります。
異動先の部署が「どうしても欲しい人材像」を強く固定していたり、「うちでは受け入れが難しい」と消極的だったりすることで、せっかくの応募も断られてしまい、応募側のモチベーションが低下するという悪循環が起こることもあります。
制度が名ばかりで、実質的に通らないのであれば、社員は「最初から応募しない」という選択をしてしまいます。
対策:スモールスタートと成功体験の可視化
社内FA制度の形骸化を防ぐためには、まず小さな成功体験を積み上げることが大切です。
いきなり全社で導入するのではなく、意欲的な部署や、若手の多い部署などから試験導入し、実際に異動が行われた成功事例を社内でしっかり共有することが重要です。
「FA制度を使った社員が異動先で活躍している」「送り出した部署も前向きに受け止めている」といった実績が見えることで、他の社員の心理的ハードルを下げることができます。
また、人事主導で制度を動かす力を持つことも欠かせません。
たとえば、制度を定期的に社内報やイントラネットで紹介する、制度活用経験者のインタビュー記事を掲載するなど、制度が動いていることを社内に伝え続けることが重要です。

社内FA制度よくある課題2:上司の理解・協力が得られない
社内FA制度の運用で最も多く見られる障壁の一つが、直属の上司による「無言の引き止め」です。
制度上は社員が自由に異動希望を出せても、実際には「今のタイミングで異動したいと言い出すなんて空気が読めていない」「君に抜けられるとチームが回らない」といった雰囲気が漂い、表立って制度利用を止められなくても、精神的な圧力を感じさせるケースが多々あります。
このような状況では、社員は制度の存在を知っていても「上司の反応が怖くて使えない」という心理状態に陥ってしまいます。
特に、現場のリーダーがメンバーの異動を損失と捉える文化が根強く残っている職場では、FA制度は理想論にとどまり、実質的には封じられた制度になってしまうのです。
評価制度とのズレが引き起こす弊害
上司の引き止めが生まれる背景には、評価制度とのズレがあります。
多くの企業では、管理職の評価項目に「チームの成果」や「メンバーの安定稼働」が含まれており、優秀な部下が異動してしまうことは、結果的に自分の評価を下げるリスクにつながると捉えられてしまいます。
また「この人を異動させると後任がいない」「業務が停滞する」などの理由から、制度利用を見て見ぬふりをするケースもあります。
制度がある一方で、異動を希望した社員に「なぜこの時期なの?」「どうして今、うちから出ようとするの?」と疑問を投げかけてしまうようでは、制度はあっても意味がありません。
本来であれば、部下の成長やキャリア形成を後押しするのがマネジメントの役割です。しかし、評価設計がそれに伴っていない場合、「自分の損得」で判断せざるを得ない状況が、上司側にも生まれてしまうのです。
対策:上司評価と制度活用を連動させる
この課題を解決するには、まず管理職への制度意義の徹底的な浸透が必要です。
単なる制度説明だけではなく、「なぜこの制度がいま必要なのか」「制度を活用することで、組織としてどのような価値が生まれるのか」を、管理職研修や1on1を通じてしっかり伝えることが大切です。
さらに重要なのが、制度活用を上司自身の評価に正しく反映させることです。
たとえば「部下の育成・送り出し実績」や「異動を通じた人材の活躍支援」が管理職の評価項目として明文化されていれば、上司も前向きに制度活用を促す動機が生まれます。
FA制度を損と捉えるのではなく、部下のキャリア支援ができた成果として評価される構造に切り替えていく必要があります。
また、代替要員の育成計画や、他部門との人材融通の仕組みも整えておくことで「人が抜けると困る」という現場の本音に対する実務的な不安も軽減できます。

制度を円滑に運用するには、理念だけでなく、現場に即した実務設計の視点も不可欠です。
社内FA制度よくある課題3:社員が制度を信用していない
制度が社内に整備されていても、社員が「本当に使っても大丈夫なのか?」と疑念を抱いているケースは少なくありません。「使うと損をする」という誤解
特にJTC(伝統的な日本企業)に多い傾向として、制度を建前と受け止める文化があります。
つまり、形式上は「自由に使ってよい」と言われても「実際に使ったら上司に睨まれるのでは?」「社内で評価が下がるのではないか」といった不安が先に立ってしまい、制度が本格的に活用されることはないのです。
このような不信感は、過去にFA制度を利用した社員が異動後に評価を落としたり、職場に居づらくなって辞めてしまったといった悪い前例が原因になっている場合もあります。
一度でもそうしたケースが起きてしまうと「制度を使うとキャリアにマイナスになる」という誤解が社内に広まり、制度の利用にブレーキがかかってしまいます。
特に若手社員ほど、人事からどう見られるかを気にする傾向があり、明確なキャリア設計がないまま異動を希望することに不安を感じています。

「異動しても今よりよくなるとは限らない」「今の部署で評価されているのに、ゼロからやり直すのは怖い」といった心理的ハードルが、制度活用の最大の壁になっているのです。
情報の非公開が信頼を妨げる
もう一つ大きな障害になるのが、制度に関する情報が社員に対して十分に共有されていないことです。
「どの部署がいつ異動を受け入れているのか」「異動後の仕事内容はどうなるのか」といった実務的な情報が不透明だと、社員は具体的な行動を起こしづらくなります。
特に、異動先の部署について詳しい情報がなく「実際どんな人が働いているのか」「雰囲気は合いそうか」「スキルは通用するのか」といったリアルな視点が持てないと、応募への心理的障壁はより一層高くなります。
応募=リスク、というイメージがついてしまうと、制度は表向きに存在していても誰も使わない状態に陥ってしまいます。

「応募して落ちたら恥ずかしい」「落ちたことが他部署にバレるのではないか」といった不安を抱く社員もいます。情報の取り扱いやフィードバック体制が不透明な場合、こうした懸念が制度利用のブレーキになります。
対策:ルール明文化と情報開示の徹底
まず取り組むべきは「制度の信用性を取り戻す」ことです。
そのためには、FA制度に関するガイドラインやFAQを明文化し、「制度を使っても評価に影響はない」「不合格でも社内で不利益を受けない」といったルールを社員がいつでも確認できる状態にしておくことが重要です。
また、制度の透明性を高めることも大きなカギとなります。
どのタイミングで制度が使えるのか、募集部署はどこか、選考の流れや基準はどうなっているかなど、実務的な情報を社内ポータルなどで定期的に公開することで、社員の安心感は大きく変わります。
さらに、異動先の部署と気軽に話ができる「事前見学」「オープン社内面談」などの仕組みを設けると、応募前に雰囲気や仕事内容を把握でき、応募への不安が軽減されます。
実際に制度を活用した社員による体験談の共有や、匿名で質問できる相談窓口を設置するのも有効です。

FA制度を信頼して使ってもらうためには、制度設計以上に「運用の透明性」と「安心できる土壌づくり」が欠かせません。社員に対して丁寧に向き合い、信頼を一つずつ積み重ねていく姿勢が必要です。
社内FA制度を機能させるための運用の工夫
評価制度との整合性を取る
多くの企業で見落とされがちなのが「制度と評価の連動設計」です。
いくらFA制度を整備しても、それを活用することで社員の評価が下がる、あるいは管理職の評価に不利になるのであれば、制度は確実に形骸化します。制度は理念では動きません。人が動くのは、「動いた方が得である」「動かないと損になる」と思える仕組みがある時です。
社員にとっては「異動を希望しても評価に影響しない」「むしろキャリア形成を前向きに評価してくれる」と感じられる設計が必要です。
また、管理職にとっても「部下を送り出すと自分の評価が下がる」という不合理がないよう、評価項目に「キャリア支援」や「部下の成長実績」を明示的に組み込むことで、制度活用に対するインセンティブを整える必要があります。

FA制度と評価制度を矛盾なく設計し直すことは、制度を実際に機能させるための土台になります。制度を浸透させるためには、理念と制度設計と運用のすべてが整合的である必要があるのです。
キャリア面談で志向を把握する
社内FA制度を機能させるために重要なのがキャリア面談の仕組み化です。
制度の内容以前に「社員が自分のキャリアをどう考えているか」を把握する仕組みが必要ですが、そのために効果的なのが、定期的なキャリア面談です。
年に1回、あるいは半期に1度のペースで、上司や人事担当者と社員が「これからどんな仕事がしたいのか」「どんな能力を伸ばしたいのか」といったキャリア志向について率直に話し合う機会を設けることで、社員自身もキャリアを見つめ直すきっかけになります。
この面談の中で「社内FA制度という選択肢がある」という情報提供がなされるだけでも、社員の視野は大きく広がります。また、異動希望があってもなかなか言い出せない社員にとって、キャリア面談が制度活用への第一歩になることもあります。

さらに、面談結果をもとに人事が社内の異動希望をデータ化・可視化しておけば、部署側からのアプローチも実現可能になり、より柔軟な人材流動が生まれやすくなります。
異動後のサポートで制度活用を後押し
制度を活用して異動したあと、スムーズに新しい部署に馴染めないと「FA制度を使って後悔した」という感情が生まれてしまいます。
制度活用を促進するうえでは「異動してからのケア」こそが最も重要だといっても過言ではありません。
異動先での受け入れ態勢を整えるだけでなく、オンボーディング支援やメンター制度、OJTの体制を明確にし、「異動先でも安心して働ける」という体験を提供することが重要です。
特に、異動後3か月・6か月などの節目でフォローアップ面談を設け、「困っていることはないか」「期待通りのキャリアにつながっているか」といったヒアリングを行うことで、早期離職の防止にもつながります。
また、異動先の部署にもFA制度の意義やメリットを伝えることが不可欠です。異動者が「外から来たよそ者」として扱われてしまえば、せっかくの制度も逆効果になってしまいます。

人材を迎え入れる側にも、会社全体で育成するという視点を持ってもらうための社内教育が必要です。
成功企業の事例に学ぶ社内FA制度が活きる組織の特徴
制度があるにもかかわらずうまく活用されていない企業がある一方で、社内FA制度を定着・活性化させている企業も存在します。
彼らに共通しているのは「制度の存在」だけでなく「制度が活きる土壌」を丁寧に整えているという点です。
ある大手IT企業では、制度導入と同時に、異動希望者全員にキャリア開発面談の機会を複数回提供し、そこで得た志向性のデータをもとに、FA制度のタイミングでマッチング精度を高めています。
社員も「自分のキャリアは自分でつくる」という意識を持ち、制度を前向きに活用する文化が根付いています。

当社もキャリア開発面談の外部キャリアコーチとしてサポートさせていただきました。
また、あるメーカーでは、若手社員のFA応募率が非常に高いのが特徴です。
理由は、入社2年目からFAの権利を持てるだけでなく、異動先で失敗しても責められない「挑戦歓迎」の風土があるからです。異動後のメンタリング制度も充実しており、早期離職を防ぐ効果も出ています。
成功している企業に共通するのは、下記を丁寧に作り上げている点です。
- 社員のキャリア自律を支援する文化
- 制度を「運用」する力(フォロー体制)
- 評価制度と矛盾しない設計

当社は社内公募制度活性化サービスとして、キャリアコーチを派遣し、1on1トレーニングを実施しています。社内異動制度の応募予定者に対して、応募理由の言語化や自己アピール作成のサポートをおこなっており、好評を得ています。興味がある企業様はお問い合わせページからご連絡ください。
社内FA制度に外部キャリアアドバイザーを入れるメリット
社員が本音でキャリア相談しやすくなる
社内の人事や上司にキャリアの悩みを相談する場合「ネガティブに評価されるかもしれない」「転職を疑われたら困る」といった心理的なブロックが生まれやすいのが現実です。
その点、外部のキャリアアドバイザーであれば、評価と無関係な第三者として、中立的な立場で相談に乗ることができます。

特に「異動を希望しているが、社内で言い出せない」「現職に満足していないが、上司には言えない」というケースに効果的です。社内に相談できるキャリアの駆け込み寺があることで、社員の孤立感も軽減されます。
キャリア設計に対する社員の視野が広がる
多くの社員は、現在所属している部署や過去の経験に引っ張られてキャリアを狭く捉えてしまいがちです。
外部アドバイザーは社内外の職種や働き方に通じているため、視野を広げたキャリア選択のアドバイスが可能です。

そもそもキャリアの選択肢を知らない社員が、実は別部署で力を発揮できることに気づくケースもあります。他社事例や最新の人材市場動向を踏まえたアドバイスが受けられる点も大きな強みです。
制度への信頼性が高まり、利用が促進される
「制度はあっても、結局使いにくいのでは…」という疑念を持つ社員は少なくありません。
外部の専門家が制度運用の一端を担うことで、客観性と信頼性が加わり、制度の本気度が伝わります。

「評価に関わる上司や人事に相談するのが怖い」という心理的障壁を壊せるのは、外部だからこその強みです。第三者の存在が「制度が使われる前提でつくられている」という文化を醸成します。
人事部門の負担軽減と中立性の担保
キャリア面談をすべて人事で担うのは工数的にも心理的にも限界があります。
外部キャリアアドバイザーを配置することで、社員への面談・フォローを分担でき、運用負荷を減らせます。また「評価者=相談相手」という不自然な関係も避けられます。

社内相談では言えない本音も、外部相手であれば自然と話せるものです。人事側も「聞き役」に徹する余裕が生まれ、戦略的な配置や制度改善に注力できます。
制度活性化・運用改善のフィードバックが得られる
社員との対話を通じて、制度の活用実態や改善ポイントを定期的にフィードバックしてもらえるのも大きなメリットです。
「制度の説明が不足している」「応募に対する不安が強い」といった生の声をもとに、運用を柔軟に改善していけます。

制度利用を阻む『見えない壁』を外部視点で特定できるのは、人事にとって非常に貴重です。定量化しにくい『感情面のボトルネック』を浮き彫りにし、制度改善に活かせます。
社員の適性やキャリア軸に沿った社内異動の最適化支援サービスへのお問い合わせはこちら
社内FA制度導入前にチェックすべき運用フロー
社内FA制度導入を失敗させないためには、運用前の設計段階が非常に重要です。以下は、制度開始前に確認しておくべき運用フローの一覧(チェックリスト一覧)です。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的とコンセプトの明確化 | なぜ導入するのか?キャリア支援・人材流動・育成等 |
| 制度設計 | 応募条件、実施頻度、選考方法、評価への影響などを明文化 |
| 管理職向け説明 | 制度の目的、メリット、登壇者向け講習会、マネジメント上の意義を伝えているか |
| 評価制度との整合性 | 評価項目との関係性を整理し、「不利益がない」ことを保証 |
| 社内ポータル整備 | 募集部署情報、応募手続き、QA、連絡先などをオンライン掲載 |
| 応募前から面接の運用 | キャリア座談会、ワークショップ、1on1の実施 |
| 応募〜異動までのスケジュール | 年間計画を立て、異動時期や選考タイミングを明確にする |
| 異動後のフォロー体制 | メンター制度やオンボーディング支援の準備 |
| 利用実績の可視化・報告 | 年次で活用状況を振り返り、社内共有 |
まとめ:社内FA制度は「運用」で決まる
社内FA制度は、うまく運用すれば「社員のキャリア形成支援」と「組織の最適配置」という2つの目的を同時に達成できる強力な人事制度です。
しかし、制度の形だけを整えても、実際にはうまく機能しないことが多く、「形骸化」「上司の反発」「社員の不信感」といった課題に直面します。
だからこそ重要なのは「小さく始めて、大きく育てる」スタンスです。
いきなり全社導入するのではなく、特定部署や特定階層で試験的に導入し、成功体験を積み重ねながら、運用ノウハウを社内に広げていく。この地道なプロセスこそが、制度の定着と活用を実現する鍵になります。
そして何より、制度の「使いやすさ」は、制度設計だけでなく、運用者(人事・経営層・現場マネージャー)の理解と実行力によって大きく左右されます。
社員が「この会社ならキャリアの選択肢がある」「本気で背中を押してくれる」と感じられるような信頼関係を築くことが、社内FA制度の最大の成功要因といえるでしょう。
今こそ、制度を掲げるだけでなく、機能させる運用へ。その一歩を、ぜひ貴社から踏み出してみてください。
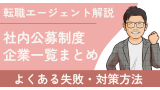
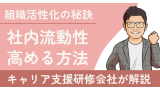
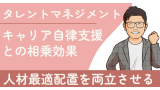
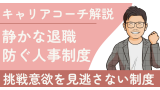
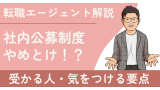
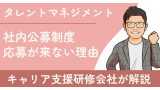
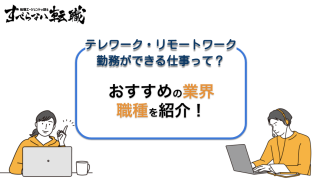
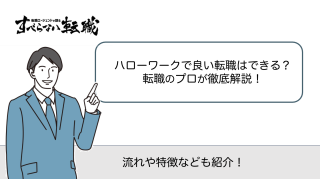
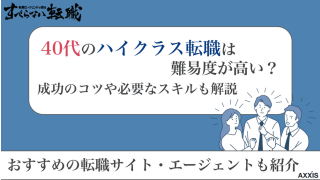
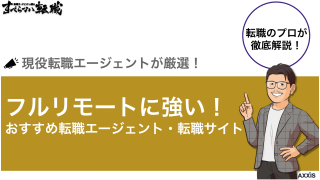
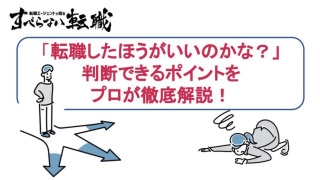
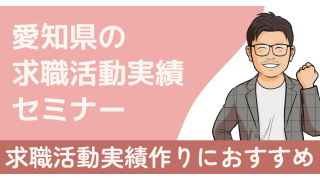
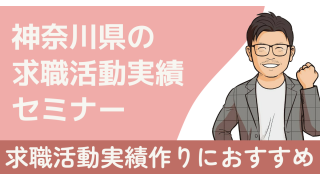
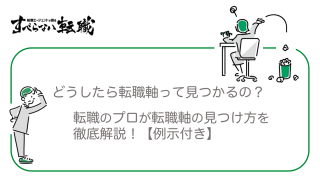
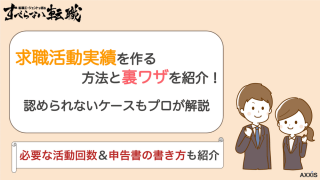
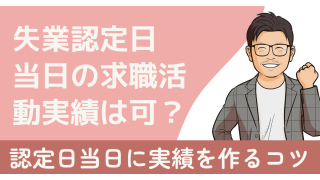







「使ってもいい制度」「制度を使っても大丈夫」という空気づくりを継続的に行うことが、形骸化を防ぎ、制度の活性化につながっていきます。