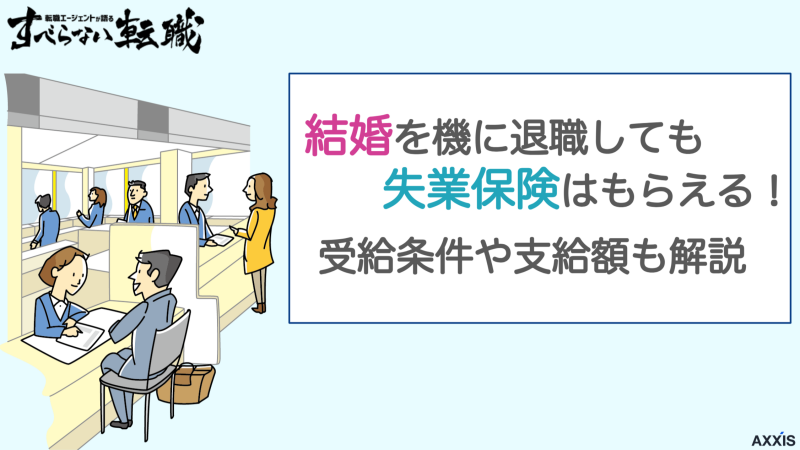
結婚を機に退職しても失業保険はもらえる!受給条件や支給額も解説
- リクルートの経験を活かしたポイントを解説!
- 結婚しても失業保険の申請手続きはできる
- 扶養に入りながら失業保険をもらうことは可能
- 求職活動実績を作るならリクルートエージェントのオンラインセミナーがおすすめ
結婚を理由に退職した場合、失業保険を受給できる人とできない人の特徴をはじめ、支給額や計算方法、申請する際の注意点などをわかりやすく解説します。
さらに配偶者の扶養に入るのとどちらが得になるのかも合わせてお伝えします。
すべらない転職が紹介するサービスの一部には広告を含んでおり、当サイトを経由してサービスへの申込みがあった場合には、各企業から支払いを受け取ることがあります。ただし、ユーザーの利益を第一に考え客観的な視点でサービスを評価しており、当サイト内のランキングや商品の評価に関して影響を及ぼすことはございません。
オンラインセミナーで手軽に求職活動実績を作る方法
ハローワークへ行かずに手軽に求職活動実績を作るならリクルートエージェントのオンラインセミナーがおすすめです。
自宅にいながら必要な実績をすべて作れるので、わざわざハローワークまで行く必要がありません。空いた時間に実績を作りたい人はぜひ活用してみてくださいね。
結婚をしても失業保険の受け取りは可能
結婚しても失業保険を受給することは可能です。ただ、失業保険を受給するためには、求職活動をおこなう意思と能力があることが大前提となるので注意が必要です。
というのも、失業保険は働く意思と能力があり、積極的に就職活動しているけれど仕事に就けない状態である人を支援する制度だからです。
そのため、結婚を機に退職してそのまま専業主婦として家庭に専念して、再就職する意思がない場合は失業保険を受給することができません。
結婚しても失業保険が受け取れる人
結婚しても失業保険を受け取ることは可能だと伝えましたが、具体的にどんな人なら受け取れるのか気になるところだと思います。
失業保険は働く意思のある人が受け取れるので「退職後も就職活動して働く意思のある人」などが受給できるようになっています。
他にもどのような人だと失業保険を受け取れるのか、さらに紹介していきたいと思います。
失業保険が受け取れる人
退職後もすぐに就職活動して働く人
結婚しても失業保険を受給できるのは、退職後も就職活動して働く意思がある人ですね。結婚を機に退職した場合は、自己都合退職として扱われるケースが多いです。
離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あり、働く意思と能力がある人が対象になります。
他にも積極的に求職活動しているにも関わらず、仕事に就けない状態であるとハローワークに認定されれば、失業保険を受け取ることができますよ。
結婚に伴って引越しが必要になる人
結婚に伴って引越し(住所変更)することになった人も、失業保険を受給することができます。結婚に伴い引越しをする場合は「特定理由離職者」として扱われる可能性があります。
ただ、受給要件として「退職と引越し(入籍)の時期が近いこと」を満たす必要があるので注意しましょう。
ハローワークによって少し変わってくる可能性があるものの、離職から住所移転までおおむね1ヶ月以内などが目安になるので、事前に確認しておくのがベストですね。

結婚による転居で通勤困難になる人
結婚による転居で通勤困難または通勤が不可能になる人も、失業保険を受け取ることができますよ。例えば、通勤するのに片道4時間以上掛かってしまうというケースが挙げられますね。
この場合も「特定理由離職者」として認められる可能性があるため、失業保険の申請手続きがおこなうことが可能です。
この場合も結婚を証明する戸籍謄本、引っ越しを証明する住民票、そして通勤経路の変更を証明する書類などが必要になるので、準備しておきましょう。
結婚しても失業保険が受け取れない人
結婚して退職したのち、失業保険を受給できない人もいます。
というのも、失業保険は退職後に働く意思のある人が受け取れるものだからです。そのため、退職後に再就職して働く意思がない人などは受け取ることができません。
具体的にどのような人が失業保険を受給できないのか、さらに紹介していきたいと思います。
失業保険が受け取れない人
退職後に専業主婦として過ごす人
結婚しても失業保険を受け取れないのは、退職後に専業主婦として家庭に専念して再就職する意思がない人ですね。
失業保険を受け取ることができないのは、求職活動をおこなわないことや、いつでも就職できる状態ではないと判断される可能性があるためです。
とくに家族の介護に専念する、又は育児に専念するといった状況の場合は、すぐに就職できる状態ではないとハローワークに判断されることがあります。
妊娠や出産を理由に退職する人
結婚をして妊娠や出産を機に退職する人も、失業保険を受給することができません。なぜなら、ハローワークから「働く能力がない」と判断されるからです。
妊娠中や出産後は体調面などから、すぐ働くことが難しいとされるのが一般的です。そのため、妊娠中や出産直後などは原則として要件を満たせないとみなされて、失業保険をすぐに受け取ることができません。
ただし、妊娠や出産に育児と両立させながら就職活動・就職する予定の人は「受給期間延長制度」の申請手続きをすれば、最長3年間の失業保険の延長ができますよ。

本来の受給期間1年と合わせて、最長4年にわたって受給資格を保持することが可能です。
その際には母子手帳や離職票の提出が必要になるので、事前にハローワークに問い合わせをして準備することをおすすめします。
アルバイトやパートで週20時間以上働く人
結婚を機に退職して、その後アルバイトやパートで働き始めて週20時間以上働く人も、失業保険を受給するのが難しいと言えます。というのも、この場合「失業状態ではない」とハローワークが判断するからです。
失業保険は働く意思と能力があって積極的に求職活動をおこない、それでも仕事に就けない状態の人に支給されるものです。
そのため、週20時間以上働いてしまうと、その人が雇用保険の加入条件を満たす労働者とみなされてしまいます。

雇用保険の被保険者になるとハローワーク側は「就職した人」と判断するため、失業状態にはならず、失業保険の支給が停止されてしまうので注意しましょう。
結婚後に受給できる失業保険の金額
結婚を理由に退職して失業保険を受給できる人やできない人について解説してきましたが、具体的にどのくらいの金額が受給できるのか気になるところですよね。
結婚後に受給できる失業保険の金額は結婚の有無に関わらず、離職時の給与(賃金)と離職時の年齢によって決定されます。とはいえ、結婚を理由にして退職した場合は、給付が始まるまでの期間が変わる可能性があります。
ちなみに、基本手当日額には上限額と下限額が決められており、毎年8月1日に見直されます。
| 離職時の年齢 | 基本手当日額の下限額 | 基本手当日額の上限額 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 2,295円 | 7,065円 |
| 30〜44歳 | 2,295円 | 7,845円 |
| 45〜59歳 | 2,295円 | 8,635円 |
| 60〜64歳 | 2,295円 | 7,420円 |
参考:厚生労働省
失業保険で1日に受け取れる金額のことを「基本手当日額」といいます。基本手当日額の計算方法は「賃金日額×給付率=基本手当日額」となっています。
つまり、賃金が低いほど給付率が高くなる傾向にあるということになりますね。
賃金日額と給付率について
- 賃金日額:離職日の直前6ヶ月間に支払われた賃金(通勤手当・残業代を含む・賞与は除く)の合計を180で割った金額
- 給付率:賃金日額や離職時の年齢によって異なり、45%〜80%の範囲で設定される
年齢別の所定給付日数
年齢別の基本手当日額を知った次に気になるのは、所定給付日数ですよね。所定給付日数とは、雇用保険の基本手当を受給する際、その上限日数を定めたものです。
所定給付日数は、離職理由と雇用保険の被保険者だった期間、そして離職時の年齢によって決定されます。
自己都合退職の場合、会社都合退職の場合で所定給付日数がどのように違ってくるのか、次で詳しく解説したいと思います。
退職理由別の所定給付日数
自己都合退職の場合(一般受給資格者)
自己都合退職の場合、失業保険の所定給付日数は雇用保険の被保険者であった期間によって決定されることになっています。
会社都合退職や特定理由離職者とは違い、年齢によって給付日数が細かく分かれることはありません。
厚生労働省のデータを元に、自己都合退職の場合の所定給付日数を表にまとめてみたので、ぜひ参考にしてくださいね。
| 雇用保険の加入期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日間 |
| 10年以上20年未満 | 120日間 |
| 20年以上 | 150日間 |
参考:厚生労働省
被保険者期間は離職日の直前2年間で雇用保険に加入していた期間の合計となっています。もし、複数の会社に勤務していた場合でも、条件を満たしていれば期間を通算することが可能です。
自己都合退職の場合は最低でも90日の所定給付日数があるものの、雇用保険の加入期間が1年未満の場合は受給資格がないので、注意してくださいね。
会社都合退職の場合(特定受給資格者・特定理由離職者)
次に会社都合や特定受給資格者、特定理由離職者の場合ですが、自己都合退職とは失業保険の所定給付日数がまた変わってきます。
厚生労働省のデータを参考に会社都合(特定受給資格者・特定理由離職者)の所定給付日数を表にまとめたので、こちらも合わせて参考にしてみてください。
| 離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
参考:厚生労働省
結婚に伴って引越しをする人や、妊娠・出産を理由に退職した人は「特定理由離職者」として扱われるため、会社都合退職と同じように手厚い給付日数が適用されます。
また、離職時の年齢によっても所定給付日数が変動するので、事前にしっかりと確認しておくのが望ましいですね。
結婚して失業保険を受給する際の注意点
結婚して失業保険を受給するとなった際には、いくつか注意しておきたいことがあります。とくに気をつけたいのは「退職後に働く意欲がない人は受給できない」ことが挙げられますね。
もちろん、結婚を機に退職したのち、再び就職活動・就職する予定がある人は失業保険の申請手続きをすることが可能ですよ。
他にも結婚をしたのちに失業保険を受け取れないケースがあるので、次でそれぞれ詳しく紹介していきますね。
結婚して失業保険を受給する際の注意点
退職後に働く意欲がない場合は受給できない
結婚して退職した後に働く意欲がない人は、失業保険を受け取ることができません。
具体的には、退職後にそのまま専業主婦として過ごす人、家族の介護に専念する人、退職後に求職活動をしない人が該当しますね。
というのも、何度もお伝えしている通り、失業保険は求職者が安定した生活を送りながら、少しでも早く再就職するための支援だからです。
待機期間中の就労はNG
失業保険の手続きをおこなうと7日間の待機期間がありますが、原則としてこの期間に就労することは認められていません。
なぜなら、待機期間はハローワークで求職の申し込みと離職票の提出を済ませて、本当に失業状態であるのか確認するための期間だからです。
そのため、7日間の待機期間は基本手当が支給されませんし、完全に仕事をしていない失業状態にあることが求められます。

もし、待機期間中に就労してしまうと待機期間が延長されたり、不正受給とみなされたりするリスクが生じるため、注意が必要です。
1日の労働時間を4時間以内にする
結婚して退職した後に、アルバイトやパートをしながら失業保険を受け取りたい場合は、1日の労働時間を4時間以内に調整する必要があります。
厳密なルールがあるわけではありませんが、1日の労働時間が4時間以上、未満によって失業保険の支給のされ方が変わってきます。
その中でももっとも重要な要件は「週の所定労働時間が20時間未満であること」「31日以上継続して雇用される見込みがないこと」の2点ですね。このルールを守らないと就職した、つまり失業状態ではないと判断されて、失業保険の支給が停止されてしまいます。

ちなみに、1日の労働時間が4時間以上の場合、その日は「就労日」とみなされ、働いた日の失業保険は支給されずに、その日の分が後日に繰り越されます。
支給される基本手当の総額が減ることはありませんが、失業保険を受給できる期間が伸びます。
一方、1日の労働時間が4時間未満の場合、その日は「内職・手伝い」とみなされ、その日の失業保険は減額される可能性があります。
どの程度減額されるのかについては、働いた日の収入額と本人の基本手当日額、賃金日額によって決まります。
求職活動実績を2回以上作る必要がある
結婚して退職したのち、求職活動実績を2回以上作らないと失業保険の手続き・申請ができないため注意が必要です。失業認定期間とは、前回の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの期間を指します。
この期間中に求職活動を2回以上おこなわなければなりません。求職活動実績として認められるのは以下の通りとなっています。
求職活動実績として認められるもの
- ハローワークでの職業相談・職業紹介
- ハローワークが開催する職業訓練の受講・説明会の参加
- 許可・届出のある民間職業紹介事業者への求職申し込み・職業相談・職業紹介
- 公的機関がおこなう職相談・セミナーの受講
- 求人への応募
- 再就職に資する各種国家試験・検定等の受験(原則1回のみ)
上記の中でも簡単に求職活動実績を作れるのは、ハローワークへの職業相談ですね。
また、許可・届出のある民間職業紹介事業者に該当する転職エージェントで就職活動をおこなったり、オンラインセミナーを受講したりするのもアリです。
もちろん、転職相談ができる転職フェアへの参加も求職活動実績として認められるからおすすめですよ。

とくにリクルートエージェント・dodaが提供しているオンラインセミナーは、自宅でセミナーを受講するだけで実績が作れるため、すぐに実績を作りたい人におすすめです。
転職エージェントは無料で登録・利用できるので、ぜひうまく活用して求職活動実績を作ってみてくださいね。
求職活動実績を作るのにおすすめの転職サイト・エージェント
-
doda
顧客満足度トップクラス!転職に役立つセミナー多数 -
リクルートエージェント
業界No1!専門性を高められるセミナーもあり
オンラインセミナーについては、こちらの記事で詳しく解説しているので、気になる人は合わせてご覧ください!
結婚後に配偶者の扶養に入る際の注意点
結婚後に失業保険の手続きをせずに、配偶者の扶養に入りたいと考えている人も多くいると思います。
配偶者の扶養に入るとなったとき、どのような注意点があるのか事前に把握しておきたいところですよね。
もっとも気をつけたいのは、年間収入見込みが130万円以上だと扶養に入れないことです。この他にも注意したい点があるので、順番に解説していきたいと思います。
結婚後に配偶者の扶養に入る際の注意点
年間収入見込みが130万円以上だと入れない
結婚したのち、配偶者の扶養に入る際には年間収入見込みを130万円以内に抑える必要があります。そうしなければ、原則として扶養から外れることになってしまうからです。
年間収入の見込みは将来にわたって、1年間の収入が130万円を超えるかどうかで判断されます。年間収入には通勤手当なども含まれており、事業収入や不動産収入、年金収入、そして失業保険の給付額も含まれます。
ちなみに130万円を超えると配偶者の社会保険の扶養から外れて、勤務先の社会保険に加入、もしくは国民保険と国民年金に加入のどちらかで保険料を支払う義務が生じます。
パートで働く場合は年収160万円未満に調整する
結婚して退職した後にパートとして働く場合は、年収160万円未満に調整しないと配偶者の扶養に入れません。
とはいえ、配偶者の扶養には「税法上の扶養」「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれで年収の壁が異なるからこそ、混同しないように注意する必要があります。
税法上の扶養(所得税・住民税)
これは配偶者が税金を計算する際に受けられる控除に影響する年収の目安。2025年1月1日以降の所得から、本人の年収が160万円以下であれば、配偶者は「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」の満額を受け取ることができる。
そのため、配偶者の税金が安くなるメリットを最大限に受けたいなら、パートの年収を160万円未満に調整するのが良い。
本人の年収が160万円を超えても201.6万円以下であれば、配偶者特別控除が段階的に減額されながらも適用される。
ただし、201.6万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除がゼロになり、配偶者の税金が安くなるメリットがなくなる。
社会保険上の扶養
これは本人が配偶者の健康保険と年金の扶養に入れるかどうかに影響する年収の目安。つまり、自分で社会保険料を支払う必要があるかどうか。税法上の扶養とは違って、こっちは2025年以降も基本的には変わっていない。
130万円の壁:本人の年間収入見込みが130万円以上になると、配偶者の社会保険の扶養から外れて、自分自身で国民健康保険や国民年金・勤務先の社会保険といった社会保険に加入して、保険料を支払う義務が生じる。
106万円の壁:130万円の壁とはべつに、パート先の働き方によっては年収106万円を超えると、強制的に勤務先の社会保険への加入が義務付けられる場合がある。
「週の所定労働時間が20時間以上」「月額の賃金が8.8万円以上」「2ヶ月を超える雇用の見込みがある」「学生ではない」「勤務先の従業員数が51人以上」といった5つの条件をすべて満たす場合に適用される。
このことから、年収160万円以上稼いでしまうと配偶者の扶養から外れてしまうので、扶養に入りながらパートで働きたい場合は、年収106万円未満もしくは130万円未満に抑えるのがベストだと言えるでしょう。
結婚して失業保険を得る際によくある質問
ここでは、結婚して失業保険を受給する際によくある質問をいくつかピックアップして、それぞれ回答していきます。
「特定理由離職者」に該当するためには退職日以降の入籍、引越しじゃないとダメ?
結論、引越しや入籍のタイミングについては、退職日以降である必要は必ずしもありません。
退職日前に結婚して入籍していても、その後結婚に伴って引越すことになり、それ露理由に通勤困難になったのであれば、特定理由離職者として認められる可能性がありますよ。
ただ、入籍してから退職や引越すまでに期間が空き過ぎてしまうと、特定理由離職者として扱われない可能性があるため、注意が必要になります。
不安な場合は、引越し先のハローワークに問い合わせをして確認しておくのがベストです。
失業保険をもらうのと配偶者の扶養に入るのは、どちらが得?
失業保険をもらうのと配偶者の扶養に入るのと、どちらが得なのかについては、正直自分自身の基本手当日額と再就職までの期間、そして世帯全体の経済状況によって変わってきます。
大事なポイントは「税法上の扶養」「社会保険上の扶養」を分けて考えることです。
例えば、自分の失業保険の基本手当日額が約3,612円未満の場合は、失業保険を受給しながら配偶者の社会保険の扶養に入るのが得です。
一方、失業保険の基本手当日額が約3,612円以上になると、失業保険を受給する期間は社会保険の扶養から外れて、自分で社会保険料を支払う必要が出てきます。
多くの場合は失業保険の受給を優先するほうが手元に残る金額が大きくなりますし、失業保険の給付額は非課税になるのでおすすめですよ。
失業保険はすぐにもらえる?
失業保険はすぐにもらえるものではありません。手続きを終えて実際に振り込まれるまでには、早くても1ヶ月かかるケースが多く、自己都合退職の場合はさらに時間がかかる傾向が見られます。
まず申請を済ませると7日間の待機期間があり、終了後には離職理由によってさらに給付制限期間が設けられることになります。
自己都合退職の場合は原則1ヶ月間の給付制限期間が設けられ、その後ハローワークで初回手続きをおこない、約3〜4週間後に雇用保険受給者初回説明会に参加することになりますね。
実際の入金は、失業認定日から約1週間程度となっています。
失業保険をもらうなら入籍のタイミングはどうしたら良い?
「特定理由離職者」の認定を受けたい場合、入籍するタイミングは退職日よりも前で問題ありませんよ。
とはいえ、入籍から退職や転居まであまりにも長い期間を空けてしまうと、結婚が退職する直接の理由であるという因果関係が薄くなってしまうので、認定が受けられない可能性があります。
そのため、できるだけ入籍してから退職、そして引越しと短期間に集中しているほうが、特定理由離職者として認定されやすくなるのでおすすめです。
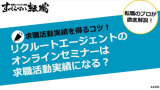

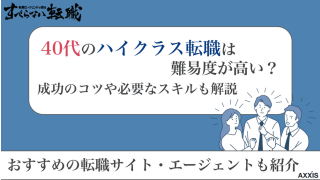
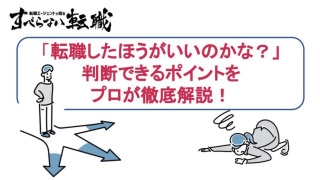
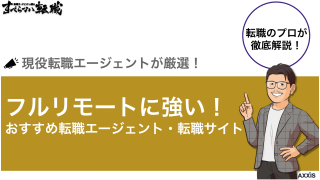
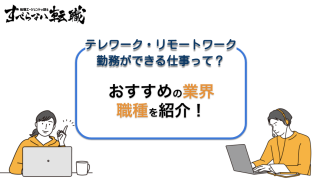
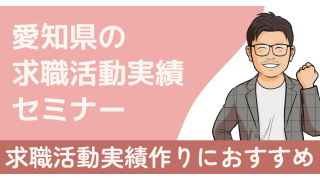
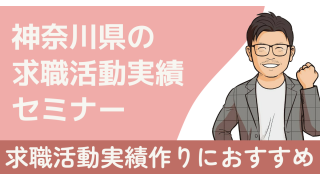
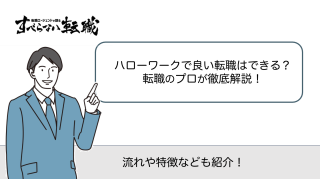
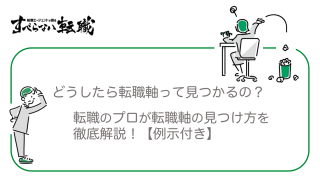
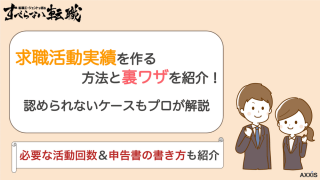
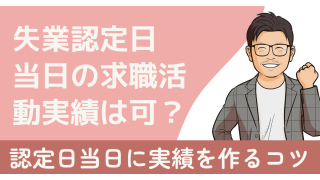







また、結婚に伴い引越し(住所変更)をする際には、結婚を証明する戸籍謄本などの書類や、引越しを証明する住民票などの提出も必要になります。