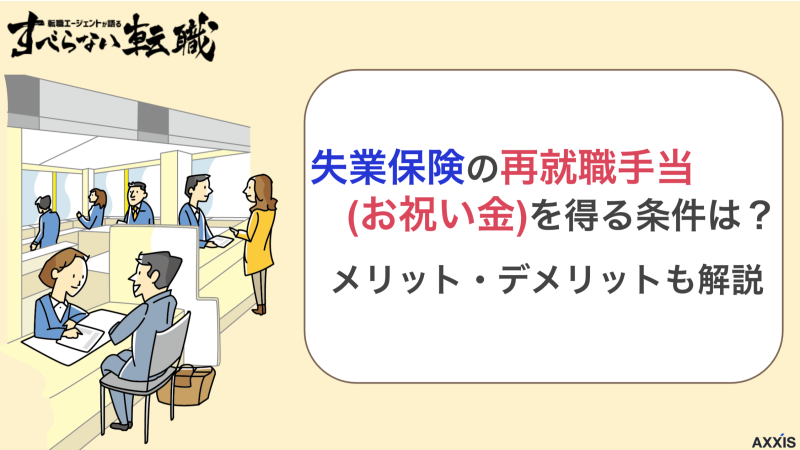
失業保険の再就職手当(お祝い金)を得る条件は?メリット・デメリットも解説
- リクルートの経験を活かしたポイントを解説!
- 失業保険と再就職手当(お祝い金)の違いは目的とタイミング
- 再就職手当(お祝い金)のメリットは経済的に安定すること!
失業保険と再就職手当(お祝い金)の違いをはじめ、受給条件や計算方法、申請手続きの流れや注意点について、わかりやすく詳しく解説しています。
他にも再就職手当(お祝い金)を受け取るメリット・デメリットも紹介します。
すべらない転職が紹介するサービスの一部には広告を含んでおり、当サイトを経由してサービスへの申込みがあった場合には、各企業から支払いを受け取ることがあります。ただし、ユーザーの利益を第一に考え客観的な視点でサービスを評価しており、当サイト内のランキングや商品の評価に関して影響を及ぼすことはございません。
失業保険と再就職手当(お祝い金)の違い
失業保険と再就職手当(お祝い金)はどちらも雇用保険から支給される給付金ですが、その目的や支給されるタイミング、条件が大きく異なってきます。
失業保険と再就職手当の違い
-
失業保険
職を失った人が再就職するまでの生活を安定させて、安心して求職活動がおこなえるように支援するのが目的。
失業保険の支給されるタイミングとしては、申し込み後7日間の待機期間を経て、自己都合退職の場合はさらに原則1ヶ月の給付制限期間を終えて支給される。 -
再就職手当(お祝い金)
再就職手当(お祝い金)は、失業保険の受給資格のある人が、所定給付日数を残して早期に安定した職業に就いた際に、その早期の再就職を促進・奨励するために支給されるもの。
支給されるタイミングは、再就職が決まって実際に働き始めてから申請し、ハローワークの審査を通過できれば一括で支給される。
できるだけ早く再就職したい人やブランクを作りたくない人は、再就職手当(お祝い金)を受け取るほうが経済的なメリットが大きく得られますよ。
一方、慎重に仕事を探したい人や少しだけ休息をとってから働き始めたい人は、失業保険を所定給付日数分のすべてを受給する選択を取るとメリットになります。
とはいえ、自分の再就職の希望や経済状況などを総合的に判断して決めるのが望ましいですね。
再就職手当(お祝い金)の受給条件
再就職手当(お祝い金)を受給したい人も多いと思いますが、受け取るためにはいくつか条件があり、そのすべてを満たす必要があります。
再就職手当(お祝い金)を受給するための条件は、主に下記に挙げた項目の通りとなっています。
再就職手当の受給条件
- 雇用保険の基本手当の受給資格があること
- 基本手当の支給残日数が3分の1以上あること
- 1年以上安定した職業に就くこと
- 7日間の待機期間が満了していること
- 支給決定日より前に採用が内定していること
- 退職理由による給付制限期間が終了していること
- 再就職先が離職前の事業主とは異なる事業主であること
- 雇用保険の被保険者資格を取得していること
- 過去3年以内に再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けていないこと
所定給付日数のうち、就職日の前日時点で3分の1以上の日数が残っていることが条件にされていますが、基本手当の支給残日数が3分の2以上残っている場合は支給率が高くなります。
もちろん、正社員だけではなく契約社員や派遣社員、アルバイトやパートでも、雇用期間が1年以上あれば再就職手当(お祝い金)の対象になりますよ。

再就職手当(お祝い金)の計算方法
再就職手当(お祝い金)がもらえる受給条件を把握した後に知りたいのは、具体的にどのくらいの金額を支給してもらえるのか、という点ですよね。 再就職手当(お祝い金)の計算方法は「基本手当日額×支給残日数×給付率=再就職手当の支給額」となっています。基本手当日額
雇用保険の基本手当(失業保険)の1日あたりの支給額。
支給残日数:所定給付日数(失業保険をもらえる総日数)から、再就職の前日までに基本手当が支給された日数を差し引いた日数。(待機期間・給付制限期間を除く)
給付率
支給残日数によって給付率が変わってくる。3分の2以上残っている場合は70%、3分の1以上残っている場合は60%。
つまり、再就職するのが早ければ早いほど支給率が高くなり、受け取れる手当額も多くなるということですね。
再就職手当(お祝い金)は再就職のタイミングと残された給付日数によって大きく変動しているため、再就職が決まった際にはハローワークで正確な支給残日数と、基本手当日額を確認するのが重要になってきます。
再就職手当(お祝い金)の申請手続きと流れ
再就職手当(お祝い金)の申請手続きと流れについてですが、事前にしっかりと押さえておきたいところですよね。
再就職が決まり次第速やかに手続きを進めることが大切になってくるため、流れを把握してスムーズに手続きがおこなえるように準備しておきましょう。
ここでは、再就職手当(お祝い金)の申請手続きの流れを紹介していきます。
再就職手当の申請手続きと流れ
再就職が決定したらハローワークに連絡する再就職が決定したらハローワークに連絡する
再就職が決まり次第、新しい会社に入社する前、もしくは入社後にできるだけ早く、自分が住んでいるエリア管轄のハローワークに連絡を入れるようにしましょう。
この際「再就職手当の申請をしたい」という旨を伝えればOKですよ。申請の旨を伝えた後は、再就職手当(お祝い金)の手続きに必要な書類があるので、しっかりと準備しておきましょう。
最後の失業認定を受ける
再就職手当(お祝い金)の申請を申し込んだら、次は最後の失業認定を受ける必要があります。
就職日の前日が失業認定日になるケースが多いので、その日にハローワークまで出向いて、最後の失業認定を受けましょう。
認定日には就職活動の状況を申告して、失業保険の支給残日数を確認することになります。この際、ハローワークから「再就職手当支給申請」が渡されます。管轄のハローワークによっては初回説明会などで渡されている場合もあります。
再就職手当支給申請書の記入と事業主の証明
「再就職手当支給申請書」を受け取ったら、今度は再就職手当支給申請書にある名前や受給資格者番号などを記入していきます。
他にも、会社名や所在地、電話番号や雇用形態といった再就職先の情報も合わせて記載していきます。再就職手当支給申請書には、再就職先の事業主による証明が必要になります。
これは自分自身がその会社に雇用されることをはじめ、雇用期間が1年以上見込まれることなどを会社側が証明する欄となっています。そのため、新しい会社の担当者や人事部などにお願いをして、必要事項に記入・捺印してもらいましょう。
申請に必要な書類を準備する
再就職手当支給申請書への記入を済ませたら、次におこなうのは申請に必要な書類を準備することです。
申請に必要な書類は主に下記にまとめたものとなっています。
再就職手当の申請に必要なもの
- 再就職手当支給申請書
- 雇用保険受給資格証
- 採用証明証
- 印鑑
- 振込希望金融機関の通帳・キャッシュカード
- 雇用契約書・労働条件通知書
上記に挙げたものは再就職手当の申請をする際に必要になるため、忘れずに用意しましょう。
採用証明書はハローワークから支給決定時に渡されることがありますが、基本的には新しい会社に記入してもらいます。

また、場合によっては雇用契約書や労働条件通知書といった、雇用期間や労働条件が確認できる書類の提出が求められることもあります。
ハローワークへ申請書を提出する
必要な書類をすべて準備できたら、就職日(入社日)の翌日から1ヶ月以内に管轄のハローワークへ出向いて書類を提出します。
郵送での提出も可能ですが、万が一何か不備があった場合に備えて直接窓口まで出向いて提出するのが良いですね。
ちなみにハローワークが比較的に空いている時間帯は、火曜日〜金曜日の午後である傾向が見られるから、タイミングを合わせてハローワークに行ってみてください。
ハローワークによる審査
ハローワークにすべての書類を提出すると、ハローワーク側で提出された書類と内容をもとにして、再就職手当(お祝い金)の支給条件を満たしているかどうかの審査がおこなわれます。
この審査は通常1ヶ月〜2ヶ月程度かかる傾向にあるものの、内容に疑問が生じる際には、さらに時間を要するケースもあります。
また、場合によってはハローワークから再就職先の会社に、在籍確認の連絡が入ることもありますね。
支給決定通知書の送付と入金
ハローワークの審査が完了して再就職手当(お祝い金)の支給が決定されると、自宅に「支給決定通知書」が郵送されます。
支給決定通知書が届いてからは、通常1週間程度で指定した金融機関の口座に再就職手当(お祝い金)が一括で振り込まれますよ。
再就職手当(お祝い金)を受給する際の注意点
再就職手当(お祝い金)を受給するとなったときには、いくつか気をつけておきたい点があります。
中でも1番注意したいのは「支給要件をすべて満たしていること」が挙げられますね。支給要件は全部で8つ用意されていますが、このうちどれか1つでも条件が欠けてしまうと、再就職手当(お祝い金)がもらえません。
他にも再就職手当(お祝い金)を受け取るための注意点があるので、順番に解説していきますね。
申請期限を厳守する
再就職手当(お祝い金)を受給する際に注意したいのは「申請期限を厳守する」ことですね。原則として再就職した日の翌日から1ヶ月以内とされています。
万が一申請期限が過ぎてしまっても再就職手当には「時効」という期間が設けられているので、就職日の翌日から起算して2年間は申請することが可能となっています。
つまり2年間以内であれば、ハローワークに再就職手当(お祝い金)の申請をして受け取れる可能性があります。

ただ、時間が経過してしまうと採用証明書など会社に記入してもらう書類の手配が難しくなるため注意が必要です。
支給要件をすべて満たしているか確認する
再就職手当(お祝い金)を受け取るためには、8つの受給資格をすべて満たす必要があります。
どれか1つでも欠けている条件がある場合、再就職手当(お祝い金)は支給対象外になってしまいます。
なぜなら、再就職手当(お祝い金)は雇用保険の基本手当(失業保険)の残りの給付日数を放棄する代わりに、早期の再就職を奨励するための特別な手当だからです。
そのため、制度の公平性を保って不正受給を防ぐために、とても厳格な条件が設けられています。
正確な情報申告を徹底する
再就職手当(お祝い金)の申請をする際には、虚偽の申告は絶対に避けて、必ず正確な情報を申告するようにしましょう。もし、申請内容に事実と異なる内容があると不正受給とみなされてしまいます。
もし虚偽の申告をしたとしても、ハローワークは勤務先の雇用保険の加入状況や、税務情報などから申請者が勤務していたことを把握する仕組みを持っているので、バレる可能性が非常に高いです。
不正受給が発覚すると、支給された手当の全額返還だけではなく、不正受給した額の2倍に相当する金額の納付が命じられるといった、重いペナルティが課せられるので注意しましょう。
必要書類の準備と不備がないか確認する
再就職手当(お祝い金)の申請をする際に提出する書類が多くあるため、どの書類が必要なのか、記入する際にどこか不備はないかどうか、しっかり確認するようにしましょう。
例えば、再就職手当支給申請書は自分自身だけではなく、会社に記入してもらったり捺印してもらったりする必要があるので、漏れがないように確認するのが大事ですね。
他にも印鑑はシャチハタが不可にされている場合もあります。書類に不備があるとハローワークの審査が遅れたり、再提出が必要になったりするので注意してください。
疑問や不明点はすぐハローワークに相談する
再就職手当(お祝い金)を受け取る前には再就職の条件をはじめ、自分が再就職手当の対象になるかどうかといった部分までハローワークに相談しておくのがベストです。
再就職手当(お祝い金)は個々によって支給額などが大きく変動するからこそ、自分の場合はどうなるのか事前にきちんと疑問や不安、不明点などを確認しておくと安心できますよ。
さらに、担当者によっては解釈が異なる場合もあるので、具体的に質問してメモを残すようにしましょう。
再就職手当(お祝い金)を受給するメリット
再就職手当(お祝い金)を受給しようか悩んでいる人の中には、どんなメリットがあるのか知っておきたい人もいますよね。
大きなメリットとしては「経済的なメリットが大きい」という点が挙げられます。まとまった一時金を受け取ることができるので、新しい仕事や必要な準備資金に充てることができますよ。
他にも再就職手当(お祝い金)を受け取るメリットがあるので、順番に解説していきますね。
再就職手当を受給するメリット
経済的メリットが大きい
再就職手当(お祝い金)を受け取るメリットとして、経済的メリットが大きいことが挙げられますね。
失業保険の残りの給付日数のうち、60%〜70%に相当する金額が一括で支給されるので、引越し費用や生活費、新しい仕事に必要な準備資金などに充てることができます。
失業保険は月々の支給になりますが、再就職手当(お祝い金)はまとまった一時金として受け取れるのがメリットですね。

とくに、支給残日数が多くあり、給付率が70%で支給される場合は、金銭的なメリットがとても大きくなりますよ。
早期の生活が安定する
再就職手当(お祝い金)を受給するメリットとして、早期に再就職が決まることで生活を安定させられることも挙げられます。毎月の給与収入が途切れる期間が短くなるため、生活がそれだけ早く安定します。
また、再就職手当(お祝い金)が支給されることにより、転職活動中の貯蓄を減少させたり、経済的な不安も軽減されて精神的な安心感も得られるのもメリットとして挙げられますね。
社会保険料の負担が軽減される
再就職手当(お祝い金)を受け取ることができれば、社会保険料の負担軽減にも繋がります。
早い段階で再就職して勤務先の社会保険に加入できると、失業保険受給中に自分で支払う必要があった、国民健康保険・国民年金保険料の負担がなくなりますよ。
失業保険の基本手当日額が高い場合は、失業中に扶養から外れて自分で社会保険料を支払う必要が生じます。しかし、早期に再就職できればその期間が短縮されるので、全体の社会保険料の負担が軽減されます。
再就職手当(お祝い金)を受給するデメリット
再就職手当(お祝い金)を受給するメリットがあれば、もちろんデメリットもあります。
もっとも大きなデメリットとしては「失業保険の残り分が受給できない」ことが挙げられますね。再就職手当は残りの失業保険の給付日数を放棄することの引き換えとして支給されるため、最大のデメリットだと言えます。
他にも再就職手当(お祝い金)を受け取るデメリットがあるので、それぞれお伝えしていきますね。
再就職手当を受給するデメリット
失業保険の残り分が受給できない
再就職手当(お祝い金)を受け取るとなった場合、失業保険の残り分が受給できないのが最大のデメリットとなりますね。
というのも、再就職手当(お祝い金)は残りの失業保険の給付日数を放棄することの引き換えとして支給されるからです。
そのため、所定給付日数が120日で、90日残して再就職手当(お祝い金)を受給した場合、本来残り90日分受け取れたはずの失業保険が支給されないということになります。

だからこそ、失業保険をすべて受け取った総額よりも再就職手当(お祝い金)で得られる金額のほうが少ない場合は、デメリットになる可能性が高いですね。
早期再就職のミスマッチのリスクがある
再就職手当(お祝い金)は就職先が決まって申請すると支給されますが、再就職手当のために焦って就職先を決めてしまうリスクがある点がデメリットになりますね。
しっかりと企業研究や企業分析、情報収集などをせずに求人へ応募して内定獲得したのち、入社してしまうと「こんなはずじゃなかった」とミスマッチが生じてしまう可能性が高いです。
その結果すぐに退職してしまうということにも繋がりかねません。
早期退職してしまったとしても再就職手当(お祝い金)の返還を求められることはありませんが、再度失業保険を受給するために新たな被保険者期間を築かなければならないので、生活が不安定になる可能性があります。
支給審査に時間がかかるケースがある
ハローワークに再就職手当(お祝い金)の申請をするとなった際には、申請から支給されるまでに時間がかかるケースもあります。
通常ハローワークの審査は1〜2ヶ月ほどかかると言われていますが、場合によってはもう少しかかることもありますね。
待機期間である7日間は就労ができず、失業保険が支給されることもないため、ある程度は生活費に余裕を持てるようにしておくと良いでしょう。
条件が細かく不支給になる可能性がある
再就職手当(お祝い金)は条件が細かく設けられているのがデメリットとして挙げられますね。
具体的には「1年を超えて安定した職業に就く見込みがあること」「受給資格決定によりも前に内定が出ていないこと」など、細かく手厳しい条件がいくつも設けられています。
設けられた条件を1つでも満たしていない場合は、再就職手当(お祝い金)を受け取ることができません。

とくに会社都合退職ではなく自己都合退職の場合、給付制限期間中の就職は紹介元がハローワークでないと対象外になるので注意が必要ですね。
再就職手当(お祝い金)に関するよくある質問
ここでは、再就職手当(お祝い金)を受給する際によくある質問をいくつかピックアップして、それぞれ回答していきます。
失業保険と再就職手当はどっちが得?
失業保険と再就職手当(お祝い金)のどちらが得なのか、それは自分自身の状況やキャリアプランによって変わってきます。
失業保険を受け取るメリットは、転職活動がじっくりできることやスキルアップ・休養に充てることができる点です。
デメリットは再就職までのブランクが長期に及ぶ可能性があることや社会保険料の負担が挙げられます。
一方、再就職手当(お祝い金)のメリットはまとまった金額がもらえることや、社会保険料の負担軽減となっています。
デメリットは失業保険の残り分が受け取れない、支給条件が厳しいことですね。
どちらが自分にとって得になるのかについては、再就職の目処が立っているか、経済的な余裕はあるかどうか判断して決めるのが良いでしょう。
再就職手当は正社員以外でももらえる?
再就職手当(お祝い金)は正社員以外の雇用形態でも受給できます。契約社員や派遣社員、アルバイトやパートでも問題ありません。
ただ「雇用保険の被保険者になること」「1年を超えて勤務することが確実であると認められること」という2つの条件をクリアする必要があります。
しかし、明確に1年未満の短期雇用であることがわかっている場合、または契約更新の見込みがない場合は対象外になるため注意が必要です。
再就職手当の受給後すぐ退職したら返還義務が生じる?
結論から申しますと、再就職手当(お祝い金)をもらった後すぐに退職しても、返還義務は生じません。
なぜなら、支給条件が「1年を超えて勤務することが確実であると認められること」というのは、あくまでも支給申請時点での見込みだからです。
実際に1年勤務を継続できなかったとしても見込みが正当なものであれば返還は求められません。ただし、不正受給とみなされた場合は返還義務が生じるので気をつけましょう。
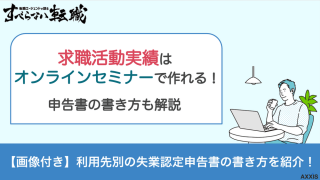
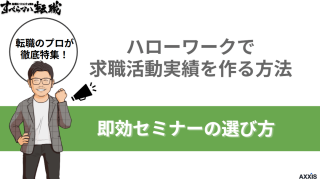
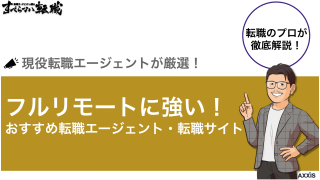
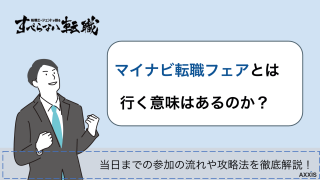
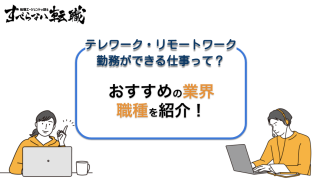
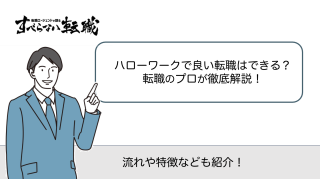
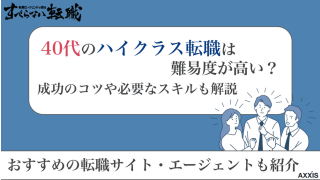
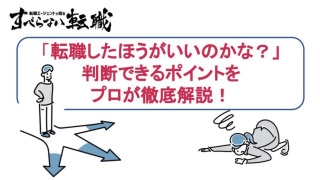
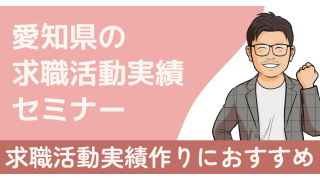
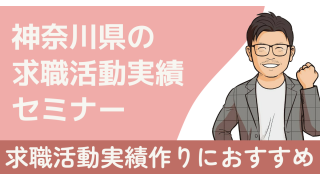







また、個人事業主として独立開業した場合でも、一定の要件を満たすことができれば対象になるケースがあります。