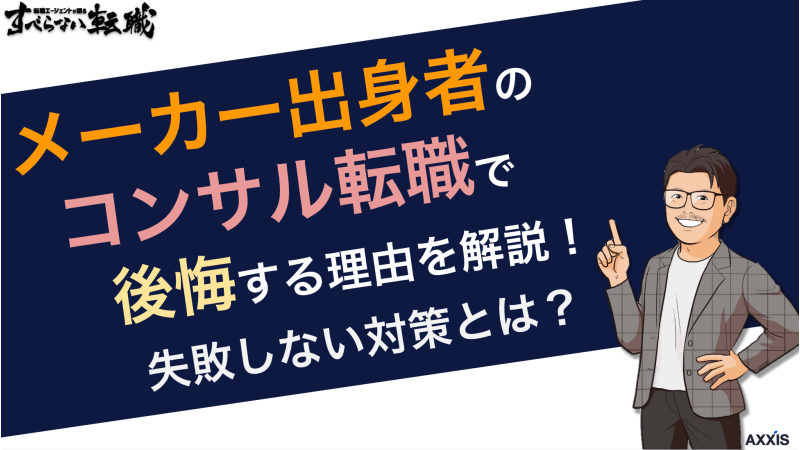
メーカー出身者のコンサル転職で後悔する理由を解説!失敗しない対策とは?
メーカーからコンサルへ転職して後悔する理由を徹底解説。
激務やスキルのギャップなど業界特有の課題を整理し、後悔しないための準備と対策を紹介します。
すべらない転職が紹介するサービスの一部には広告を含んでおり、当サイトを経由してサービスへの申込みがあった場合には、各企業から支払いを受け取ることがあります。ただし、ユーザーの利益を第一に考え客観的な視点でサービスを評価しており、当サイト内のランキングや商品の評価に関して影響を及ぼすことはございません。
メーカーからコンサル転職で後悔する人は多い?
メーカーからコンサルに転職したものの、後悔する人は一定数います。
仕事の進め方が大きく変わり、成果主義の厳しさに直面して「想像以上に大変だ」と感じるケースが少なくありません。
とくに、機械や製品を扱ってきた環境から、人や組織を相手にする仕事へ移ることで戸惑う人が多いのも現状です。
その背景には、仕事の性質の違いがあります。
メーカーでは時間をかけて「ものづくりをする」働き方が中心となりますが、コンサルでは短期間で成果を出すことが重視されます。
そのため仕事の進め方とのギャップを感じ、後悔に繋がる人が少なからず存在するのです。


メーカーからコンサルへ転職を考えている場合、まずは転職サイトを活用して情報を集めるのがおすすめです。
業界ごとの仕事内容や求められるスキル、働き方の違いなどを簡単に比較できます。
さらに、元コンサル出身のアドバイザーがサポートしてくれる転職サービスだと、実践的な面接対策やキャリア相談も可能です。
無料で利用できるので、まずは登録して自分に合った会社を探してみてください。
おすすめの大手総合型転職エージェント
-
リクルートエージェント
業界No1!転職者の8割が利用する最大手の定番エージェント -
doda
顧客満足度トップクラス!サポートが手厚い定番エージェント -
マイナビ転職エージェント
20代支持率No.1!若手を採用したい企業の正社員求人が多数
メーカー出身者がコンサル転職で後悔しやすい理由
メーカーからコンサルに転職すると、仕事の性質や評価基準の違いから後悔しやすい傾向があります。
ここでは代表的な理由を3つ紹介します。
スキルや知識のギャップに戸惑う
メーカー出身者は、コンサルに転職した後にスキルや知識の違いに戸惑う人が多いです。
製品や機械に関する専門知識は豊富でも、人や組織を対象にした課題解決には直結せず、適応に時間がかかりやすいです。
メーカーの仕事では研究開発や生産管理などの専門性が重視されます。
しかし、コンサルの現場では論理的な思考力や顧客への提案力など幅広い力が求められます。
そのため、コミュニケーションやデータ分析の面で不足を感じ、職務の変化に苦労する人も少なくありません。

最初は業務内容の違いに戸惑うのは自然なことです。
むしろ「新しい環境で伸ばせる力が多い」と考えると前向きになれますよ。
少しずつ慣れていけば、自分の強みと新しい学びを組み合わせて成長していけます。
激務・成果主義の働き方に適応できない
コンサル業界は成果主義が強く、長時間労働も多いため、メーカー出身者の中には適応できず後悔する人もいます。
安定した環境で製品を扱っていた働き方から、人を相手に常に成果を求められる環境へ移ることで、大きな負担を感じやすくなるのです。
メーカーでは製品開発や生産に時間をかけられるのに対し、コンサルは限られた期間で成果を出さなければなりません。
さらに評価は個人単位で厳しく管理されるため、仕事のペースや圧力に慣れず、後悔につながるケースが少なくないのです。

成果を厳しく求められるのは確かに大変ですが、そのぶんやりがいも大きいのがコンサルです。
最初から完璧にこなす必要はなく、少しずつ環境に合わせて工夫していけば、自分なりの働き方を見つけられますよ。
将来のキャリアパスが不透明になる
メーカー出身者がコンサルに転職すると、将来のキャリアパスが見えにくいと感じることがあります。
仕事内容がこれまでの職種と大きく異なるため、どのように成長できるのかや、自分の市場価値が分かりづらくなるのです。
コンサルではプロジェクトごとに求められるスキルや成果が変わり、経験年数だけで昇進や評価が決まるわけではありません。
さらにメーカーでの経験が直接役に立たない場合もあり、キャリアの方向性を描きにくい状況に直面する人が少なくないのです。

キャリアの先が見えにくいのは不安ですが、自分で選択肢を広げられるのもコンサルの特徴です。
プロジェクトを通じて得られる経験をどう活かすかを意識すれば、強みを作るきっかけにできますよ。

将来のキャリアプランに迷っているなら、コンサル転職だけでなく、メーカーや設計職の経験を活かせる転職先も視野に入れてみるのがおすすめです。
製造業の求人が豊富な転職サイトや、機械設計から一般企業への転職について解説した記事もあります。
キャリアの幅を広げるヒントになりますので、ぜひ参考にしてみてください。
コンサル転職で後悔しないための準備と対策
コンサル転職は、しっかりとした準備をして臨むかどうかで結果が大きく変わります。
自己分析やスキルの習得を怠ると、入社後にメーカーとコンサルとのギャップを感じて後悔につながることもあります。
一方で、事前にやるべき対策を押さえておけば、キャリアの方向性を明確にし、自分に合った働き方を選べるようになります。
ここでは具体的な準備と対策を2つ紹介します。
自己分析で「なぜコンサルか」を明確にする
コンサル転職で後悔しないためには、自己分析を通じて「なぜコンサルに挑戦したいのか」を明確にすることが大切です。
仕事に求めるやりがいや、自分の強み・成長したい分野を整理することで、転職先の選択がぶれにくくなります。
自己分析によって、現在のスキルや知識の棚卸しができ、将来のキャリア目標もはっきりします。
これにより、メーカーで培った経験をどのように活かせるかを把握し、人や仕事内容とのミスマッチを避けやすくなるのです。
その結果、入社後の満足度を高め、後悔のないコンサル転職につながります。

ちょっとした自己分析の習慣でも効果があります。
たとえば、日々の業務で「得意だと感じること」「苦手だと感じること」をメモしていくと、自分の強みや方向性が見えてきます。
小さな積み重ねが、転職の軸を固める助けになるのです。
入社前にスキルと心構えを身につける
メーカーからコンサルへ転職する際には、事前に基礎スキルを磨き、心構えを整えておくことが大切です。
具体的には、論理的思考力や資料作成力、データ分析力などの力を高め、柔軟な考え方や主体性を意識しておくことが、転職後の後悔を防ぐポイントになります。
コンサルタントは短い期間で成果を出すことが求められるため、単なる作業だけでなく、人を動かすコミュニケーション力や自ら学び続ける姿勢が不可欠です。
入社前の準備があるかどうかで適応力に差が出やすく、その後のキャリア形成や職場での評価にも大きな影響を与えるのです。

いきなり完璧なスキルを身につける必要はありません。
たとえば普段から「物事を結論から説明する練習」や「数字で根拠を示す意識」を持つだけでも、コンサル的な考え方に近づけます。
日常のちょっとした工夫が、入社後の大きな助けになるのです。

コンサルに転職したい人はMyVisionがおすすめです。
キャリアアドバイザーの多くは元コンサル出身であり、現場で培ったノウハウを活かした実践的なケース面接対策が可能です。
これにより、未経験からコンサル業界を目指す人でも、自信を持って選考に臨めます。
実際の業務イメージやキャリア形成の相談にも丁寧に対応してくれ、転職成功率の高さに定評があるサービスですよ。
コンサル転職に向いている人・向いていない人
向き不向きを理解することで、入社後に感じるギャップやミスマッチを減らすことができます。
とくに、仕事の進め方や求められるスキルがメーカーとは大きく異なるコンサル業界では、自分に合った働き方かどうかを事前に把握することが重要です。
ここでは、コンサル転職に向いている人と向いていない人の特徴を詳しく紹介します。
コンサル転職に向いている人の特徴
コンサル転職に向いている人は、考えを整理して伝える力と、人と上手にやり取りする力を持ち、学び続ける意欲がある人です。
変化の多い環境でも柔軟に動き、自分で課題を見つけて解決方法を考えられます。
コンサルの仕事では知らない業界やテーマに取り組むことも多いため、情報を吸収して整理する力や、人と円滑にやり取りする力が必要です。
こうした力を持つ人は、仕事でも成果を出しやすく成長も早くなります。
コンサル転職に向いている人
- 新しい課題にも前向きに取り組める
- 考えを整理してわかりやすく伝えられる
- チームや相手とスムーズにやり取りできる
- 自ら学び、成長し続けられる
コンサル転職に向いていない人の特徴
コンサル転職に向いていない人は、指示を待つことが多く、自ら学ぼうとする意欲が低い人です。
変化やプレッシャーに弱く、安定した環境を好む場合も多く、仕事との相性が合わず後悔しやすくなります。
コンサルの仕事では常に新しい課題に取り組み、短期間で成果を求められるため、自ら考えて行動する力や学ぶ意欲が欠けていると適応が難しくなります。
安定やルーティンを重視する人は環境の変化に対応できず、早期に転職を後悔する可能性が高いです。
コンサル転職に向いていない人
- 指示待ちが多く、自分から行動できない
- 新しい知識やスキルの習得に消極的
- 変化やプレッシャーに弱い
- 安定志向が強く、環境の変化に適応できない
メーカーに転職を考える人は以下の記事をご覧ください。選び方から、失敗しない活用術まで解説しています。
以下の記事では、「向いていないと思う仕事を辞めるタイミング」を紹介しています。ぜひご覧ください。
コンサル転職で後悔しない選択をしよう
コンサル転職で後悔しないためには、自分の適性や希望に合った会社を選び、将来のキャリアプランまで考慮した判断が重要です。
会社ごとに業務内容や文化、求められるスキルは異なるため、適性に合わない会社を選ぶと入社後のミスマッチにつながりやすくなります。
転職サイトやエージェントを活用すると、複数の会社の情報を効率的に集めて比較でき、自分に合った選択がしやすくなります。

さらに転職サイトは無料で利用でき、複数の会社の情報をまとめて比較できるだけでなく、社員の実際の声や給与・待遇の違いも確認できます。
自分に合った会社を見つけやすくなるので、迷っている人はまず相談・登録してみてくださいね。
コンサル業界に強い転職サイトを紹介しています。ぜひご覧ください。
メーカーからコンサル転職で後悔する人によくある質問
メーカーからコンサル転職で後悔する人によくある質問をまとめました。
理系大学院卒でメーカーではなくコンサルに就職した場合、後悔することはありますか?
理系大学院卒で直接コンサルに就職した場合でも、後悔する可能性はゼロではありません。
理由としては、仕事の性質や求められるスキルが想像と異なることや、短期間で成果を出す環境に適応できず戸惑う場合があるためです。
ただし、メーカー経験を経ずにコンサルに入る場合は、研究開発や製品知識のギャップに悩むことは少なく、入社前に業界研究やケース面接対策をしっかりおこなえば、後悔のリスクを大きく減らせます。
転職して後悔する人は何割くらいですか?
コンサル転職で後悔する人の正確な割合を示す統計は公開されていません。
ただし、業界の特性や体験談から、一部の人が環境や仕事内容に適応できず、後悔を感じるケースがあることはわかっています。
プレッシャーの大きさや成果主義の厳しさ、人や組織を相手にする業務への戸惑いなどが、主な理由として挙げられます。
コンサルは何年で辞める人が多いですか?
正確なデータはありませんが、コンサルは3〜5年程度で次のキャリアを考える人が多い傾向があります。
経験を積む中で自分に合う働き方や専門性を見極める人も多く、焦らず自分のペースで将来を考えることが大切です。
大手や人気企業の求人を多数保有!大手エージェント
大手エージェントには、全業界・職種の求人が集まっています。さらに、大手企業や人気企業の求人を独占で持っていることも。
幅広い選択肢の中から求人を提案してもらいたい、大手企業や人気企業への転職を検討しているという方は登録しておきましょう。
業界No.1!転職者の8割が利用している
国内最大の定番エージェント
おすすめポイント
- 求人数が業界No.1!人気企業・大手企業の非公開求人を多数保有
- 数の強みを活かした幅広い業界・職種の提案が可能
- たくさんの求人の中から比較検討できる
CMでおなじみ!顧客満足度トップクラス!
豊富な求人数に加えて、専任アドバイザーの手厚いサポートが強み
おすすめポイント
- リクルートと並ぶ、実績豊富な国内最大級の転職エージェント
- 20万件以上(2023年3月時点、非公開求人を含む)の求人から、厳選して紹介をしてくれる数少ないエージェント
- リクルートが保有していない有名企業の求人に出会える可能性が高い
20代の登録者数No.1!
20〜30代前半・第二新卒向けの非公開求人を多数保有
おすすめポイント
- 新卒サイトNo.1のマイナビが運営。若手層を採用したい企業とのコネクションが豊富
- 営業、メーカー、金融、ITなどの転職支援に強み
- 20〜30代など若手層の転職サポート・アドバイスの手厚さに定評あり
メーカーエンジニアの転職に特化した転職エージェント
機械設計や半導体製造、生産管理、機械エンジニアの人は、業界特化のマイナビメーカー AGENTへの相談がオススメ
※関東エリアの求人が中心となっているので、他エリアの求人は少なめです
おすすめポイント
- メーカー、ものづくり業界に特化したエージェント
- ものづくり業界出身のキャリアアドバイザーがニーズにマッチした求人を紹介
- 大手だけではなく、中小の優良企業やベンチャー企業の求人も保有
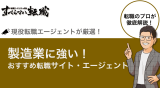

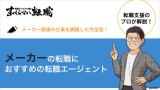
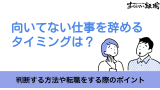





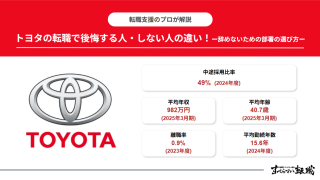
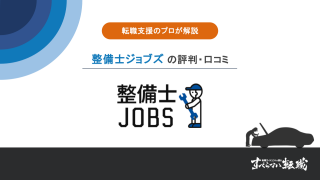

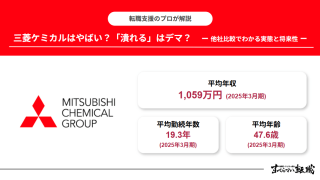

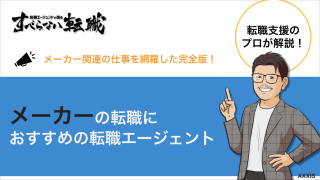

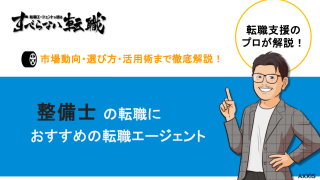
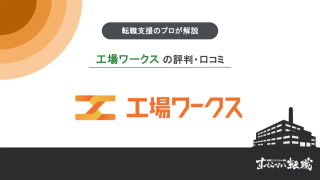
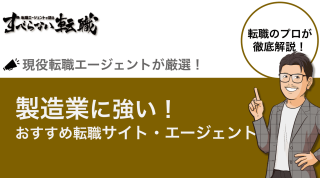







メーカーからコンサルへ移ると、仕事のスピード感や成果の出し方に大きな違いを感じる場面が少なくありません。
戸惑うこともありますが、その分、仕事のスピード感や進め方、同僚の雰囲気などビジネスマンとしての経験値が豊富に積めます。
こうした経験の積み重ねが将来の成長につながり、非エンジニアとしてキャリアパスを広げられるのが大きな旨みです。
転職を前向きに捉える姿勢がとても大切ですよ。