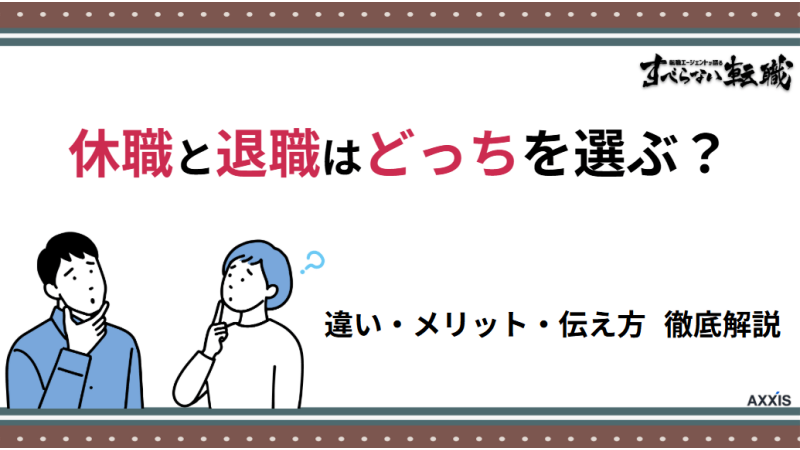
休職と退職はどっちを選ぶ?違い・メリット・伝え方を徹底解説
休職と退職のどちらを選ぶべきか、迷う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、違いやメリット、会社への伝え方、転職の選択肢、失業保険の注意点まで解説しています。
有給の消化と挨拶マナーについても説明していますので、参考にしてくださいね。
すべらない転職が紹介するサービスの一部には広告を含んでおり、当サイトを経由してサービスへの申込みがあった場合には、各企業から支払いを受け取ることがあります。ただし、ユーザーの利益を第一に考え客観的な視点でサービスを評価しており、当サイト内のランキングや商品の評価に関して影響を及ぼすことはございません。
休職か退職のどちらが良いか迷った時の判断基準
今働いている会社を「休職」するか「退職」するか迷った時は、以下の判断基準を参考にすると良いですよ。
休職をした方が良いケース
今働いている会社との関係を維持したいと考えている場合は、退職よりも休職を選んだ方が良いですね。
特に、出産・育児・介護で一時的に長期的な休みが欲しい場合は、退職よりも休職を選んだ方がキャリアへの影響は少ないです。
また、精神疾患や怪我で休職する場合も、会社とのつながりを保っておくと、復職しやすくなりますよ。
退職をした方が良いケース
今の会社に不満やストレスを感じていたり、新しい環境で働きたいと考えている場合は、退職を前提に転職活動をした方が良いですね。
また、育児や介護で復職の目処が立っていない場合や今の会社で働き続けるのが難しい場合には、退職を視野に入れることも一つの選択肢です。
そのほか、ハラスメントを受けていて精神的につらいと感じている場合は、体調を崩す前に早めに退職した方が良いですよ。

休職と退職の違い
休職と退職には、それぞれ以下のような違いがあります。
休職と退職の定義の違い
休職と退職はそれぞれ以下のように定義されています。
-
休職
労働契約を維持したまま、一時的に労働の義務を免除されること -
退職
会社との労働契約を終了すること
休職は、傷病の療養や育児・介護など、長期的な休みが必要な人向けの制度で、退職は会社を辞める際におこなう手続きとなります。
また、会社の制度によっては休職中でも手当や給付金が支給されることもあり、これが退職との大きな違いですね。
法的な取り扱いの違い
休職と退職は、法的な取り扱いには以下のような違いがあります。
| 休職 | 退職 | |
|---|---|---|
| 雇用契約 | 継続 | 終了 |
| 業務 | 一時中止 | 終了 |
| 給与 | 会社によって支給されることもある | 支給されない |
| 福利厚生 | 継続的に利用できる可能性あり | 権利喪失 |
| 復職 | 原則として可能 | 不可 |
| 法的な取り扱い | 会社が任意で就業規則の規定に基づいて設けている制度 | 労働者の意思表示による自己都合退職や解雇などの会社都合退職がある |
休職は就業規則にもとづいて会社が任意に設けている制度であり、雇用契約は継続され、理由によっては一定の給与が支払われることもあります。
一方、退職は雇用契約が終了するため、一般的には給与は契約終了と共に終わり、福利厚生の権利も失われるのが違いですね。
休職のメリットとデメリット
休職するか決める際には、メリットとデメリットも把握した上で決めることが大切です。
メリット|生活とキャリアの安定
休職するメリットには以下のようなものが挙げられます。
休職するメリット
- 療養・治療に専念できる
- 復職の可能性を残せる
- 制度や手当の受給ができる
休職は、会社との雇用契約を維持したまま業務を一時的に中断する制度なので、仕事から離れて育児・介護・療養に専念できます。
また、休職は復職の可能性が残せたり、制度を活用して休職中に給与額の一部を受給できる可能性がある点もメリットとして挙げられますね。
デメリット|将来の不安と収入減
休職をするデメリットとしては以下のようなものが挙げられます。
休職するデメリット
- 長期の休職はキャリアに影響がある
- 復職できなかったら退職の扱いになる
- 必ずしも手当の受給ができるわけではない
3か月以上休職したら、履歴書や職務経歴書に記載が求められることもあり、休職の事実を偽った場合には経歴詐称とみなされる可能性もあります。
また、休職期間が終わっても復職できない場合は退職勧告を受けることもあります。
そして、休職中は原則として無給なので、手当や給付制度を利用しない限り、休職中の収入はなくなる点には注意が必要ですね。
休職に関する基本情報
休職する際には、休職の種類や期間など、基本情報を把握しておくことも大切です。
ここでは、休職を考えている人に知っておいて欲しい情報をお伝えするので参考にしてみてください。
休職の種類
休職にはいくつか種類があります。
休職の種類
-
傷病休職
業務外の病気や怪我で申請するもの -
自己都合休職
留学やボランティアなど、従業員の個人的な理由で申請するもの -
事故欠勤休職
業務外の事故で長期的に欠勤する時に申請するもの -
起訴休職
刑事事件で起訴された場合に会社が休職を命ずるもの -
組合専従休職
労働組合の業務に専従するために休職する際に申請するもの -
公職就任休職
国会議員や地方議員などの公職についたことを理由に休職する場合に申請するもの -
出向休職
グループ会社や関連会社への出向をする時に、元の会社で休職扱いにする時のもの
休職は正当な理由がなければ承認されないこともあるため、休職を希望する時には、あらかじめ就業規則を確認しておくと良いですよ。
また、自己都合で休職する場合は、交渉内容によっては退職を勧告される場合もあるので、休職の話をする際には慎重に準備を進めることが大切です。
休職期間の目安
休職期間の目安は会社によって異なりますが、一般的には3ヶ月〜6ヶ月程度とされることが多いです。
また、理由次第では1年〜3年の休職も相談できることがあり、休職期間も状況次第で延期の相談も可能です。
ですが、休職に関することは就業規則で規定されていることもあるため、まずは所属会社の就業規則を確認すると良いですよ。
休職中の収入の考え方
ノーワーク・ノーペイの原則により、労働の対価として賃金が支払われるため、休職中は原則として給与は支給されません。
ただし、傷病手当金の支給対象となる場合や、会社の就業規則に基づいて特別手当が支給される場合は、一定の収入を得られることもあります。
また、育児・介護休業など、法定の休業制度に該当する場合は、雇用保険から給付金が支給される仕組みもあります。
これらの条件は会社によって異なるため、制度の内容を把握しておくと安心です。
休職中に申請できる公的手当
公的な手当を活用すれば、休職中でも給与の一定割合の金額をもらうことができます。
-
傷病手当金
病気や怪我で休職した場合の手当 -
労災保険給付・災害補償給付
労災認定を受けた場合に申請できる給付 -
出産手当金
産前産後休業で休んだ時に申請できる手当 -
育児休業給付金
育児休業をした時に申請できる給付金 -
介護休業給付金
介護休業を取得した時に申請できる給付金
休職中に申請できる公的手当は、正当な理由があって申請ができるものなので、個人的な都合での申請はできない点には注意が必要です。
また、傷病手当金や労災保険給付・災害補償給付は、診断書や労災保険支給決定証明願が必要になるので、忘れずに取得しておくと良いですよ。
休職中の副業・アルバイトは要注意
休職中で傷病手当金を受給している場合や会社の就業規則で副業・アルバイトが禁止されている場合には原則として認められていません。
ですが、会社が病気や怪我のリハビリや改善に役立つと判断して許可された場合には認められるケースもあります。
休職理由次第ではありますが、休職中に働くことを良しとしないことも多いので、事前に就業規則を確認したり、相談をしてから判断すると良いですよ。

休職中に収入があった場合、隠していても社会保険料や源泉徴収から収入が明らかになる可能性は高いです。
そのため、副業やアルバイトをする場合は事前に相談して許可を得ておく方が安心ですね。
休職を申し出るときの手続きと会社への伝え方
休職を申し出る時には、休職理由を整理した上で、上司に相談して承諾を得る必要があります。
ここでは、休職を申し出る時に必要な準備や上司への伝え方を紹介するので参考にしてみてください。
申請理由と必要情報の整理
休職申請をする時は、休職理由をまとめた上で診断書や傷病手当支給申告書など、休職理由の正当性を証明するための書類を準備する必要があります。
そして、休職願(休職届)は会社でフォーマットが用意されているなら、会社の様式に合わせて記載して提出します。
また、会社によっては休職のために追加で書類提出が求められることもあるので、事前に就業規則を確認して必要なものを整理しておくと良いですよ。
上司への相談と伝え方
休職の相談をする際には、直属の上司に相談をして話を進めていく必要があります。
その際には、以下の内容をもとに上司に理由を伝えて、話し合いをすると良いですよ。
上司に相談を持ちかける時
本日はお時間いただきありがとうございます。
お時間をいただいた件なのですが、〇〇の理由で休職を検討しております。
休職の時期としては3ヶ月〜6ヶ月程度を考えており、引き継ぎ期間も考慮して、可能であれば〇月〇日を目安に休職の手続きを進められればと考えております。
また、〇〇(休職理由)のことが解消されたら、引き続き〇〇会社で働きたいと考えているため、休職のご相談とさせていただきました。
突然の申し出で大変恐縮ですが、この後どのような形で手続きを進めていけば良いのかも含めてお話しさせていただければ幸いです。
上司との関係性が悪いことが理由で体調を崩してしまっている場合には、人事部の相談窓口や産業医経由で休職の相談をすることも可能です。
また、上司や人事部の相談窓口に取り合ってもらえない場合には、公的機関の相談窓口を活用すると良いですよ。
休職期間と引き継ぎの進め方
休職期間は休職理由や就業規則の規定によって変わるため、まずは相談をした上で適切な期間を設定する必要があります。
また、引き継ぎが困難なケースを除いて、会社に損害が生じないように努める必要があるため、引き継ぎ事項はしっかりと確認しておくことが大切です。
早めに休職したい場合には、事前に自身の仕事内容や引き継ぎ事項をまとめておくと、上司も安心して休職の手続きを進めることができますよ。
休職中に退職を選ぶ際の注意点
休職中に退職を検討している時には、いくつか気をつけておかなければいけないことがあります。
就業規則に沿って退職手続きを進める
休職中に退職をする場合、一方的に退職の旨を伝えるのではなく、就業規則に則って退職の手続きを進めていくことが大切です。
もちろん、法律上では2週間前までに会社に退職の旨を伝えれば問題ありません。
ですが、傷病手当や給付金を受け取っている場合は、退職に際して手続きが必要なこともあるので、事前に就業規則を確認しておいた方が良いですね。
上司に円満退職の意思を伝える
休職中は会社も復職を前提にサポートや仕事の調整をしてくれていることも多いです。
そのため、退職を円満にするためにも、話を切り出す時には感謝の気持ちを伝えることが大切です。
休職中に退職の相談をする時
タイトル:休職中の退職について(〇〇部 〇〇)
お世話になっております。
休職中にてご迷惑をおかけしております。
この度、〇〇(理由)で休職させていただいておりますが、休職期間終了後の復職が難しいとの判断に至り、退職の相談をさせていただければと考えております。
今まで休職中も復職に向けて手厚くサポートしてくださったのにも関わらず、ご期待に添えずに申し訳ありません。
また、退職日に関しては2025年〇月〇日付を検討しております。
突然の申し出で大変恐縮ではありますが、退職に際して必要な手続きについて相談させていただければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
退職の旨を伝えるのは、先にメールで伝えてから話をする形でもかまいませんが、相手の立場に立って丁寧に説明することを心掛けると良いですよ。
傷病手当金から失業保険へ切り替える
休職中に傷病手当の給付を受けている場合は、同じ傷病での療養に限り、退職後も傷病手当は受給できます。
また、退職して傷病手当の受給期間が終了した後に、就労したいけど就職先が見つからない場合は失業保険への切り替えも可能です。
失業保険の申請方法や受給中の求職活動実績の作り方は以下の記事で解説しているので、興味がある人は参考にしてみてくださいね。
休職後に退職か復職か迷ったときの相談先
休職後に退職するか復職するか迷ったら、以下の公的機関やサービスを活用するのもおすすめです。
ハローワークで退職後の相談をする
ハローワークでは、若者や子育て世代、氷河期世代や高齢者世代など、様々な年齢層の方に向けた相談対応をおこなっています。
また、退職した後に申請できる手当や給付に関する相談もできますし、キャリアに関する相談や求人紹介を受けることも可能です。
そのため、休職後に復職をするべきか、退職をするべきか迷った時には、まずハローワークで相談をしてみると良いですよ。
自治体の相談窓口を利用する
休職や退職に関して、就労以外のことについて相談したい場合には、自治体の相談窓口を利用するのもおすすめですね。
特に、市役所では生活・子育て・福祉・健康など、幅広い相談ができますし、厚生労働省では相談窓口もあります。
自治体によって独自の相談窓口を用意しているケースもあるので、生活や心のケアに関する相談がしたい場合は活用してみると良いですよ。

自治体ではオンラインの面談やチャットで相談できるサービスを提供していることもあります。
そのため、もし対面での相談がしづらい場合はチャット相談から始めてみると良いですよ。
転職エージェントに相談する
休職後のキャリアや仕事のことについて悩んでいるのであれば、転職エージェントで相談するのもおすすめです。
転職エージェントでは、希望に合わせて様々な求人の紹介をしてくれますし、転職に関する支援も充実しています。
また、業界の転職に特化したキャリアアドバイザーがサポートしてくれるので、転職も視野に入れているなら活用してみると良いですよ。

転職エージェントを活用するなら、リクルートエージェント・マイナビエージェントがおすすめです。
いずれも、求職支援実績も豊富で手厚い転職支援が期待できるので、転職を考えているなら登録しておくと良いですよ。
求職活動実績を作るのにおすすめの転職エージェント
-
リクルートエージェント
業界No1!専門性を高められるセミナーもあり
転職を視野に入れるなら転職エージェントの活用がおすすめ
退職後に転職活動を検討している場合には、転職エージェントの活用がおすすめです。
また、転職エージェントは希望によっておすすめのサービスは変わるので、希望に合う転職サービスも紹介していきます。
転職エージェントのセミナーで求職活動実績を作る
退職後に失業保険の受給を検討している場合は、求職活動の実績づくりをする必要があります。
実績作りは求人応募や職業相談をする方法もありますが、最短で実績を作りたい場合には、リクルートエージェントの活用がおすすめです。
転職活動に役立つ実践的なセミナーやコンテンツが豊富に用意されているため、求職活動の実績を急いで作りたい人にもおすすめですよ。
求職活動実績を作るのにおすすめの転職エージェント
-
リクルートエージェント
業界No1!専門性を高められるセミナーもあり
休職・退職歴の伝え方についてエージェントに相談する
長期的に休職した場合は、履歴書や職務経歴書に記載するのが一般的なので、転職活動では休職や退職をした経緯を説明する必要があります。
休職理由や休職後の退職の理由が妥当・正当なものであれば問題ありませんが、場合によっては休職歴があると転職が不利になる可能性もあります。
そのため、転職する時には転職エージェントで休職・退職歴に関する書類への記載方法や面接での伝え方について相談すると良いですよ。
職務経歴に不安がある人が使いやすいエージェント
社会人経験が少ない中で体調を崩して休職した人や職務経歴に自信がない人は、第二新卒や正社員経験が少ない人向けのエージェントもおすすめです。
特に、UZUZはフリーターや社会人経験が少ない人でも手厚くサポートしてくれるため、転職に不安がある人は登録して相談してみると良いですよ。
また、ハタラクティブやマイナビジョブ20'sも未経験者の転職支援に強いので、経歴に自信がない人でも安心して利用できるサービスになっています。
正社員経験が少ない人におすすめエージェント
-
UZUZ
平均12時間以上の手厚いサポート!高卒・既卒・フリーターからの正社員転職に強み -
ハタラクティブ
大手企業が運営している老舗の転職エージェント!未経験から挑戦できる求人多数 -
マイナビジョブ20's
未経験OKの求人が7割以上!新卒支援実績No.1のマイナビによる20代向けエージェント
休職・退職に関するよくある質問(FAQ)
最後に、休職・退職に関するよくある質問を紹介します。
休職を始めるまでにどれくらいの期間がかかりますか?
一般的には数日から数週間程度で休職手続きは完了します。
基本的に会社との面談で休職期間や休職中の対応について決めてから、休職開始になると考えておくと良いですよ。
休職中に退職を勧められたらどうすればよいですか?
休職中に正当な理由なしに退職を迫られた場合には専門家への相談も必要です。
また、退職勧告は提案であり拒否することができるため、まずは状況を整理して冷静に対応すると良いですよ。
有給休暇と休職は併用できますか?
原則として休職期間中は有給休暇の消化はできません。
有給休暇は労働義務がある人の労働を免除する制度で、既に労働義務を免除されている休職者は対象外です。
休職中、会社に置いている私物はどうすればよいですか?
「自分で取りにいく」「郵送してもらう」「処分してもらう」のいずれかで対応するケースが多いですね。
まずは会社に連絡して、どのようにすればいいか指示を仰ぐことが大切です。
休職中は何をして過ごせばいいですか?
休職中は復職に向けて必要な行動を取ることに専念しましょう。
体調不良や傷病での休職では、休養・安静にした上で、医師の診断を元にリハビリしていくことが多いですね。
復職前にリハビリ出勤は可能ですか?
医師の指示があったり、会社に相談すればリハビリ出社は可能です。
ただし、副業やアルバイトは、会社の許可がないと就業規則違反になる可能性があるので注意が必要です。
休職中に転職活動をしても問題ないですか?
休職中に転職活動をしても問題はありません。
ただし、就業規則で制限されていたり、会社や応募先に知られるとトラブルになる可能性があるため注意が必要ですね。
休職・退職の経歴は履歴書や職務経歴書に書く必要がありますか?
休職したことを履歴書や職務経歴書に書く義務はありません。
嘘をついたり、虚偽の経歴を記載すると経歴詐称とみなされる可能性があるため注意が必要です。
休職には診断書が必要ですか?どこで取得できますか?
心身の不調や傷病による休職の場合には、診断書が必要になります。
診断書は診断・治療を受けた病院・クリニックで発行してもらえるので、発行をしてもらうと良いですよ。
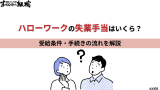
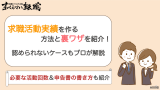
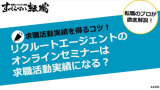
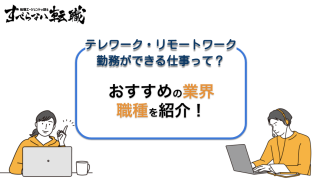
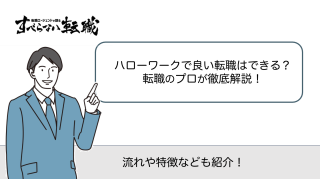
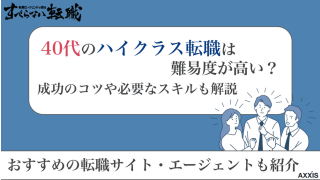
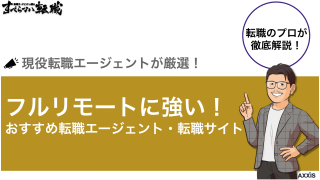
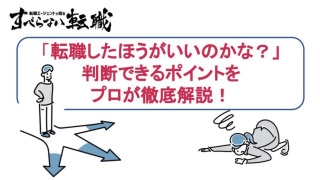
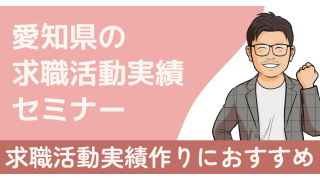
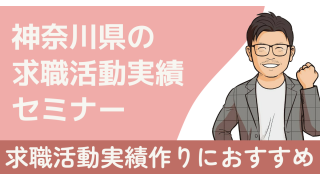
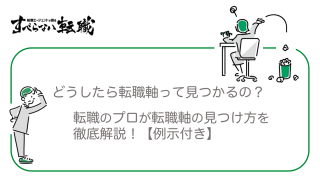
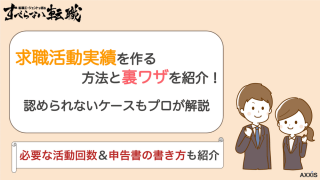
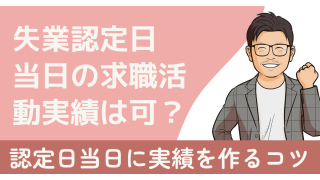







すでに療養が必要な状態であれば、退職せずに休職で治療に専念し、その後あらためて退職する選択もあります。
休職と退職のどちらかで迷った場合は、公的機関の窓口で相談してみるのもおすすめです。