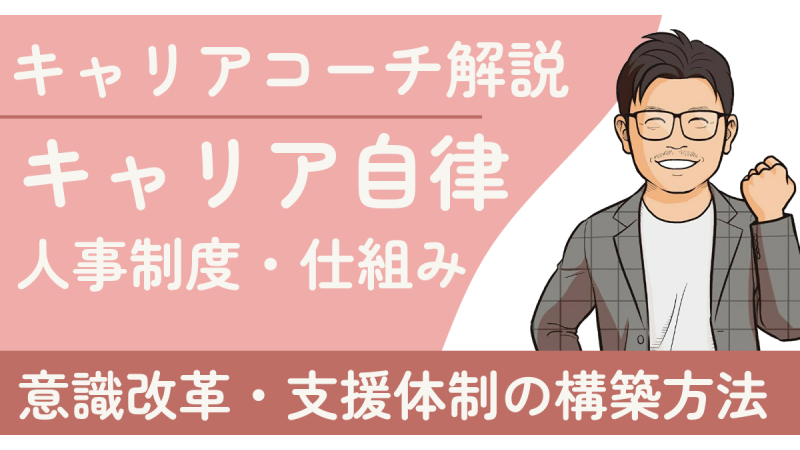
キャリア自律を進めたいのに社員が動かない理由とその処方箋
「社内にキャリア支援制度を導入したのに、ほとんど活用されていない」「キャリアは自分で考えてくださいと伝えても、リアクションが薄い」こうした声を、キャリア研修講師として企業を訪れるたびによく耳にします。
人的資本経営が注目されるなか、多くの企業が「キャリア自律」をキーワードに施策を講じています。しかし、現場で起きているのは「制度やツールを用意したのに、社員が動かない」という現実です。
なぜ、社員はキャリアに対して自律的に動けないのでしょうか?本記事では、その根本原因をひも解いたうえで、組織として今すぐできる具体的な処方箋を提示します。
すべらない転職が紹介するサービスの一部には広告を含んでおり、当サイトを経由してサービスへの申込みがあった場合には、各企業から支払いを受け取ることがあります。ただし、ユーザーの利益を第一に考え客観的な視点でサービスを評価しており、当サイト内のランキングや商品の評価に関して影響を及ぼすことはございません。
キャリア自律とは
キャリア自律とは、企業や上司に任せるのではなく、自分自身の価値観・強み・目標に基づいて、主体的にキャリアを設計・選択し、行動していくことを指します。
言い換えれば「どんな人生を歩みたいか」「どのように働きたいか」といった個人の価値観・目標に基づいて、自らの意思でキャリアの方向性を考え、選択し、実行していく力とも言えるでしょう。
これまでの日本型雇用では「会社の人事に任せていれば、自分のキャリアも自然に決まる」という考え方が一般的でした。配属・昇進・異動といった重要な意思決定は多くの場合、会社側に委ねられており、社員は『会社のレールに乗ること』がキャリア形成とされてきました。
しかし現代では、事業環境や職種の変化が激しく、同じ職場・同じスキルで一生働き続けることが難しい時代になっています。そのため、自身のキャリアを「誰かに委ねる」のではなく、「自分で考え、選び、磨いていく」姿勢が求められるのです。

なぜ今、キャリア自律が求められるのか?
以前の日本型雇用では「年功序列」「終身雇用」「会社に任せていれば出世できる」といった前提がありました。しかし今は、以下のような変化が起きています。
| 社会の変化 | キャリアへの影響 |
|---|---|
| 終身雇用の崩壊 | 会社が一生面倒を見てくれない |
| 働き方の多様化 | 正社員・副業・フリーランスなど選択肢が増えた |
| テクノロジー進化 | スキルの陳腐化が早くなり、学び直しが重要に |
こうした変化により、「キャリアは会社が決めるもの」から「キャリアは自分でつくるもの」へと価値観がシフトしています。
経営者・人事視点でのキャリア自律の意義
キャリア自律とは、単に転職や独立を目指すという意味ではありません。むしろ自社のなかで新たなスキルを獲得したり、新しい役割に挑戦したりすることも自律的キャリアの一形態です。
企業にとってキャリア自律を促すことは、以下のようなメリットにつながります。
キャリア自律の意義
退職の抑制:転職ではなく社内異動や挑戦でキャリアを築ける
人的資本の最大化:社員が自律的に学び、成果を出すサイクルが生まれる
組織力向上:自ら考え動ける人材が増えることで、変化に強いチームになる

誤解されがちですが「キャリア自律=個人任せ」ではありません。むしろ会社が支援しない限り、多くの社員はどう考えたらいいかわからず、動けなくなってしまいます。だからこそ、企業側は「キャリア自律を支援する仕組み」が必要なのです。
厚生労働省も提唱する「キャリア自律」の必要性
実はこの「キャリア自律」という概念は、個人や企業の取り組みにとどまらず、厚生労働省も政策レベルで重要性を提唱しています。
厚生労働省が進める「キャリア形成支援制度」や「セルフ・キャリアドック制度」では、社員が自らのキャリアを定期的に振り返り、主体的に将来を設計することを支援する仕組みが強調されています。
これらは、単に従業員の能力向上を目的とするのではなく、働く人一人ひとりが“キャリアの主人公”として自律的に歩む社会の実現を目指したものです。
また、人的資本経営やリスキリング推進の流れのなかでも、キャリア自律の概念は避けて通れません。政府としても、変化の激しい時代において「指示を待つ労働者」から「自ら考え動く労働者」への転換を促しており、企業にもその支援体制の整備が求められています。

キャリア自律とは個人の意識の問題であると同時に、企業・社会全体で育むべき共通価値でもあるのです。
キャリア自律を促しても社員が動かない3つの理由
キャリア自律を促す取り組みをしても、社員がなかなか動いてくれないことを課題に感じる会社が増えています。
その原因は、制度や意識だけの問題ではなく、組織風土や対話の在り方にもあります。ここでは、社員が動けない主な理由を3つに分けて解説します。
「キャリア=会社が考えるもの」という文化が根強い
社員に「キャリアは会社に任せておけばよい」という“待ち”の姿勢が根付いていることが、キャリア自律を阻む大きな要因です。
特に、大企業や日本型雇用の文化が色濃く残る組織では「上司に評価されることがキャリア」「自分の希望より、与えられた役割を全うすることが美徳」といった価値観が定着しています。
一概にそれが悪いとは言えませんが、こうした環境では『自ら考え、選び、行動する』という思考習慣が育ちにくく、主体的なキャリア形成が生まれにくい土壌となっています。
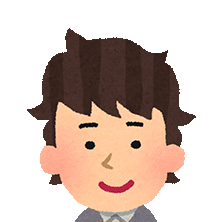
正直、うちは異動や昇進も会社次第だし、自分でキャリアを選ぶなんて考えたこともなかったです。会社や上司の方針に従って結果を出すことが良いキャリアだと信じていました。

「今の仕事を通じて何を学びたいか」「どんな働き方が自分らしいのか」「次に挑戦したい領域は何か」といった問いに向き合い、選択を重ねていく一連のプロセスこそが、キャリア自律の本質です。
制度はあるけれど、動機づけがない
多くの企業ではキャリア研修やリスキリング研修を整備していますが、機能していません。
なぜなら社員側に「なぜ今キャリアを考えるべきなのか」「どんなメリットがあるのか」が腹落ちしていないことがほとんどだからです。
また「制度を利用すると上司に辞めたいのではと誤解されるのでは」といった心理的ハードルがある場合もあります。制度が使える状態であることと、使いたくなる状態であることには、大きな差があるのです。
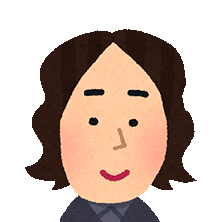
キャリア研修は受けましたが、これを受けたらどうなるかがイメージできなくて…。制度を使ってみたい気持ちはあっても、結局いつも忙しくて後回しになってしまいます。
上司がキャリア支援の担い手になっていない
キャリアの話は、本来上司と部下の信頼関係の中でこそ機能するものです。
しかし現場では、評価や日々の業務に追われ、部下のキャリア形成を支援する余裕やスキルが十分にあるとは言えません。
実際「うちの管理職はキャリア相談に乗れない」という声は少なくなく、結果として制度はあるが“対話がない”という状態に陥りやすくなります。
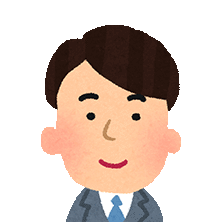
評価の話はよくあるけど『将来どうしたい?』って聞かれたことは一度もありません。こちらから言い出すのも気まずくて、結局キャリアの話はずっとできないままです。

キャリア自律を促すには「制度を整える」だけでなく、社員が『自分ごと』として考えられるような関わり方が不可欠です。
社員が動くキャリア自律支援の3つの視点
キャリア自律支援には社員が「自分のキャリアを考えたくなる」ような環境と関わり方が必要です。ここでは、社員の行動を引き出すためのキャリア自律支援の視点を3つ紹介します。
キャリア自律の定義とゴールを組織として明確にする
「キャリア自律=転職を促すこと」と誤解されることも多いですが、本来の意図は「社内でのキャリア選択肢を広げ、自ら意思決定できる状態をつくること」です。
まずは、組織としてキャリア自律をどう捉えているのか、その意図を言語化し、社内に伝える必要があります。経営メッセージとしてトップが語るだけでも、社員の認識は大きく変わります。
考えたくなる仕掛けを設計する
制度や仕組みを提供するだけでなく、「考えるきっかけ」を会社が能動的に作っていくことが大切です。
たとえば下記の様な取り組みがおすすめです。
- キャリア相談窓口や、キャリアコーチとの1on1
- 自己理解を深めるためのワークショップや社内イベント
社員自身が「これは自分のためだ」と感じられる設計が必要です。
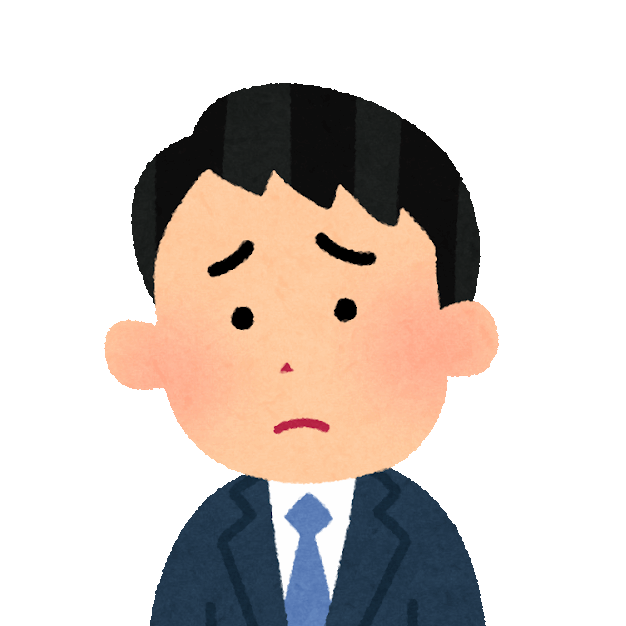
当社の従業員は3000名規模なので、相談数もかなりの数になりそうです。キャリア相談窓口を設置したいですが、正直なところ通常業務が忙しくて対応が難しいです。

当社は社外キャリアコーチ(外部キャリア相談サービス)を派遣し、キャリア相談窓口をサポートしています。興味がある企業様はお問い合わせページからご連絡ください。
管理職をキャリア支援のファシリテーターに変える
管理職には、部下の成長とキャリア形成を支援する支援者としての役割を明確に伝え、具体的な対話スキルを育成する必要があります。
たとえばキャリア面談のトレーニングを行い「部下が何を考えているのか」「将来どうなりたいのか」を聞き出す技術を磨くことで、日々の1on1やチーム運営にも好影響が出てきます。
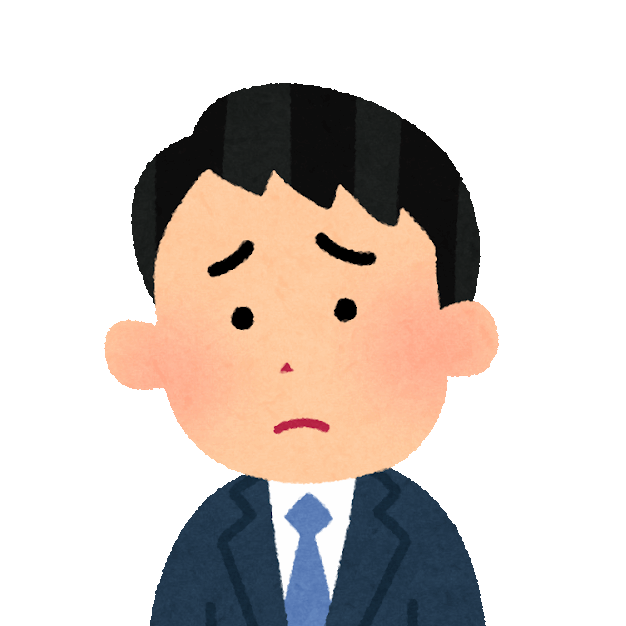
1on1を取り入れましたが若手からは「社内には相談しづらい」「利害関係がある上司には本音を言いにくい」といった声が出て大不評でした。結果的に形骸化してしまい、失敗しました…。

その問題は多くの大手企業に共通する問題です。そうした問題に対応するため、外部のキャリア相談サービスを福利厚生として導入する企業も増えています。匿名で相談できる仕組みは、社員にとって安心感を与え、キャリアを主体的に考える入口になります。気になる方は下記からお問い合わせください。
社外キャリアコーチ・外部相談サービスサービスへのお問い合わせはこちら
キャリア自律を実現する企業事例
キャリア自律を促すには、社員の「自分で選べる実感」を高めることが欠かせません。
その第一歩として効果的なのが、社内でのキャリア選択肢を制度として用意することです。ジョブローテーション、社内副業、社内FA制度はその代表例です。
40代向け「キャリア・ブレイク制度」で再挑戦を後押し
中堅社員がキャリアの方向性に迷った際に、一時的な社外研修や越境学習に参加できる制度を導入。
結果として動けないミドル層が再び学びに目覚め、組織内異動や社内新規事業への関与が活発になりました。
社内FA制度で「希望異動」を仕組み化
大手メーカーA社では、年に2回、自ら希望する部署へ異動を申し出られる「社内FA制度」を導入。
応募時には、キャリアコーチとの面談を経て応募理由やスキルの棚卸しを行う設計にしており、自己理解を深めたうえで意思決定ができるように工夫されています。
結果として「誰かに抜擢される」のではなく「自分で行きたい場所を選ぶ」という風土が育ちました。

当社が支援した事例です。当初はミスマッチが発生しており、活性化していなかった社内FA制度ですが、人事と連携し、各部署の求める人物像を整理・明確化。応募者側には面接前にキャリアコーチとの面談を実施してもらい志望動機を明確化。希望と配属のズレを解消しました。
社内副業制度で越境学習を後押し
B社では、社内の他部門の業務に一定時間だけ関われる「社内副業制度」を導入しています。
たとえばマーケティング部の社員が週に数時間、人事のプロジェクトにも関わるといった形式で、異なる視点やスキルを得る機会になっています。
社員は「キャリアの幅を広げること」が具体的な行動として実感できるようになりました。
まとめ:キャリア自律の鍵は制度ではなく「文化」
社員が動かないのは、意欲がないのではなく、動くきっかけがないだけです。制度を整えることに加え「キャリアについて話すことが当たり前な風土」をつくることで、社員は少しずつ自律的に動き始めます。
その第一歩として、今日、誰か一人の部下に「今後どうしていきたいか?」と声をかけてみてはいかがでしょうか。キャリアの火種は、静かな問いかけから生まれます。

私たちアクシス株式会社では、キャリア自立支援制度の導入から活性化までを一貫して支援しています。
他社では対応が難しい「現場巻き込み」や「制度の形骸化対策」まで含めて伴走支援いたします。興味がある企業様はお問い合わせページからご連絡ください。
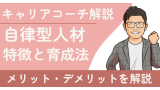
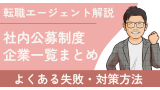
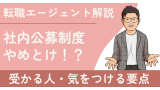
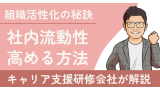
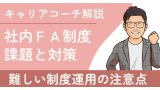
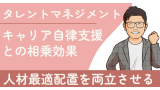
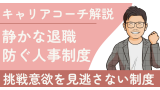
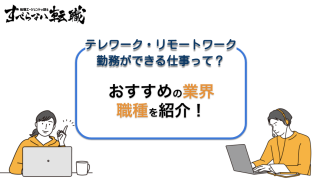
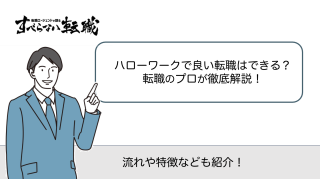
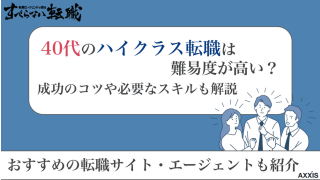
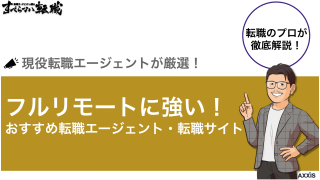
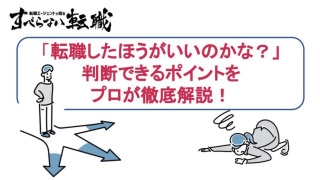
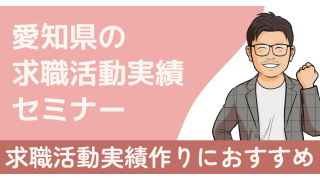
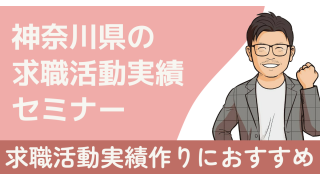
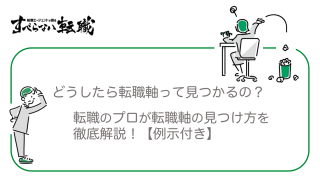
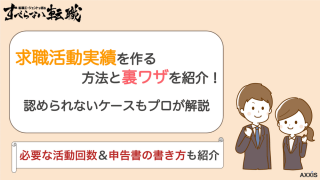
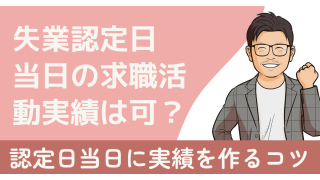







「今の仕事を通じて何を学びたいか」「どんな働き方が自分らしいのか」「次に挑戦したい領域は何か」といった問いに向き合い、選択を重ねていく一連のプロセスこそが、キャリア自律の本質です。