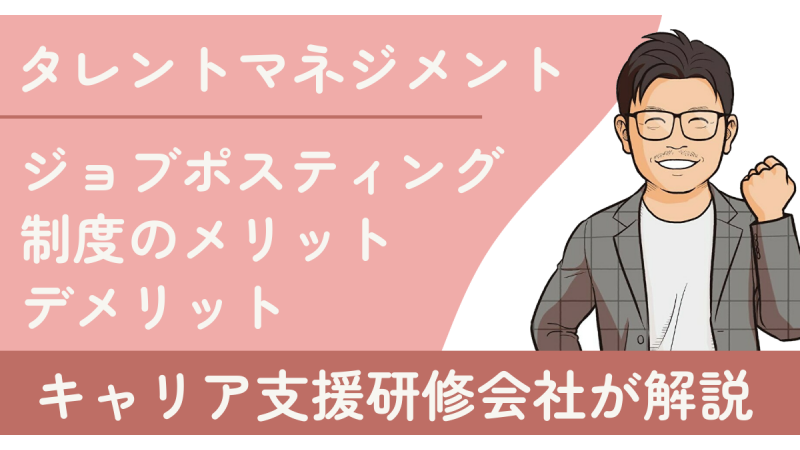
ジョブポスティング制度とは?社内公募との違いや導入メリット・成功事例を解説!
自社の人材をもっと活かしたい。そう考えたときに注目したいのが「ジョブポスティング制度」です。
欧米では一般的なこの制度は、社員が自ら希望して社内のポジションに応募できる仕組みであり、キャリア自律の支援や社内人材の有効活用を目的に、日本企業でも導入が進んでいます。
しかし、「社内公募制度」との違いが分からない、実際にどのようなメリットやデメリットがあるのか不安…という声も少なくありません。
本記事では、ジョブポスティング制度の基本から社内公募との違い、導入による効果、成功企業の事例、制度をうまく活用できない企業の特徴まで、わかりやすく解説します。
すべらない転職が紹介するサービスの一部には広告を含んでおり、当サイトを経由してサービスへの申込みがあった場合には、各企業から支払いを受け取ることがあります。ただし、ユーザーの利益を第一に考え客観的な視点でサービスを評価しており、当サイト内のランキングや商品の評価に関して影響を及ぼすことはございません。
ジョブポスティング制度とは
ジョブポスティング制度とは、企業内で発生した空きポジションや新たな役職に対して、社内の従業員に向けて募集をかける制度のことです。
社員が自らの意思で新たなポジションに応募することができるため、社内のキャリア形成を促進する仕組みとして注目されています。
この制度はもともと欧米の企業で一般的に導入されてきましたが、近年では日本企業でも徐々に導入が進んでいます。
特に人材の定着率向上や、従業員のエンゲージメント強化が課題となっている企業においては、ジョブポスティング制度が一つの有効な打ち手として機能しています。
ジョブポスティング制度の目的と背景
ジョブポスティング制度が注目される背景には、従業員のキャリアに対する主体性の高まりがあります。
終身雇用や年功序列といった日本型雇用慣行が揺らぐ中、企業は従業員のモチベーションを高め、優秀な人材を社内に留める工夫が求められています。
このような時代背景において、従業員が自らのキャリアを描き、自発的に新たなポジションに挑戦できるジョブポスティング制度は、多様な働き方を可能にする仕組みとして高く評価されています。
また、従業員の能力や希望を把握しやすくなることで、企業にとっても人材配置の最適化が図れるというメリットがあります。
さらに、企業の中には部署ごとの縦割り文化が強く、部門間の人材交流が進みにくいケースもあります。ジョブポスティング制度を通じて部門を超えたキャリアパスが生まれることで、組織の活性化、退職率防止にも繋がります。
社内公募制度との違いとは?
ジョブポスティング制度と混同されがちな制度に「社内公募制度」があります。
いずれも社内での人材募集という点では共通していますが、そのアプローチや運用方法には明確な違いがあります。
社内公募制度は、企業側が特定の職種やポジションに対して応募を促す制度です。一方でジョブポスティング制度は、発生したすべてのポジションを原則として社内に公開し、誰でも応募できる仕組みが基本です。
つまり、社内公募制度はやや選抜的であり、対象者が限定されることが多いのに対し、ジョブポスティング制度はよりオープンでフラットな制度と言えるでしょう。
また、社員の意思を尊重する仕組みであるため、キャリア自律を支援する文化の醸成にもつながります。

ジョブポスティング制度のメリット
ジョブポスティング制度のメリットをまとめました。
社員のモチベーション向上
自らの意思でキャリアパスを選択できるという感覚は、社員の自己決定感や達成感を高める要因となります。
特に若手社員にとっては、自分の将来が会社に委ねられるのではなく、自らの手で切り開けるという実感が働くモチベーションにつながります。
また、定期的にポジションが公開されることで、自分が目指すべきキャリア像を具体的に描きやすくなり、日々の業務にも目標意識を持って取り組めるようになります。
人材の流動性向上
組織の中で人材が固定化されると、マンネリ化や停滞が起こりやすくなります。
ジョブポスティング制度を導入することで、部署間の人材移動が活性化し、さまざまな知見や価値観が交差する環境が生まれます。
結果として、社内に新しい発想や革新が生まれやすくなり、イノベーションの土壌が育まれます。また、本人が異動に対して前向きである分、新しい部署での定着率や成果にも好影響を与えることが期待されます。
人材配置の最適化
社員が自分の強みや志向性を活かせるポジションに自ら応募することで、企業としても適材適所の配置が実現しやすくなります。
これにより、ミスマッチによる早期離職の防止や、業務効率の向上にもつながります。従来の人事異動のように一方的な配置ではなく、本人の意志を尊重したマッチングが行われるため、モチベーションの維持や成果へのコミットメントも高まりやすくなります。
採用コストの削減
外部から新たに人材を採用するには、求人広告費や面接・教育コストが発生します。
ジョブポスティング制度を通じて社内から適任者を充てることができれば、これらのコストを大幅に削減できます。
また、既に企業文化や業務の流れを理解している内部人材であれば、立ち上がりも早く、即戦力としての活躍が期待できるという点でも、経営的なメリットは非常に大きいです。
キャリアの透明性が向上する
社内でどのような職種やポジションが存在しているかが社員にとって見える化されることで「将来の選択肢が見えない」という不安が軽減されます。
情報がオープンになることで、自分がどのようなスキルや経験を積めばそのポジションに手が届くのかが明確になり、キャリア形成の意欲を高める効果があります。
特に中堅社員や女性社員の活躍推進といったダイバーシティ戦略とも親和性が高く、多様な人材の定着にも寄与します。
エンゲージメントの強化
会社が社員の挑戦を後押しする姿勢を見せることで、社員側も会社に対して「信頼されている」「成長を支援してもらえている」という感覚を持ちやすくなります。
このような相互信頼が高まることで、企業へのエンゲージメントが強化され、組織全体の一体感やコミットメントも向上します。
エンゲージメントの高い組織は離職率が低く、生産性も高いことがさまざまな研究からも明らかになっており、ジョブポスティング制度はその基盤づくりに貢献するといえるでしょう。
ジョブポスティング制度のデメリット
ジョブポスティング制度のデメリットをまとめました。
上司との軋轢
ジョブポスティング制度では、部下が上司に相談せずに異動に応募するケースもあるため、上司の理解や協力が得られないと職場内に摩擦が生まれることがあります。
特に評価期間中やチームで重要なプロジェクトを抱えている際に、突然部下が異動を希望することで、上司は「裏切られた」と感じることもあります。
このような心理的軋轢が放置されると、組織内の信頼関係が崩れ、職場の空気が悪化してしまう恐れがあります。制度導入時には、管理職にも制度の意義を丁寧に説明し、前向きな受け止め方を促す必要があります。
制度運用の負担
ジョブポスティング制度は、一見するとシンプルに見えますが、実際には募集ポジションの設計、選考基準の設定、応募者への通知、面談調整、フィードバックなど多くの業務プロセスを伴います。
人事部門だけでなく、各部門のマネージャーにも相応の工数が求められるため、制度導入時にリソース不足となりがちです。特に複数のポジションが同時に公募されると、調整の煩雑さが一気に増すため、スケジュール管理や進捗共有の仕組みづくりが重要です。

1万人規模の会社だと、ジョブポスティング制度をしっかり運用するのは担当2人程度では不十分です。こまかい部分までサポートするには外部メンバーを含めて運用するのが理想です。
応募が集中するポジションの偏り
どうしても人気の高い部署や業務内容には応募が殺到し、反対に不人気な部署にはほとんど手が挙がらない現象が起こりやすくなります。
その結果、特定部署への人材偏重が起きたり、空席が埋まらない部署の業務負担が増えるなど、全体最適の視点から見るとバランスが崩れてしまうリスクがあります。
この課題を解消するには、すべてのポジションを魅力的に見せる努力や、不人気ポジションへのインセンティブ制度導入も検討材料となります。
公平性への懸念
制度がオープンである一方で「結局は社内のコネや上司の意向で決まっているのではないか」といった不信感を持たれることがあります。
特に選考理由が明文化されていなかったり、選ばれた人物に対しての根拠が曖昧だと、制度自体の信頼性が損なわれます。
社員からの信頼を得るためには、応募から選考、内定に至るまでのプロセスを可視化し、透明性のある運営を徹底する必要があります。

公平な選考を心がけていても落とされた社員からは不公平だったという意見が生まれやすいです。ネガティブな噂は広まりやすいので注意して透明性ある運営を心がけましょう。
社員間の競争激化
ジョブポスティング制度は、社内における「見えない選考レース」を引き起こす場合があります。
同じポジションに複数の社員が応募した際、選考に漏れた側が落胆したり、選ばれた社員に対して嫉妬や敵対感情を抱くこともあります。
このような競争が健全なモチベーションにつながる場合もありますが、過度な競争は職場内の人間関係に悪影響を与える恐れもあるため、制度設計段階で「競争」ではなく「成長の機会」として捉えられるような文化醸成が求められます。
ジョブポスティング制度導入企業の事例紹介
ジョブポスティング制度を導入している企業は、富士通、中外製薬、ソフトバンク、パナソニック、くふうカンパニーなどの大手企業です。
中外製薬ではキャリア自律を支援する人事戦略の一環として、全社的にジョブポスティング制度を導入しています。制度導入によって、社員は自らの興味や志向に合ったキャリア形成がしやすくなり、実際に異動後の満足度も高いという結果が出ています。
ソフトバンクでは異業種・異職種へのチャレンジを推奨する文化が根付いており、ジョブポスティングを通じて新たなキャリアの扉を開く社員が多数存在します。

このような企業では、人事制度と経営戦略がしっかり連動しており、制度が形骸化せず、機能していることがわかります。
ジョブポスティング制度導入のポイントと注意点
ジョブポスティング制度を成功させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。
制度設計の透明性
募集条件や選考基準、選考プロセスを明確にし、社員の納得感を得ることが大切です。
どのようなスキルや経験が求められるのか、選考はどのように行われるのかといった情報を明文化することで、制度への信頼性が高まります。
特に、制度を初めて導入する企業では「誰が見ても公平」と感じられるプロセス設計が不可欠です。また、募集情報を社員全体に公平に伝えるための社内イントラネットや掲示板の整備も重要です。
経営陣のコミットメント
制度が単なる「飾り」にならないように、経営層が制度の目的と意義を明確に発信する必要があります。
トップメッセージとして「社員のキャリア自律を支援する文化をつくる」という意図を社内に周知することで、制度に対する本気度が伝わります。
経営陣が制度を推進する姿勢を見せることで、現場のマネージャーや社員にも制度の重要性が浸透しやすくなります。
管理職の意識改革
異動に対して消極的な管理職が存在すると、制度全体の活用が進まなくなるため、上司向けの研修や評価制度への連動も検討が必要です。
上司が部下の異動を妨げたり、評価に影響を与えるような言動をすると、社員は制度を利用しづらくなります。
管理職に対しては「部下のキャリア支援もマネジメントの一環である」という意識づけを徹底し、制度活用をポジティブに評価する仕組みを組み込むことが理想的です。
応募者へのフォロー体制
不採用となった社員に対しても、今後のキャリア形成に役立つフィードバックを提供し、モチベーションの維持を図ることが求められます。
単に「不合格」の通知を出すだけではなく「なぜ選ばれなかったのか」「どのようなスキルが足りなかったのか」「今後どのような成長が期待されるのか」といった建設的なフィードバックを行うことで、制度そのものへの信頼を高めることができます。

当社は社内異動制度の応募予定者に対してキャリアコーチを派遣し、1on1トレーニングを実施しています。応募理由の言語化や自己アピール作成のサポートをおこなっています。興味がある企業様はお問い合わせページからご連絡ください。
試験導入と段階的展開
いきなり全社導入するのではなく、まずは一部部署や職種におけるパイロット運用を通じて、制度の有効性や課題を検証することが有効です。
小さな成功事例を積み上げながら、徐々に対象範囲を広げていくことで、制度に対する社内の理解や納得感も得られやすくなります。
また、試験運用中に発生した課題をもとに制度を改善してから本格導入することで、運用リスクを最小限に抑えることができます。
評価制度との連動
ジョブポスティングによる異動がキャリアにどのように影響するのかを明確化し、社員の将来像と制度の関連性を可視化することが重要です。
例えば、異動後にどのような評価を受ける可能性があるのか、昇進・昇格にどのようにつながるのかといった点を明らかにすることで、社員は安心して制度を活用できるようになります。
制度単体で完結させず、全体的な人材育成・配置戦略と連動させる視点が必要です。
社員の適性やキャリア軸に沿った社内異動の最適化支援サービスへのお問い合わせはこちら
ジョブポスティング制度がうまくいかない企業の共通点
制度を導入したものの、うまく機能していない企業には共通点があります。
運用が属人的になっている
制度担当者の裁量に依存してしまい、基準が曖昧になると信頼性が損なわれます。
たとえば、どのポジションをジョブポスティングの対象とするかの判断が明文化されていなかったり、選考のプロセスや合否判断の根拠が担当者ごとに異なると、応募者側にとっては不透明に感じられ、不公平感が募る原因となります。
特に人事部門やマネジメント層との連携が不足している場合、制度全体が属人化し、継続的な改善や評価が行われないというリスクもあります。
こうした属人的な運用は、制度の形骸化や社内不信につながるため、ジョブポスティング制度の設計段階で、役割分担や評価基準の明確化、透明性のある運用体制の構築が求められます。
応募者がいない・偏る
制度上は誰でも応募可能であっても、実際には特定の部署やポジションにしか応募が集まらないと、制度としての効果は限定的になります。
例えば、人気部署に応募が集中し、その他の部署では応募者ゼロという事態が起きると、部署間のバランスが崩れるだけでなく、制度全体への信頼性も損なわれます。
また、そもそも制度の存在が十分に周知されていなかったり、募集情報が分かりにくい場所に掲載されている場合、社員が情報にアクセスできずに応募に至らないケースもあります。
公平な制度運用には、応募促進のための社内広報や、全社員への積極的な情報発信が不可欠です。
組織文化とのミスマッチ
ジョブポスティング制度は社員の主体性を前提とした仕組みであるため、トップダウン型の組織文化が強い企業では、社員が自発的に手を挙げること自体が難しくなります。
たとえば「異動を希望するのは現部署への不満と受け取られるのでは」といった心理的ハードルが存在する場合、制度の利用をためらう社員が増えます。
また、上司が異動を快く思わない風土があると、表向きは自由な制度であっても、実質的には使われない制度になってしまいます。
社員の心理的安全性を高め、異動希望をポジティブに受け止める企業文化を醸成することが、制度の定着には不可欠です。
選考プロセスが不明確
応募後の選考基準やフィードバック体制が不透明なままだと、応募者のモチベーションが下がり、制度の信頼性が低下します。
たとえば、何を基準に選考されたのかが分からず、不合格理由も明示されないと、「形式だけの制度だ」と感じる社員が増えるリスクがあります。
また、同じような経歴やスキルを持つ社員が選考で落ちたり受かったりする事例が重なると、制度の公正性にも疑問が生じます。
選考フローを文書化し、フィードバックを丁寧に行うことで、制度への信頼と透明性を確保することが求められます。
短期的な成果に偏重
ジョブポスティングによる異動後、短期間での業績や成果だけを評価基準にしてしまうと、社員は失敗を恐れて応募を控えるようになります。
特に、挑戦的なポジションや未経験領域への応募に対してプレッシャーが強すぎると、制度本来の目的であるキャリアの可能性拡大が実現しなくなります。
また、上司や周囲の期待に過度に応えようとすることで、心理的ストレスが増し、離職リスクが高まる可能性もあります。
制度設計の際は、中長期的な視点での成長支援を重視し、異動後すぐに結果を求めすぎない評価の仕組みが必要です。

これらの課題を克服するには、制度そのものの設計だけでなく、企業文化やマネジメントスタイルの見直しも並行して行う必要があります。特に、評価制度や管理職の育成方針との整合性をとることが、制度の定着において非常に重要です。
まとめ|ジョブポスティング制度で組織も社員も成長できる
ジョブポスティング制度は、社員のキャリア形成を支援しながら、企業全体の人材最適化を実現できる優れた制度です。
導入には一定の労力が必要ですが、制度が根付き、運用が軌道に乗れば、社内の活性化、イノベーション創出、定着率向上といった多くのメリットが期待できます。
これからの時代に求められるのは、「雇われる側」から「キャリアを自ら選ぶ側」への意識の変革です。ジョブポスティング制度は、その一歩を踏み出すための土台となる仕組みと言えるでしょう。
社員と組織がともに成長できる環境を整えるために、まずは小さな部署からでも導入を検討してみてはいかがでしょうか。
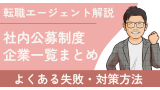
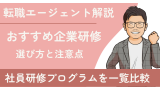
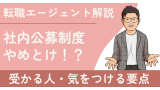
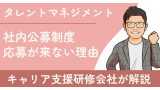
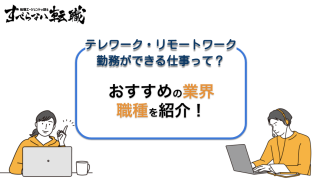
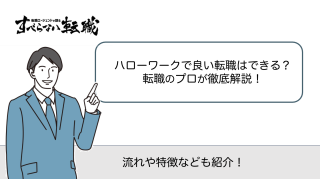
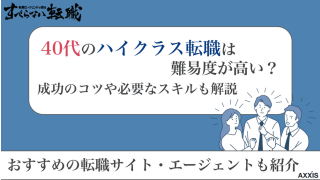
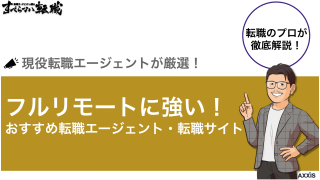
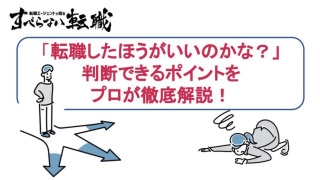
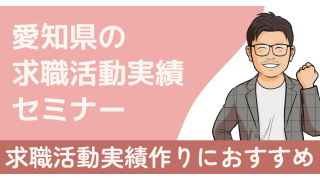
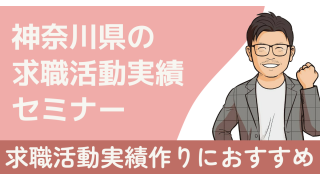
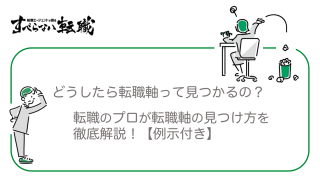
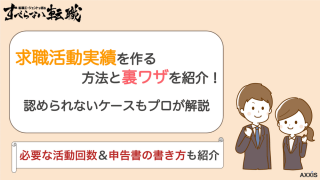
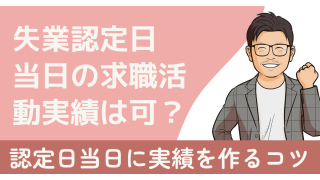







社内転職制度、社内FA制度、フリーエージェント制度など企業によって様々な名称があります。社内公募制度と同じ意味で使用している企業もあるので、必ずしも明確に区別されているわけではありません。