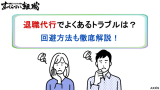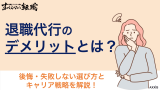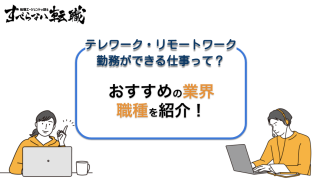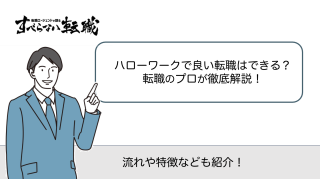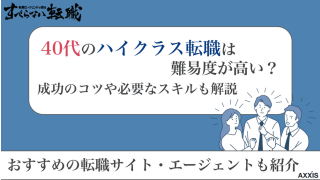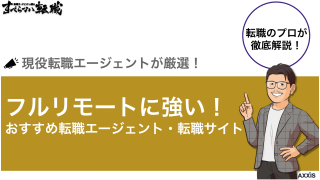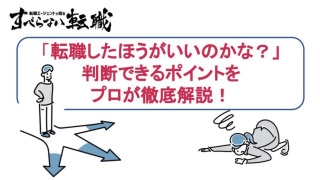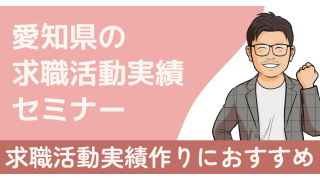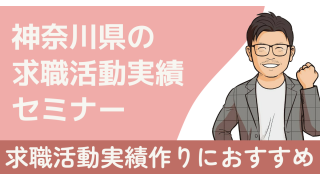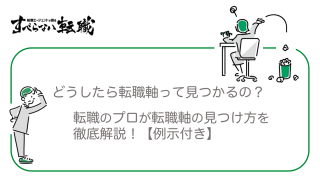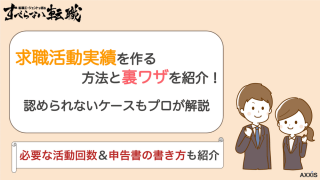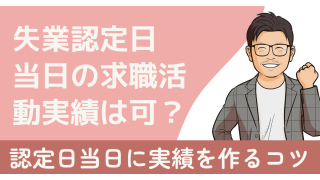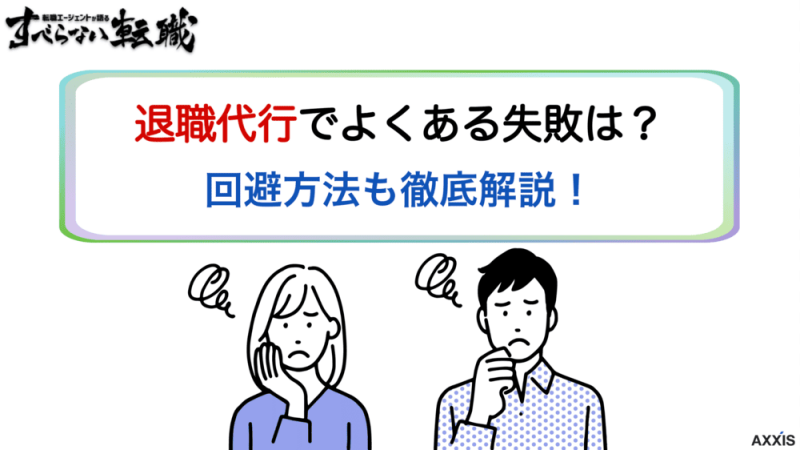
退職代行で失敗?よくある事例8つと対策を徹底解説
退職代行で失敗したくない人必見!よくある失敗事例とその原因、後悔しないための業者選びや対策を徹底解説します。
非弁行為のリスクや追加料金のトラブルなどをふせぎ、円満退職をするための完全ガイドです。
すべらない転職が紹介するサービスの一部には広告を含んでおり、当サイトを経由してサービスへの申込みがあった場合には、各企業から支払いを受け取ることがあります。ただし、ユーザーの利益を第一に考え客観的な視点でサービスを評価しており、当サイト内のランキングや商品の評価に関して影響を及ぼすことはございません。
退職代行のリアルな失敗パターン8選
退職代行を利用して失敗したケースが実際にあるのか気になりますよね。
これから紹介する8つの事例は、実際に起きた退職代行の失敗パターンです。
どんなリスクがあるのか、どう避ければいいのか、一緒に見ていきましょう。
これが現実!退職代行のよくある失敗事例
そもそも退職できなかった
退職代行のよくある失敗事例の1つ目は「そもそも退職できなかった」です。
かなり稀なケースですが、退職代行サービスを利用しても退職そのものができない場合はあります。とくに注意すべきなのは、非弁護士業者に依頼した場合です。彼らは法律の専門家ではないため、会社との交渉に法的な限界があるのです。
※以下、非弁護士業者を非弁業者と示す。
非弁業者は、退職届を代理で出したり、ただ退職の意思を伝えることしかできません。もし会社が「退職を認めない」「本人に直接確認したい」などとゴネてきた場合、法的な交渉ができないため、結局あなた自身が会社に顔を出さないといけなくなるケースもあります。
退職代行を利用する際は、弁護士が運営するサービスまたは弁護士と手を組んでいる業者を選ぶと良いです。弁護士は法的交渉が可能なため、会社側のむちゃぶりにも応えてくれますよ。

末永
ちょっとした小ワザなのですが、退職代行サービスを考えている人は、在職中に転職エージェントにも登録したほうが良いんです。
私が見るかぎり、在職中に次の転職先を決めず、退職後に「どうしよう…」と不安になってしまう人が多いイメージです。
転職エージェントは最後まで無料で使えます。新しい働き先を一緒に決めてくれるだけでなく、めんどくさい企業とのやりとりなど全て代わりにやってくれるので、ぜひ退職代行とあわせて登録してみてくださいね。
おすすめの大手総合型転職エージェント
-
doda
顧客満足度トップクラス!サポートが手厚い定番エージェント
即日では退職できなかった
退職代行のよくある失敗事例の2つ目は「即日では退職できなかった」です。
まず基本となるのが、民法627条1項になります。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法(明治二十九年法律第八十九号) 第六百二十七条 第一項
この「2週間」がポイントです。退職代行に依頼したその日から退職できるわけではなく、法律上は2週間の猶予期間(ゆうよきかん)があるのです。
「今日依頼して明日から会社に行かなくていい」と思っていた場合、法的に2週間は雇用関係が継続していることに気づかず、「うわ… 失敗した」と感じてしまうケースがあります。
ちなみに、有期雇用契約の場合、契約期間中の一方的な退職は原則としてできません。
たとえば、1年契約で1ヶ月経過した時点で退職したい場合、会社の同意がなければ契約違反となる可能性があります。インターネット上の「すぐに辞められます」などの広告には注意してくださいね。
就業規則で「退職届は1ヶ月前に提出すること」などと定められているケース
就業規則で「退職届は1ヶ月前に提出すること」などと定められている場合でも、法律的には民法の2週間が優先されます。
ただ、会社側が「規則違反だ!」とケチをつけてくることもあります。このようなトラブルがあると弁護士の交渉が必要になり、退職日が遅くなる可能性もありますね。
公務員が退職できるタイミング
会社から直接連絡が来てしまった
退職代行のよくある失敗事例の3つ目は「会社から直接連絡が来てしまった」です。
退職の意思を会社に伝えたあと、上司や人事部から「詳しい話を聞きたい」「一度話し合いましょう」といった内容で電話やメールが退職者本人に直接届くことがあります。
利用者の口コミ・失敗談

退職代行ガーディアンを利用して退職代行を行ったのですが、会社から自分にはもちろん親にも連絡があり、急に辞められては困るや、このままだと弁護士に言って訴えるだの言ってきました。
その旨をガーディアンに伝え、会社に本人や親に連絡をしないように警告をしていただきましたが、次の日家に会社から通知書が届き、無断欠勤が続いており、就業規則に違反しています。この書面をもって出勤していただくよう通知いたします。という内容でした。
ガーディアンに伝え警告含め抗議をするとのことでしたが会社はガーディアンの電話にはでずに無視をしています。
Yahoo!知恵袋他にも「退職代行を使ったのに、翌日から上司から毎日のように電話がかかってきて、精神的に追い詰められた」「退職代行が連絡した翌日、会社の同僚が自宅まで来て、直接話をしたいと言われた」などの事例も見受けられました。

末永
退職代行を頼むときは、会社からの連絡に対する対応方針を事前に相談しておくことが失敗をさけるポイントです。
会社から直接連絡が来た場合の対応を決めて、このようなトラブルに備えておくと良いですよ。
有給休暇を消化できなかった
退職代行のよくある失敗事例の4つ目は「有給休暇を消化できなかった」になります。
労働基準法では、労働者には年次有給休暇を取る権利が保障されていますが、実際には難しくなることもあります。
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 第三十九条 第五項
とくに退職直前の有給消化について、引き継ぎなどを理由に会社側がいやがることが多いです。
実際に、「退職代行を使ったら即日退職になり、残っていた20日分の有給が消化できなかった」こともあります。退職代行サービスが「有給消化も対応します」とうたっていても、最終的には会社側の判断次第となります。
労働基準法39条によると、有給休暇は金銭で買い取ることも法律上認められていないため、消化できなかった場合は権利が失われてしまいます。

末永
退職代行を利用する前に、自分の有給休暇の残日数を確認し、可能であれば退職届提出前に計画的に消化しておくことをおすすめします。
また、退職代行サービスを選ぶときは、有給消化についての交渉実績や対応方針を事前に確認しておけるとよいです。
退職後の書類が届かなかった
退職代行のよくある失敗事例の5つ目は「退職後の書類が届かない・手続きが進まない」です。
退職後には離職票や源泉徴収票などの書類が必要ですが、届かなかったり手続きが遅いケースがあります。
利用者の口コミ・失敗談
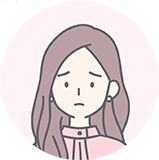
退職代行で先月末に退職届けを出して辞めました。
私と会社側は直接連絡を取らないという決まりがあるのですが、退職代行を実施後会社からの書類(離職票や健康保険資格喪失証明書など)が送られて来なく、本当に退職できたのか分かりません。
退職代行に確認したところ「書類等は2〜3週間程で届くのでお待ちください」と言われてはっきり退職した事は言われませんでした。サポート期間も実施後2週間なのでもう切れました。
Yahoo!知恵袋離職票は失業給付を受けるために必要社側に発行義務があり、雇用保険法施行規則の第7条でも「退職後10日以内に発行」するように義務づけられています。しかし、退職代行を利用して円満でない形で退職した場合、会社側があえて書類発行を遅らせることが考えられます。
その他の届かない書類について
源泉徴収票も遅れることがあります。確定申告や次の就職先への提出に必要な書類が届かず税金関連の手続きに支障をきたしてしまう人もいるようです。
また、健康保険被保険者証の返却や年金手帳の返却も滞ることがあり、健康保険の切り替えができず、医療機関での自己負担額が増えたなどの口コミもありました。
書類が届かない場合は、まず退職代行業者に相談し、対応してもらえるか確認します。
それでも解決しない場合は、労働基準監督署に相談すると良いです。離職票は法的に発行義務があるため、公的機関からの働きかけが助けになります。
労働基準監督署の場所は厚生労働省の公式サイトから確認してみてくださいね。

末永
大手転職エージェントdoda(デューダ)のオンラインセミナーは、登録して聞くだけで失業手当を継続して受け取るために必要な求職活動実績になります。
退職前に次の転職先が決まっていない人は、必ず登録しておくようにしましょう。
未払い(退職金・残業代が支払われなかった)
退職代行のよくある失敗事例の6つ目は「退職金・残業代が支払われなかった」になります。
退職金については、就業規則で「自己都合退職の場合は減額」と定められていることも多く、会社側が「退職代行を使った退職は自己都合退職として扱う」とプレッシャーをかけるケースも見られます。
これは、労働契約法によると、もし会社が元々の就業規則にないものを後出しした場合はすべて無効なので安心してくださいね。
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。
労働契約法(平成十九年法律第百二十八号) 第九条
ただ、退職金(退職手当)の支給は、法律で定められていません。
たとえば、企業が「勤続3ヶ月未満は退職金不支給」「自己都合退職は○割減」などと元々の就業規則に定めていれば、そのまま有効です。
未払金に対するまとめ
法令(労働契約法・労働基準法) > 就業規則
退職代行を使った後に就業規則を変更されても無効
退職金の支給自体は法律上の義務ではない
会社からの脅し(損害賠償・懲戒解雇)
退職代行のよくある失敗事例の7つ目は「会社からの脅し(損害賠償・懲戒解雇)」です。
退職に否定的な社風の会社では、突然の退職に対して感情的になってしまうことがあります。「会社に損害を与えた」「就業規則違反だ」などとゴネて、損害賠償を請求すると言ってくることも少なくありません。
また「退職届を出す前に退職代行を使ったのは就業規則違反だから懲戒解雇にする」と通告してくることもありますね。
しかし、こうした脅しのほとんどは法的根拠が薄いものです。
日本国憲法第22条1項によると、退職は職業選択の自由に基づく労働者の基本的な権利と書かれています。また、労働基準法5条は「強制労働の禁止」を記しており、社員が退職の意思を示した後に働かせ続けること自体が許されません。
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
日本国憲法(昭和二十一年憲法) 第二十二条 第一項
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 第五条
退職代行を利用すること自体は違法ではありません。
訴訟にまでなるケースは極めて稀で、多くは脅すためのハッタリにすぎません。
ただし、引継ぎを全くせずに退職したり、会社の機密情報を持ち出したりした場合は、本当に法的責任を問われる可能性があるので注意が必要です。
退職代行業者とのトラブル
退職代行のよくある失敗事例の8つ目は「退職代行業者とのトラブル」です。
退職代行サービスを利用する際、会社とのトラブルだけでなく、退職代行との間でトラブルが起きるシチュエーションもあります。
退職代行との失敗事例
連絡がつかなくなった
追加料金・キャンセル代がかかった
広告の内容や事前説明と違った
最も多い退職代行業社との失敗例は「連絡がつかなくなった」です。
まず、最初に知っておいてほしいのは、退職代行サービスの多くが前払いであることです。料金を支払ったあとに担当者と連絡が取れなくなり、退職手続きの進捗状況がわからないまま不安な日々を過ごした人もいますね。
利用者の口コミ・失敗談
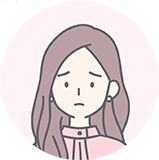
今、、私next退職代行サービスを利用しています。
まだ代行の途中です。昨日連絡をしてもらい、店長が不在だった為、店長の次の責任者の方に連絡してもらい、店長の確認が必要で先方から弊社に連絡がくるまでお待ちください。とのことでした。
私next代行サービスの担当者さんにLINEでやり取りをしているんですが今までだったらすぐに連絡が来ていたんですが…..
私が連絡しても既読がついて返事が返ってきません。凄く不安になるんですが、詐欺とかじゃないですよね?
Yahoo!知恵袋次に「追加料金・キャンセル代がかかった」などの失敗例があります。
たとえば「未払い賃金は支払わない」「退職日は会社が決める」などと言われ、代行業者が会社と交渉する必要が生じたときに起こりやすいですね。
基本パッケージには退職届を出すところまでしか含まれていないサービスもあります。交渉や弁護士対応に追加料金がかかるのか、キャンセルポリシーはどうなっているかは必ず事前に確認しておきましょう。
利用者の口コミ・失敗談

私は先程、依頼を相談の上指定された金額をデビットカードの引き落としで入金しました。
その後、誤りがあり 貴方の雇用形態上、追加で10,000円かかるから指定口座に振込んでください。と言われました。
キャンセルの場合も同様の金額がかかると言われたので、明日の朝 振り込みますと言ってしまいましたが、振り込んだ後もまだ振り込まされる可能性(ちゃんと振り込めてない等)はありますでしょうか?
相手側に都合の悪い質問にはきちんと返答がなく、クチコミもあまり良くない為、不安な状態です。焦ってしまい、冷静さに欠けた行動を取ってしまった自分に落ち度があるので指定の合計金額は支払うつもりではいますが、これ以上請求されないかが心配です。またこのような誤解が生まれにくくなればと思い投稿いたしました。
Yahoo!知恵袋また「広告の内容や事前説明と違った」もよくある失敗例です。
ウェブサイトでは「24時間対応」「即日退職可能」と書いていても、実際には平日のみの対応だったり、即日対応に追加料金が必要だったりするケースがあります。
さらに「すべて対応します」と言われたのに、実際には退職の意思を伝えるだけで終わり、その後の手続きは自分でしなければならなかったなどのケースもあります。こちらもマストで確認してくださいね。
利用者の口コミ・失敗談
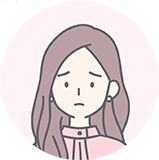
退職代行を使いましたが後悔しています。
詳しい経緯が言えませんが退職代行に依頼して2週間以上経ちましたが退職代行を通して職場から"引き継ぎ"という項目で毎日連絡が来ます。私じゃなくても答えられるものばかりで正直嫌がらせにも捉えられる量にも関わらず、退職代行からは損害賠償をひきあいに出され引き継ぎには答えて下さいの一点張りです(フォーゲル)。
こういった事が考えられるからこそ退職代行を使ったはずなのに、自分で辞めるよりも逆に面倒な事になってしまいました。
Yahoo!知恵袋退職代行が失敗する原因をズバリ解説
退職代行サービスを利用したものの、思ったような結果にならず失敗と感じてしまうことも多いようです。
なぜ失敗してしまうのか、前の目次で紹介した事例をもとにその原因を詳しく見ていきましょう。
なぜ?失敗の原因をパターン別に解説
そもそも退職できない理由
退職代行を使って、そもそも退職できなかった理由は業者選びの失敗といえます。
費用の安さだけで選んでしまい、実は法的な対応ができない「伝書鳩」タイプの業者だったケースですね。会社側が「退職を認めない」といえば、代行業者にはそれを覆す法的な権限が必要なのです。
法律上は、民法627条1項により労働者には退職の自由が保障されていますが、会社側が「規則違反だ」「迷惑だ」と強気で言ってきた場合、一般の退職代行業者では対応しきれないことがあります。
退職できないリスクを減らすためには、退職代行を依頼する前に自社の就業規則を確認し、退職に関する規定を把握しておくことが重要ですよ。
即日では退職できない理由
退職代行を使って、即日では退職できなかった理由は会社との退職日の合意が必要だからです。
退職代行が会社に「本日付で退職します」と伝えたとしても、会社が即日退職を了承しなければ、法的には退職日とはなりません。(※定めのない雇用契約の場合)
ただ、下の3つケースであれば即日退職も成功しやすいので目を通してみてください。
「即日退職」が成立する3つのロジック
会社が同意してくれる
有給休暇が2週間以上残っている
民法628条1項"やむを得ない事由"を主張する
まず、会社が当日付退職を承諾するパターンで、合意が得られればその瞬間に雇用契約が終了します。
また、年次有給休暇を2週間以上残したまま退職を申し出て、残りの日数をすべて消化にあてて退職日まで出社しない方法があります。法律上の退職日は2週間後でも、体感的には即日で終わりにする戦略ですね。
さらに、民法628条1項のやむを得ない事由を立てて「すぐに退職したい」と伝える方法もあります。賃金未払い・パワハラ・セクハラ・医師の就労不可診断など証拠集めができればその日で契約が切れますよ。
会社から直接連絡が来る理由
退職代行を使ったのに、会社から直接連絡が来る理由は退職代行業者の対応の不十分さにあります。
退職代行サービスは基本的に、今後の連絡は全て代行業者を通してほしいと会社側に伝えてくれます。しかし、対応が雑な業者などが「うっかりミスで伝えていなかった」などの失敗事例も見受けられます。
民法第99条の『代理行為の要件及び効果』によると、退職代行が本人から正式に委任を受け、会社へその旨を書面で通知した時点で、原則として会社は本人ではなく代理人を窓口にしなければなりません。
1.代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2.前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
民法(明治二十九年法律第八十九号) 第九十九条
そのため、退職代行を介した連絡経路を会社が無視して、本人に直接連絡がいってしまうことは違法性が高いといえます。
ちなみに、弁護士資格を持たない一般の退職代行業者でも「代理人としての委任通知」は民法上有効です。ただ 非弁行為(弁護士法72条)にふれる交渉までやってもらうと逆に違法になるおそれがあります。

末永
せっかく退職代行を使ったのに会社から直接連絡が来てしまうとショックですよね。「会社からの連絡を遮断できるか?」は事前に質問しておくと良いですよ。
また、まんがいち会社から連絡が来た場合の対処法「無視する、代行業者に転送する」なども事前にすり合わせておくとスムーズです。
豆知識ですが、退職代行サービスを使う前に転職エージェントに登録しておくことをおすすめします。
転職エージェントは転職だけでなく退職のプロでもあります。失敗なく退職している人は、みなさん事前に転職エージェントに登録してから退職代行サービスを使っていますね。
おすすめの大手総合型転職エージェント
-
doda
顧客満足度トップクラス!サポートが手厚い定番エージェント
有給休暇が消化できない理由
退職代行を利用しても有給休暇が消化できなかった場合、依頼文に年休取得の日付が盛り込まれていない可能性が高いです。
依頼文とは・・・
依頼文とは、退職代行業者が会社あてに送る通知書の中で、労働者の意思(退職日・年休取得日など)を伝える文書をさします。
退職届だけでなく、別紙の「年次有給休暇取得願」が必要になってきます。

末永
退職届は「退職の意思表示」を目的とする書面であり、年休取得の意思(時季指定)が書かれていなければ会社は付与義務を負いません。
代行業者に依頼するときは退職届とは別に、年休取得日を指定した通知を盛り込むように伝えると良いです。
労働基準法第39条5項によると、年次有給休暇は労働者が時季を指定して請求しない限り効力がありません。
退職代行を使っても、その依頼文に年休取得の具体的日付が盛り込まれていなければ会社は付与義務を負わず、結果的に未消化のまま退職となってしまいます。
ただ、請求さえしていれば会社は退職日以降へ時季変更できないため取得を拒めません。
すでに退職してしまった場合でも「退職日までの未消化分」を賃金請求(年休相当額の未払賃金)として通せる余地があるので、内容証明や労働基準監督署のあっせんを借りて回収すべきですよ。
退職後の書類が届かない理由
退職代行を使って退職した後、退職後の書類が届かない理由は会社が法定書類の発行・発送をわざと後回しにしているか宛先・手続きの確認が取れていないためです。
退職代行を使った場合、会社としては「気持ちのよくない辞め方」と感じることもあり、書類発行を後回しにされるケースですね。これは明らかな嫌がらせといえるかもしれませんが、単に人事担当者が忙しいという理由の場合もあります。
ただ、退職後に会社が交付すべき書類(離職票や源泉徴収票など)には期限や提出義務が明記されています。退職代行を介していても会社が期限を守らないのは違法なので退職代行にしっかりと主張しましょう。
その他|退職後に必要な書類
- 離職票(雇用保険被保険者離職票‐1・離職票‐2)
- 雇用保険被保険者証(在職中に預けていた場合)
- 源泉徴収票
- 社会保険資格喪失証明書
- 健康保険被保険者資格喪失証明書(協会けんぽ等)
- 厚生年金保険資格取得・喪失連絡票(事業所控除分の写しなど)
- 住民税特別徴収に関する通知書
- 退職金(または企業退職年金)支給決定通知書・支払明細
- 企業年金/確定拠出年金(DC)加入者資格喪失通知書※該当者
- 財形貯蓄残高通知書・解約書類※財形加入者のみ
- 社員持株会 持分払出通知書※加入者のみ
- 会社貸与品返却確認書・最終清算書(私物ロッカー確認等)
- 退職証明書※請求した場合
また、宛先・手続きの確認が取れていないのは、退職代行の通知書に抜けもれがある可能性が高いです。この場合「どこに・何を・どう送ればいいか」会社側が確定できていない状態になっています。
退職後の書類が届かない場合は、退職代行に下の情報を共有したうえで相談してみてくださいね。それでも届かない場合は行政ルートを使うしかありません。
退職代行に共有するデータ
- 現住所・郵便番号・氏名(フリガナ)
- 送付希望書類のリスト(離職票、源泉徴収票、資格喪失証明書 など)
- 希望する送付方法(簡易書留・レターパック など)
- 希望する連絡先(メール・携帯)
書類別の対応方法
離職票・雇用保険関係:住所を管轄するハローワークへ「事業主が発行しない」と相談
源泉徴収票:税務署の源泉所得税担当に「交付義務違反」として連絡
その他書類・賃金:労働基準監督署へ申告
退職金・残業代が支払われない理由
退職代行を利用したあとに退職金・残業代が支払われない理由は、退職代行を理由に会社が本来の支払い手続きを後回しにしているためです。
退職代行の利用自体を理由に退職金や残業代を払わないことは、法的根拠がなく違法といえます。内容証明で請求し、応じなければ労基署申告または訴訟・労働審判で回収するのが適切な対応ですよ。
ちなみに残業代は、時効内であれば過去分までまとめて請求できます。時効かどうかは下の表を参考にしてみてくださいね。
| 該当する残業代 | 時効期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 2020年4月1日以降に支払期日を迎えた分 | 3年 | 労働基準法115条 |
| 2020年3月31日以前に支払期日を迎えた分 | 2年 | 同条の旧規定 |
損害賠償・懲戒解雇などと脅される理由
退職代行を利用したら損害賠償・懲戒解雇などと脅される理由は単純に引き止めたいからです。
とくに中小企業など人手不足の職場では、突然の退職でダメージをくらうこともあるでしょう。また、退職代行を使われたことでプライドが潰れてしまう上司もいるはずです。
そこで「簡単には辞めさせない」と心理的な圧力をかける作戦で、損害賠償や懲戒解雇を持ち出しているのです。

末永
結論からいうと、このような脅しは法的根拠が弱いです。内容証明で退職意思と代理窓口を再通知し、応じなければ労基署申告や労働審判の力を借りれば問題ありません。
損害賠償は「従業員に故意・重過失があり、かつ会社が具体的損害額を立証」できて初めて認められます。引継ぎ不足だけで賠償が通ったシナリオはまずありません。
また、労働契約法15条によると、懲戒解雇は「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必須となります。退職代行の利用自体を理由にするのは権利濫用で無効なので安心してくださいね。
退職代行業者とトラブルが起こる理由
退職代行業者とトラブルが起こる理由は、退職者が期待するサポートと業者が法的に対応できる範囲に食い違いが生じるためです。
たとえば「会社と交渉してほしい」「未払い残業代も請求してほしい」といった期待を持って一般企業が運営する退職代行サービスに依頼しても、法的に交渉ができません。
こういったギャップに退職者は失敗したと感じやすいです。これは、退職者が「退職に関することなら何でもやってくれる」と期待する一方で、サービス側は「法的に許された範囲の連絡代行のみを行う」という認識のミスマッチですね。

末永
退職代行サービスによっては、誇大広告・宣伝も、退職者の期待値を不必要に高め、失敗と感じてしまう原因となります。
「100%退職可能」「会社と完全に縁が切れる」といった断定的なキャッチフレーズや、「どんな状況でも対応可能」など個別の状況による文言はあまり間に受けすぎないように注意です。
ここからは、これまで紹介してきた失敗談やトラブル事例をふまえて後悔しない選び方をレクチャーしていきます。失敗したくない人は必見ですよ。
失敗しない退職代行業者の4つの選び方
退職代行サービスを利用するとき、失敗しないためには事前の準備と正しい知識のインプットが欠かせません。
これから退職代行を使おうと考えている人が後悔しないよう、業者の選び方と対策について詳しく解説していきますね。
退職代行の失敗をふせぐ4つの鉄則
運営元を確認する
退職代行サービスを選ぶときに、まず確認すべきなのが「誰が運営しているのか」です。運営元によって提供できるサービスの範囲や法的な安心感が大きく変わってくるからですね。
退職代行サービスの運営元は主に3つのタイプに分かれています。
| 運営元 | 民間企業 | 労働組合 (ユニオン連携) |
弁護士法人 |
|---|---|---|---|
| 特徴 |
・退職意思の伝達、会社との仲介のみに対応 ・退職日や有休消化などに関する交渉、裁判や訴訟の対応はできない |
・退職意思の伝達に加え退職日の調整や有休消化に関する交渉が可能 ・裁判や訴訟への対応は不可能 |
・退職意思の伝達から法的な交渉、裁判や訴訟まで総合的なサポート |
1つ目は「民間企業」です。サービスの数がもっとも多くお財布にやさしい料金なのが特徴です。ただ、法的な交渉権限がなく、会社との交渉はできません。あくまで退職の意思を伝えるだけのサービスとなります。
2つ目は「労働組合」が運営するタイプになります。労働組合には団体交渉権があり、会社側と交渉することが可能です。未払い残業代の請求や退職金の交渉など、よりふみ込んだサポートを受けられるのが強みですね。
3つ目は「弁護士法人」が運営するサービスです。法律の専門家が対応するため、安心感があります。会社からの脅しやトラブルがあっても法的な措置ができます。そのぶん、料金は他の2つに比べて高めに設定されていることが多いです。
運営元の選び方まとめ
単純に会社を辞めたいだけなら民間企業のサービスで十分
退職日、退職金のあつかいなど労働条件について会社と交渉したいなら労働組合
法的なリスクを最小限におさえたい場合は、弁護士法人がおすすめ
料金体系を確認する
退職代行サービスを選ぶとき、料金相場を確認したり妥当な料金設定かどうかを見極めるのがポイントです。
退職代行の料金相場は、民間企業が運営しているサービスであれば2〜3万円、労働組合が運営する退職代行だと2.5万円〜4万円ほどになります。また、弁護士が運営する退職代行だと5〜10万円程度ですね。
このギャップは対応できることの違いによるもので、弁護士以外の業者は会社との交渉ができないため料金が安くなっています。
| 運営元 | 民間企業 | 労働組合 (ユニオン連携) |
弁護士法人 |
|---|---|---|---|
| 料金相場 | 2万円〜3万円 | 2.5万円〜4万円 | 5万円〜10万円 |
| 追加料金 | オプションによる | 組合費 (2,000円程度) |
成功報酬 (回収額の20%程度) |
| 主な内訳 | 交渉ができないため人件費も低め | 組合費を徴収し労組活動原資を確保 | 弁護士ならではの専門対応や保険加入、事務所運営のコスト |
民間企業のサービスを使う場合、確認してほしいのはオプションです。基本パッケージは安く見えても、自分がしてほしいサポートをつけて請求金額が増えていることもあります。
よくつくオプションと追加料金のめやす
| オプション内容 | 追加料金の相場 | 具体例 |
|---|---|---|
| 即日対応 | 無料〜20,000円 | 退職代行RETIRE:深夜連絡対応料金 2万円 |
| 書類回収・転送代行 | 5,000〜1万円 | 退職代行EXIT:書類再請求サポート 5,500円 退職代行Jobs:書類取得サポート 8,000円 |
| 退職届・内容証明の作成代行 | 3,000〜7,000円 | ニコイチ:内容証明代行 6,600円 |
| 弁護士紹介 | 3万円+成功報酬 | EXIT:弁護士紹介パック 33,000円+回収額20% |
| 対面・オンライン相談 | 1時間 5,000円〜1万円 | モームリ:15分まで無料(以降1時間8,000円) |
また、おおはばに相場より安いサービスにも要注意です。一概にはいえませんが、1万円以下など明らかに安い金額だと、サービスの質が低かったり個人情報を別の目的で利用したりするリスクがあります。
料金体系を見るときは、下の3つをチェックしてみてくださいね。
料金のウォッチポイント
最初に提示された金額以外の請求はあるか
料金に含まれるサービスの範囲が明確か
キャンセル料の有無や返金ポリシーはどうなっているか
サービス内容・対応範囲を確認する
退職代行業者を選ぶ際の、サービス内容と対応範囲を確認することも大切です。サービスの中身をしっかり理解しておかなければ、後々「こんなはずじゃなかった」という失敗になりかねません。
まず確認すべきはベースとなる対応範囲です。多くの退職代行サービスでは、会社への退職意思の伝達、退職日の調整、会社との連絡代行などが含まれています。
「退職の意思伝達のみ」で終わるサービスもあれば、「退職後の書類のやり取りまで」対応するところもあります。自分が必要としているサポート内容がカバーされているか、事前に確認しておくと良いですね。

末永
アフターフォローがあるかも確認しておくと安心です。
退職はゴールではなく新たなスタートの始まりですから、その後のサポートも視野に入れて選ぶことをおすすめします。
ちなみに、退職代行サービスは対面やオンラインでの相談にオプション料金がかかることが多いです。転職エージェントであれば退職相談から入社が決まるまですべて無料で利用できるので、いっしょに登録しておくと良いですよ。
おすすめの大手総合型転職エージェント
-
doda
顧客満足度トップクラス!サポートが手厚い定番エージェント
実績や評判・口コミを確認する
退職代行業者を決めるまえに参考にしておきたいのが、サービスの評判や口コミです。せっかく勇気を出してお願いしたのに、ずさんな対応をされてしまい退職がスムーズに進まなかったなどの失敗があるからですね。
少なくとも運営歴と対応実績数は見ておきたいです。退職代行業界は比較的新しいマーケットですが、3年以上の運営実績がある業者は一定の信頼性があるといえます。
また、対応実績が1,000件を超えているサービスであれば、ほとんどのケースバイケースに対応できる可能性が高いですね。

末永
評判や口コミはGoogleの口コミやSNSが参考になります。
良い評判・悪い評判どちらも見たうえで「自分の場合でもいける?」と気になる口コミをいくつかピックアップしておくとよいです。
退職代行を利用する前に、不安なことはすべてスッキリさせてから支払いをすませてくださいね。
退職代行の失敗は転職エージェントの併用で回避
退職代行の失敗リスクを減らすには退職代行サービスを使う前に転職エージェントに登録するのがポイントです。
「え、退職代行の話なのに、転職エージェント?」と思われたかもしれません。
実はこれ、知る人ぞ知る、少しだけずるい使い方なのです。あまり多くの人は気づいていません。

末永
退職代行は依頼前のお悩み相談に、1時間あたり数千円~1万円といった費用がかかるサービスが多いです。それに対して、転職エージェントの相談は完全に無料です。
また、転職エージェントは転職のプロであるとともに、退職に関する悩みや、その後のキャリアについても一緒に考えてくれます。
まとめると、お金のかかる退職代行サービスを使う前に相談相手を見つけ、利用前の不安をなくすことが、退職代行を成功させるコツですね。
大手や人気企業の求人を多数保有!大手エージェント
大手エージェントには、全業界・職種の求人が集まっています。さらに、大手企業や人気企業の求人を独占で持っていることも。
幅広い選択肢の中から求人を提案してもらいたい、大手企業や人気企業への転職を検討しているという方は登録しておきましょう。
CMでおなじみ!顧客満足度トップクラス!
豊富な求人数に加えて、専任アドバイザーの手厚いサポートが強み
おすすめポイント
- リクルートと並ぶ、実績豊富な国内最大級の転職エージェント
- 20万件以上(2023年3月時点、非公開求人を含む)の求人から、厳選して紹介をしてくれる数少ないエージェント
- リクルートが保有していない有名企業の求人に出会える可能性が高い
退職代行の失敗についてよくある質問
退職代行の失敗についてよくある質問をまとめました。
退職代行の成功率は?
退職代行の成功率は、法制上ほぼ100%です。
民法627条の「2週間ルール」と労働基準法5条「強制労働の禁止」があるため、期間の定めのない正社員の場合は退職の意思を会社に届ければ、2週間経過で雇用契約は終了します。
ちなみに、成功の定義が「退職できる」であればほぼ100%成功といえますが、すぐに退職できなかったり、会社ともめてたりして失敗と感じる人もいます。
退職代行で起こりうるトラブルは?
退職代行で起こりうるトラブルは、勤めている会社とのトラブルと、退職代行業者とのトラブルがあります。
会社とのトラブルだと「会社から直接連絡が来てしまう」などが一例です。退職代行とのトラブルであれば「業者と連絡が取れなくなる」などのトラブルですね。
退職代行でよくあるトラブル事例については下の記事でも解説しています。あわせてごらんくださいね。
退職代行でクビになる?
労働契約法16条によると、退職代行を利用してクビになることは原則ありません。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
労働契約法 第十六条
クビ(懲戒解雇)になるのは横領・背任・無断長期欠勤など重大な義務違反があるパターンに限られます。退職代行の利用をベースに懲戒解雇になった事例はありません。
会社は退職代行を拒否できますか?
民法99条1項によると、会社は退職代行を拒否できません。
1.代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2.前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
民法(明治二十九年法律第八十九号) 第九十九条
もし会社が「本人から直接聞いていない」といってきても、代理通知がとどけば法的には拒否できません。
退職代行を使うと後悔する?
退職代行を使って後悔している人は、残念ながらいるのが現実です。
下の記事では、退職代行で後悔する理由や後悔しないためのポイントについて解説しているので読んでみてくださいね。
退職代行を使うデメリットは?
退職代行のデメリットは、費用・法的限界・悪質業者のリスクです。金銭や法的、業者選びの問題が生じうるからですね。
下の記事では、退職代行を使うデメリットについて解説しているのであわせて読んでみてくださいね。
労働組合型の退職代行なら失敗がない?
労働組合型だから絶対失敗しないとはいえませんが、民間企業の退職代行サービスより交渉が失敗しづらいです。
労働組合法6〜7条によると、労働組合は団体交渉権があります。残業代・退職日・書類請求を正式に交渉でき、会社が無視すると不当労働行為になるからですね。
労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号) 第六条 交渉権限